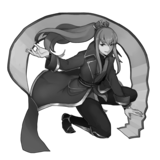親族の仇討ちに奮起する馬超
■ 親族の仇討ちに奮起する馬超
親族の仇討ちに奮起する馬超
まずは、蜀の馬超から見てみましょう。
馬超は西涼の人物です。父は馬騰。西涼は北西の地域で、モンゴルと近い位置にありました。
「赤壁の戦い」にて、劉備(玄徳)と孫権に敗れる曹操。彼は両者への復讐を企む一方で、馬一族からの襲撃を懸念していました。このころ曹操は皇帝を保護していたため、名前を借りて馬騰とその息子(馬超の弟)をおびき寄せます。
馬騰らも曹操を嫌っていたのでこの隙に暗殺しようとしましたが、返り討ちに遭いました。ちょうど西涼にいた馬超はこれに激怒。仲間と協力して、曹操の領土を落とします。
魏の名将や張飛との一騎討ちへ
■ 魏の名将や張飛との一騎討ちへ
魏の名将や張飛との一騎討ちへ
馬超は曹操の名将を次々と破りました。于禁、張コウ、李通、そして許チョ。なかでも于禁と張コウは、のちに五大将軍として選ばれています。許チョも曹操の親衛隊の1人です。この状況を見た曹操は、馬超を恐れて逃げ延びました。
しかし、仲間との揉めごとで曹操撃破のチャンスを失います。さらに妻など一族を皆殺しにされたため、張魯に身を寄せました。このころ張魯は、劉璋と対立していました。そして、劉璋には劉備(玄徳)軍もいます。
やがて馬超は、劉璋に派遣された張飛と一騎討ちに。張飛は劉備(玄徳)の義兄弟であり、関羽と並ぶほどの豪傑でした。100回以上戦ったものの、お互いに一歩も退かなかったのです。
蜀へ下ったその後
■ 蜀へ下ったその後
蜀へ下ったその後
長くなりましたが、曹操軍を次々と破ったことで「錦の馬超」とも呼ばれています。しかし、劉備(玄徳)の配下時代では、鈍りが少しずつ露見していました。
張飛や趙雲らとともに、五虎将軍の1人になった馬超。「定軍山の戦い」では趙雲が仲間を救出したのに対し、曹操の親戚に阻まれて何一つ上手くいかなかったそうです。
このとき既に40代で、その5年後に死去。70代で他界した人物と比べると、少々短く感じます。
曹操の覇道を支えた荀イク
■ 曹操の覇道を支えた荀イク
曹操の覇道を支えた荀イク
続いて、魏の荀イクについてご紹介します。
荀イクは、幼いころから「補佐としての才能がある」と期待されていました。元は袁紹に仕えていましたが、彼からは将来性を感じられずにいたのです。
その後、曹操を見つけて君主を乗り換えます。曹操は、荀イクを心から歓迎しました。
荀イクは、董卓の自滅や仲間の謀反を予測することに成功。さらに、皇帝の保護を助言するなど的確な進言によって、曹操からの信頼を確実に掴んでいきました。治世に関する相談事は、常に荀イクが解決してくれたのです。
官渡の戦い
■ 官渡の戦い
官渡の戦い
袁紹は、曹操に対し無礼な手紙を送りつけたことがありました。曹操はこれに激怒しましたが、荀イクが曹操の長所を丁寧に伝えたことで平静を取り戻します。
さらに、袁紹の元配下であった経験を活かして、彼らの欠点を徹底的に突く荀イク。曹操の兵力は1万だったのに対し、袁紹の兵力はその10倍。しかし、荀イクは「袁紹は立ち回りや軍の配置が下手」と指摘します。こうして、官渡の戦いは曹操が勝利しました。やがて袁紹はこの敗北で病死し、後継者をめぐる争いによって袁家が滅亡します。
曹操からの空箱
■ 曹操からの空箱
曹操からの空箱
魏公という念願の夢がもうすぐ実現する曹操。曹操は部下の進言を受けて、皇帝から9つの贈呈品をいただくことになります。
荀イクがこれに対し、「たいていは無償で国を治めるものですよ」と反対したため、曹操との関係に亀裂が生じました。
この頃、曹操は赤壁での復讐を果たすため、進軍の準備も行なっていました。荀イクは仮病を使って従軍を断ります。(赤壁の戦いは後述)
ある日、荀イクは曹操から箱を受け取りましたが、その中身は空です。「お前はもう要らない」という意味だと悟った荀イクは、ショックのあまり自殺します。死後も、曹操は荀イクを優秀な軍師として祀ることはありませんでした。
赤壁の戦いで活躍した周瑜
■ 赤壁の戦いで活躍した周瑜
赤壁の戦いで活躍した周瑜
最後は、呉の周瑜と黄蓋です。まずは、周瑜からご紹介します。
周瑜は孫権配下の軍師。整った顔立ちから、「美周郎」とも呼ばれていました。
「赤壁の戦い」では、司令官として戦線に立ちました。
劉備(玄徳)軍と同盟を結ぶために、孫権の妹を送り出します(政略結婚)。
諸葛亮と張り合ったものの、大火計を生み出したことで曹操軍の撃退に成功しました。
その際、周瑜は部下の黄蓋を曹操軍の船に載せます。周瑜に殴られ満身創痍で曹操に偽の降伏をすることで、火攻めを仕掛けたのです。
しかし、周瑜はその後も諸葛亮の才知を認めず、ライバル視していた様子が目立ちました。
周瑜の死
■ 周瑜の死
周瑜の死
「天はなぜ同じ時代に諸葛亮を生み出した!」
これは周瑜が最期に遺した言葉です。
周瑜はその後も曹操軍を追い込みました。そこで勝利を掴んだものの、矢傷を負ってしまいます。
さらに諸葛亮の計略によって、荊州の半分を劉備(玄徳)に奪われました。劉備(玄徳)もまた、荊州を返す約束を守らなかったのです。
この怒りで矢傷が裂け、病に倒れます。
荊州を取り返す計略はすべて諸葛亮に見破られたので、なす術もなく世を去ることとなりました。
余談ですが、ドラマ版『三国志』では諸葛亮が周瑜の葬儀に向かう場面があります。あの諸葛亮が泣き叫ぶシーンは貴重でしょう。(もちろん、計略の1つです)
孫家に仕えた猛将 黄蓋
■ 孫家に仕えた猛将 黄蓋
孫家に仕えた猛将 黄蓋
黄蓋は、孫権の父や兄が存命していた頃から仕えていた人物です。力強くも心優しかったため、山賊を鎮圧した際は多くの民が心服したといいます。
赤壁の戦いといえば、黄蓋の存在も欠かせません。「曹操軍の船を焼き払うべく、偽りの投降をする」という計略を周瑜に持ち掛けたのです。
その翌日に周瑜から暴行を受け、計略通りに曹操に投降しました。やがて東南の風が吹いたとき、曹操軍の船に火を放ちます。
この行為を「苦肉の計」と呼びます。日本では「苦肉の策」と言いますが、「一生懸命考えた提案」という意味で使われます。
赤壁での功績を経て
■ 赤壁での功績を経て
赤壁での功績を経て
黄蓋のエピソードは上記の出来事が有名ですが、その後はあまり知られていません。
赤壁での功績は、彼をさらに評価するきっかけに繋がります。
船が炎上したあと、曹操はただちに逃亡しました。黄蓋がその後を追いますが、流れ矢に当たって負傷してしまったのです。
そのまま川へ飛び込み、すくい上げられた黄蓋。しばらくは他所で放置されていましたが、幸い仲間に救出されました。
手当てを受けたのち、より高い階級に昇進します。
黄蓋はさらに優遇されましたが、驕ることなく日ごろの任務をこなしました。
そして周囲の人々は、彼の死後も祀ったのです。
有名な活躍に隠れた未来
■ 有名な活躍に隠れた未来
有名な活躍に隠れた未来
黄蓋は、赤壁での「苦肉の計」がきっかけで着実に昇進していきました。命がけの計略に見合った人生ではないでしょうか。
荀イクや周瑜も、それぞれの君主の下で有名な戦いを成功に導いています。しかし、そのぶん彼らの晩年は儚さが際立っています。君主の手のひら返し・敵の軍師に勝てないストレスは、この時代において軽視できるものではないでしょう。
馬超は曹操軍の名将や張飛との一騎討ちが有名です。これにより五虎大将の1人として選ばれたものの、その後は目立った結果がありません。
素晴らしい活躍をしたその後は、自力ではどうにもならない出来事に苛まれることも。今回紹介した人物の人生は、それを物語っているように思えます。