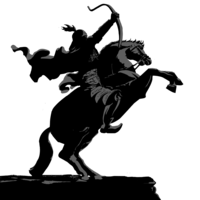荀彧(文若)
■ 荀彧(文若)
荀彧(文若)
荀 彧(文若)は後漢末期の政治家で、魏の曹操(孟徳)に仕えた魏軍の名軍師です。若かりし頃より優れた才能があり、人々は彼の才能を「王佐の才」とうたいました。
名門荀家の出身で、家柄、人柄、品性にも優れており、朝廷の官吏登用制度である孝廉に推挙されて一時期は朝廷の官吏として働きました。
外戚と宦官による汚濁政治が行われていた後漢末の動乱期において、董卓が戦乱を起こすとここぞとばかりに転職を願い出て、官を辞し、名門袁家の袁紹(本初)の配下になりました。実は戦乱が到来することを荀 彧(文若)は予期していたらしく、自分の才能を発揮させられる者に仕えようと何人が候補を絞っていたそうです。
名門袁紹(本初)に身を寄せたものの袁紹(本初)は大業を成し遂げられる人ではないと早々に見切りをつけて、漢第14代皇帝の献帝の代に実権を掌握した曹操(孟徳)に身を寄せました。
曹操(孟徳)多くの献策を行い、その覇業をたすけましたが、魏公就任の件で揉めてしまい、悲惨な末路を迎えました。
荀攸(公達)
■ 荀攸(公達)
荀攸(公達)
荀攸(公達)はいとこの荀 彧(文若)と同じく後漢末期の政治家で、魏の曹操(孟徳)に仕えた魏軍の筆頭軍師です。
荀彧(文若)が曹操(孟徳)に推薦して招かれ、筆頭軍師に任命されました。
董卓暗殺計画に加担して処刑されかけましたが、董卓が王允によって暗殺されたので、死刑執行前に助けだされました。
その後は曹操(孟徳)に仕えて官渡の戦いをはじめとする戦いにおいて大活躍しました。
荀子
■ 荀子
荀子
荀子は中国の春秋戦国時代の末期に斉の襄王(じょうおう)楚の春申君(しゅんしんくん)という
当時の楚国宰相に仕えた文官です。国に忠義を尽くす文官としての顔以外にも、思想家、儒学者としての顔も兼ねそろえていました。彼を師と仰いだ弟子の中には法家思想の大成者である韓非子と秦の始皇帝に仕え名参謀、秦国宰相となった李斯(りし)がいます。李斯は始皇帝の指示のもと、史上初の法治国家を実現させ師匠や学友が目指した「法」によって君主が国家と民を支配する体制を確立しました。
いわゆる荀子は法家や法治国家の土台を築いた人物であり、彼が存在していなければ「法(法律)」によって犯罪者の取り締まりや政治運営、身分制度が定められるようになるのは、もっと後の時代に実現されたことでしょう。
さて、荀子の残した名言、名文、思想は現代を生きる我々はおろか全世界に通づるものがあるので、以下に列挙します。
人生は学び続けること
■ 人生は学び続けること
人生は学び続けること
ある通信講座を主体としている大企業では、自社の名前の前に「生涯学習は~」とうまく耳に残るキャッチフレーズをつけて宣伝しています。その「生涯学習」を初めてうたった人物が何を隠そう荀子であります。彼が残した著書の「荀子」の中には勧学編(学問をすすめる編)という章があり、その中で「人はその一生涯において学び続けることにより、自身の欠点を改善しなければならない」と説いています。ちなみに弟子が師よりも優れた人物になることを意味する言葉に「青は藍より出でて、藍より青し」がありますが、これは同著の中にある「青はこれを藍よりとりて、藍よりも青し」という記述が語源となっています。本来の意味は、学ぶときは自分勝手な学問をしても実にならないので、信頼できる師を得て、その者の下で体系的に学び、かつ正しく礼を身に付けた君子を目指しなさいという教えです。
ちなみに彼が定義している「君子」とは、「礼法を守り、社会を礼法に基づいて牽引する指導者」のことを指します。
礼法による統治を目指す
■ 礼法による統治を目指す
礼法による統治を目指す
彼は君子が学ぶべきものは「礼」であると書いています。また、同著の修身編では「君子は『礼』に従って行動するべき」と説いています。
荀子は古来より人々が受け継いできた「礼」に国家を治めるにあたっての公正な法の精神があると考えました。
そして荀子は理想の国家は王が「補佐する人材」、「礼制」、「論理」、「法律」を制定して治める国家であると説きました。
つまり君主を頂点に礼を正しく身に付けた君子を従わせて、民を法にもとづき支配する国の統治原理に「礼」があると考えたのです。
荀子は残念ながら自分でこの夢を実現することが叶わなかったのですが、弟子の李斯が秦の官僚制度として実践し、漢代以降の歴代王朝が官僚に儒学を修めた者を採用したことで、後世の国家体制の根幹になり実現しました。
実力主義・成果主義
■ 実力主義・成果主義
実力主義・成果主義
営業職やクリエイティブな仕事をしている方にはおなじみの歩合制という体制の根本的な考え方です。しかし荀子は営利的な意味でなく、社会的な意味で実力主義と成果主知の有効性を説いています。少し残酷ですが彼が示したかったことは「王侯、士大夫の子孫であっても礼儀を正しく心得ていない者は容赦なく庶民に落とす。庶民の出身者であっても文芸学問を修め、正しい行動や礼儀をわきまえている者は卿や士大夫に昇進させましょう」と提唱しました。
性悪説
■ 性悪説
性悪説
荀子は人間の本性は「悪(利己的存在)」であると説いています。性悪説をかみくだいて説明すると、「人間は生まれながらに悪の性質をもってこの世に生を受け、その本性を後天的な努力によって修正し、善の道へ向かう」と考えました。孟子の提唱した性善説の「人間の本性は善で、生まれ育った環境や周りをとりまく親や友達、上司などの影響をうけて悪の要素を覚えてしまう」という考え方とは相反しています。
そのため彼は孟子の性善説を批判していました。
まとめ
■ まとめ
まとめ
荀 彧(文若)と荀攸(公達)は荀子を祖とする荀家の名に恥じない大変立派な英雄です。双方は君主である曹操(孟徳)の覇業をたすけ、後漢の汚濁政治に終止符をうちました。とくに名門袁紹(本初)と曹操(孟徳)が争った官渡の戦いにおいては、圧倒的な兵力差と底をついた兵糧によって曹操(孟徳)でさえも泣きごとを吐いてしまいました。
そのとき、君主をあえて叱咤激励して闘志を呼びさまし、兵糧や内政を滞ることなく行って
曹操(孟徳)を安心して戦いに専念させたのは荀 彧(文若)。
大胆かつ巧妙な作戦を立てたり、最適なタイミングで用兵を助言するなど戦場で君主を支え続けたのは、荀攸(公達)です。
彼らがいなければ曹操(孟徳)も覇業を成し遂げることは無理であったことでしょう。それだけ両者の存在は曹操(孟徳)率いる魏にとってなくてはならない存在だったのです。