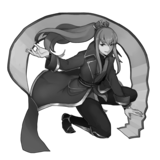周瑜(公瑾)の周りの人物について
■ 周瑜(公瑾)の周りの人物について
周瑜(公瑾)の周りの人物について
周瑜(公瑾)を語る上で欠かすことができない人物が孫策(伯符)です。孫策(伯符)は孫堅(文台)の長男にして孫権(仲謀)の兄にあたります。どちらも読みが「そんけん」と紛らわしいのですが、最初に江東(後の呉にあたる地域だと思ってください)の君主として君臨したのが孫堅(文台)ですが、彼が早くして亡くなったため後を継いだのが孫策(伯符)で、さらにその孫策(伯符)が早死にした為弟の孫権(仲謀)が呉の君主となったわけです。もちろんこの間に紆余曲折があり、親子だからと言って簡単に事が進んだわけではありませんがここでは割愛します。
さて、この孫策(伯符)ですが、彼は3000の兵から建国を目指していました。その際にまず右腕として迎え入れたのが周瑜(公瑾)です。二人は同い年で幼馴染。孫堅(文台)が戦争に行くたびに孫策(伯符)を周瑜(公瑾)の父に預けていたため親同士も仲が良かったわけです。
さらに周瑜(公瑾)の妻と孫策(伯符)の妻が姉妹という事もあり、最終的には義兄弟となっています。
呉の基盤はまさにこの二人の鉄則の絆からできています。孫策(伯符)亡き後も孫権(仲謀)を支え続けたわけですが、孫権(仲謀)にしてみても兄の友達(更には義兄弟)という事もあり周瑜(公瑾)には頭が上がらないことも多々あったことでしょう。
周瑜(公瑾)のルックスについて
■ 周瑜(公瑾)のルックスについて
周瑜(公瑾)のルックスについて
三国志で最強の人物は誰かという話になると「呂布(奉先)」という答えが返ってくることが多いのですが、では「三国志で一番の美男子は?」という質問をすると帰ってくる答えは「周瑜(公瑾)」だったようです。彼の美貌を称え「美周郎」というあだ名があったほどです。妻が天下の美女「小橋」ということも、彼が美男子だったということを証明する要素の一つになるのではないでしょうか。
諸説様々ではありますが、彼のルックスにより人々から親しまれたというのはあながち間違いではないと思います。女性ほど男性のルックスに対しては目を光らせられることはありませんが彼の成功の元に「三国志一のルックス」というのは多少なりともあったことでしょう。
周瑜公瑾は、若くして成功を収める
■ 周瑜公瑾は、若くして成功を収める
周瑜公瑾は、若くして成功を収める
孫策(伯符)の旗揚げを共にした周瑜(公瑾)ですが、その年齢はわずか21歳です。いくら孫策(伯符)や周瑜(公瑾)の生まれがいいといっても親を亡くしているわけで、この年齢での旗揚げというのは求心力、決断、自信があったことが分かります。
さらに周瑜(公瑾)は参謀に二張(張昭(子布)と張紘(子綱)=同じ張がついても親族ではありません)を推薦し孫策(伯符)は了承しました。
特に張昭(子布)は内政のスペシャリストで最終的には孫権(仲謀)のご意見番的存在となり81歳まで生き呉を指させ続けました。
そういった文官をどっしり構えることができたということもあり孫策(伯符)、周瑜(公瑾)は快進撃を広げ領土を徐々に広げていくことに成功しました。
3000人からの旗揚げですが、わずか5年で呉の礎を築いたわけです。このスピード感あふれる成長はこの二人にしかなしえなかったことでしょう。(同じく天才とされている諸葛亮(孔明)は勢い任せというより理詰めで来るためこうはいかなかったはずです)
最大の見せ場、赤壁の戦い
■ 最大の見せ場、赤壁の戦い
最大の見せ場、赤壁の戦い
そして周瑜(公瑾)を語る上で避けては通れないのが赤壁の戦いです。呉の重鎮(上記で挙げた張昭(子布)も含まれます)が曹操軍には敵わないから降伏しようという中、頑として戦う姿勢を見せていたのが周瑜(公瑾)です。
劉備軍と連携を図り、次から次へと知略を練り、数で圧倒的に上回る曹操軍を倒してしまったのです。三国志で最大のジャイアントキリングで周瑜(公瑾)が伝説化された一戦です。
分かりやすくいってみれば高校球児が隠し玉を使ったり、雨天をうまく利用したりしてプロ野球チームに勝ってしまうといった感じでしょう。その際に監督を務めていたのが周瑜(公瑾)だと思ってください。
諸葛亮(孔明)が最大のライバル
■ 諸葛亮(孔明)が最大のライバル
諸葛亮(孔明)が最大のライバル
そんなスーパーヒーロー的存在の周瑜(公瑾)ですが、やはり諸葛亮(孔明)は難攻不落の相手でした。孫権・劉備連合軍を結成した際に彼の才能を見抜き度々暗殺をたくらみますがのらりくらりと交わされてしまいます。
常に諸葛亮(孔明)の知略の方が一歩上を行き、ライバルはいう物の、常に負けているというのが正史の記述でのデータです。その証拠に「なぜ天は諸葛亮(孔明)なぞ生まれさせず、わたしひとりにしてくれなかったのだ」と言っています。このセリフは周瑜(公瑾)が諸葛亮(孔明)に敵わないことを示唆しているといっても過言ではないでしょう。
とはいえ、必ずしも諸葛亮(孔明)が周瑜(公瑾)を上回っていたとは思えません。確かに知略という面に限っていえば諸葛亮(孔明)が勝っていたでしょう。しかし周瑜(公瑾)は戦闘力もかなりありました。
置き換えるのは難しいかもしれませんが、野球選手でいうと諸葛亮(孔明)が25勝を挙げるピッチャーで、周瑜(公瑾)は15勝を挙げるピッチャーです。しかし周瑜(公瑾)はバッターとしても活躍ができ、25本のホームランを打つことができるのです。こうなれば「諸葛亮(孔明)の方が圧倒的に優れている」ということができないと思うのは私だけではないはずです。
周瑜公瑾は、音楽の腕前も恐ろしいほどあった
■ 周瑜公瑾は、音楽の腕前も恐ろしいほどあった
周瑜公瑾は、音楽の腕前も恐ろしいほどあった
最後に周瑜(公瑾)を語る上で外せないのが音楽についても達人だったということです。自身が演奏する際にはプロ顔負けの演奏をしたようです。さらに演奏者が音を間違えると必ず演奏者の方を振り返ったと言われています。恐らく今でいう「絶対音感を持っていた」ということになります。
その能力が戦に生かされていたかどうかは定かではありませんが。もしかしたら地方の豪族を束ねる際に役になった可能性は否定できません。
周瑜公瑾 まとめ
■ 周瑜公瑾 まとめ
周瑜公瑾 まとめ
周瑜(公瑾)について簡単に紹介しましたが、彼の凄さについてお判りいただけたら幸いです。戦だけでなく、ルックス、家柄、趣味、友人など全てを加味すると彼の右に出るものがなく、まさに「三国志最強の男」といっても過言ではないのではないでしょうか。現代にしてみれば「医師免許を持っているオリンピック金メダリストのイケメン俳優(そして妻が超美人の女優)」という位とにかく万能な人間なのです。
しいて言えば「短命だった」という欠点を持ってはいるものの生きている間は何から何まで非の打ちどころのない人物。それが周瑜(公瑾)なのです。