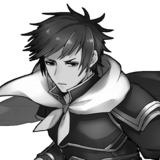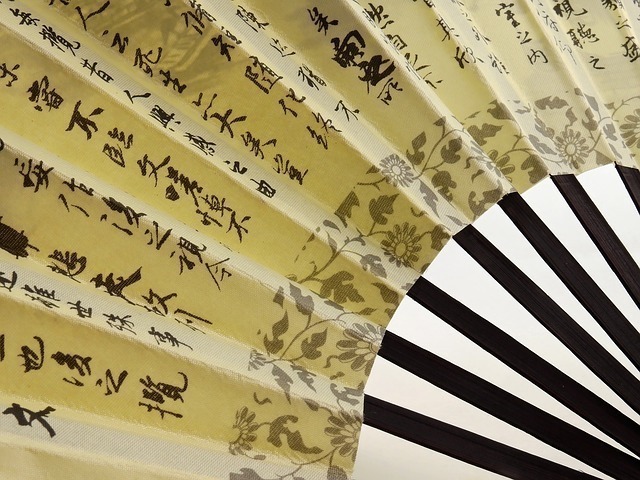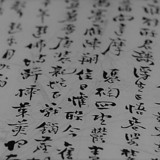魏一人目、典韋
■ 魏一人目、典韋
魏一人目、典韋
典韋は三国志の名だたる武将の中でも最も戦闘力が高い一人でした。そして彼は曹操(孟徳)のボディーガードを務めました。「典韋がいる限り曹操(孟徳)の暗殺は絶対に無理」と言われていたほどでした。
曹操軍に裏切り者が少なかったのも彼の功績だといわれています。典韋は家柄がよかったわけではありません。それどころか若いころゴロツキで、今でいう「ヒットマン」のようなことをしていました。町の顔役(今でいう県議会議員)とその妻を殺した彼は堂々と門を出ました。
大騒ぎとなりましたが典韋の怖さに誰も近づくことができなかったというエピソードがあります。
そんな典韋ですが曹操(孟徳)の片腕ともいえる夏侯惇(元譲)にスカウトされ曹操(孟徳)のボディーガードをすることになったのです。
勤務態度はいたってまじめで、曹操(孟徳)のそばに立ち続けた典韋はまさにボディーガードの鏡と言えました。典韋は張繍に攻め込まれた曹操(孟徳)を逃がし追っ手を防いだのですが、そこで死にました。身には無数の傷を受け失血死したといわれています。まさに武蔵坊弁慶のような死に方だったのでしょう。
こんな魅力たっぷりの武将が魏の一人目の人物です。
呉一人目、黄蓋(公覆)
■ 呉一人目、黄蓋(公覆)
呉一人目、黄蓋(公覆)
呉の将軍黄蓋(公覆)といったらやはり赤壁の戦いで勝利を導いたエピソードが一番強いですが、その前に黄蓋(公覆)という男が将軍になるに至った経緯について紹介します。
黄蓋(公覆)は若くして父を亡くし、貧しい暮らしの中で兵法を学びました。知力に優れ行動力もあったためすぐに抜擢され江東の統治官として力を発揮していました。反乱が勃発すると必ず黄蓋(公覆)が派遣され鎮圧したといわれています。
しかし彼は武力で高圧的に反乱を抑えたわけではなく、弱いものに対し手厚い保護の手を差し伸べたため反抗していた者たちも彼に対し心を開くようになりました。それでいて戦も得意で孫堅(文台)、孫策(伯符)といった戦好きの君主を支えました。
そして極めつけが赤壁の戦いです。レッドクリフを見た人ならご存知だと思いますが火責めで呉・蜀連合軍は優位に立ちます。この火責めを提案したのが黄蓋(公覆)です。降伏したかのように見せかけ魏軍に近づき軍戦に火をつけたのです。それを成功させた大きな要因が「演技」です。まず呉の君主孫権(仲謀)に自分を半殺しの目に合わせ、曹操(孟徳)に忠誠を誓うふりをしたのです。
黄蓋(公覆)の死後、彼の肖像画を描いて季節ごとにお祭りをしたというエピソードがあります。
蜀一人目、黄忠(漢升)
■ 蜀一人目、黄忠(漢升)
蜀一人目、黄忠(漢升)
三国志で老将と言って真っ先に思い浮かべられる人物が黄蓋(公覆)と黄忠(漢升)です。二人とも「黄」がついて紛らわしいです。
黄忠(漢升)の出生については不明なので正確な年齢は知られていませんが、とにかく老いていたということだけは確かなようです。老いてなお戦闘力に長けていて並み居る猛者たちを一騎打ちで葬ってしまう実力の持ち主でした。
彼の武勇伝は尽きることがないのですが、それに加え人格者でもあるといわれていました。黄忠(漢升)は関羽(雲長)と同等の後将軍に任命された際、関羽(雲長)は老人と同格であることにひどく腹を立てました。それに対し劉備(玄徳)が何とか説得し、関羽(雲長)を説得しました。
この際黄忠(漢升)の発言に対してはフォーカスされていませんが関羽(雲長)が腹を立てたことに対し「何を!この青二才が!」となってもいいくらいの実力の持ち主だったのに、きっと笑って見ていたのでしょう。
三国志演義では黄忠(漢升)が70歳を過ぎているにも関わらず魏の中でもトップクラスの夏侯淵(妙才)を打ち取るという歴史的勝利を収めました。
まさに会社を退職した人たちの希望の星ともいえるのが黄忠(漢升)ではないでしょうか。
魏二人目、李典(曼成)
■ 魏二人目、李典(曼成)
魏二人目、李典(曼成)
戦争では力が強く相手を葬る猛々しい武将が目立ちますが、その一方で兵糧輸送などの後方支援は地味ですが、非常に重要な役割を担っています。そんな後方支援のエキスパートが李典(曼成)です。もともとは武芸より学問を好んでいて、様々な書物を読み漁り儒学の知識も備えていました。
そんな李典(曼成)ですが、父、兄を亡くし3000人の兵を纏めなければいけない立場になりました。そうなると「学問が好き」とは言えない状況になってしまい曹操(孟徳)の軍門に下ることになったのです。
李典(曼成)は冷静で用心深く、戦況を見極められるということもあり将軍として理想的な人材という高評価でした。
張遼(文遠)とは仲が悪かったが「仕事に私情ははさまない」とする李典(曼成)は二人で合肥に攻め入る呉軍を蹴散らしました。
そんないぶし銀的な活躍をする李典(曼成)はいかがでしょうか。
呉二人目、甘寧(興覇)
■ 呉二人目、甘寧(興覇)
呉二人目、甘寧(興覇)
人材登用と言ったら曹操(孟徳)の十八番のように思われますが、呉の君主孫権(仲謀)もなかなかなものです。特に彼は誰もが手を付けたくない呂蒙(子明)、甘寧(興覇)といったどうしようもないゴロツキを将軍にまで押し上げてしまったのです。
恐らくレッドクリフで中村獅童が演じた甘興は甘寧(興覇)がモデルです。さらにキングダムを読んでいる人に分かりやすく言うと「桓騎」です。やくざの親分として暴れまわっていた甘寧(興覇)はこのままではまずいと思い更生しました。
孫権(仲謀)は周瑜(公瑾)や呂蒙(子明)に説得され特別待遇で甘寧(興覇)を迎えるとその期待以上の働きをし、赤壁の戦いでは勝利に大きく貢献しました。
奇襲が得意で度々魏に損害を与えていたので孫権は「魏には張遼(文遠)がいるが呉には甘寧(興覇)がいる」といったくらいです。
こんな見事なジョブチェンジを果たした張遼(文遠)はいかがでしょうか。
蜀二人目、姜維(伯約)
■ 蜀二人目、姜維(伯約)
蜀二人目、姜維(伯約)
姜維(伯約)はもともと魏兵でしたが、彼の上司が、部下の姜維(伯約)が敵軍と内通しているのではないかと信じられなくなったため城から追い出してしまいました。やむなく蜀に降伏した姜維(伯約)ですが、孔明はそんな彼の能力を見抜き将軍に任命しました。
姜維(伯約)はその期待に十二分にこたえる形で関羽(雲長)、張飛(翼徳)、趙雲(子龍)亡き後蜀軍次世代エースとして大車輪の活躍をしました。
魏が蜀に攻め込んできて君主・劉禅(公嗣)が魏に降伏した後も姜維(伯約)だけはあきらめずに抗い続けました。結局捉えられ殺されてしまいましたが、最後の最後まで魏に抗った姜維(伯約)は見事ではないでしょうか。
諸葛(孔明)は生前、姜維(伯約)を「才能は馬良以上」「軍事を非常によく理解している」「仕事に忠実で細かなことにもよく気が付く」と褒め千切っています。なんでも自分でやらなければいけない諸葛亮(孔明)の目には姜維(伯約)が救世主に見えたのではないでしょうか。
投降したから自分は蜀を支えるという熱い思いを持っていた男姜維(伯約)はいかがでしょうか。
まとめ
■ まとめ
まとめ
上記6人のストーリーを目にして、「この国を推したい!」と思う人が一人でも生まれてくれたら幸いです。
三国志は他にも魅力ある将軍、軍師が沢山います。今までの固定観念を取っ払って新たに推しメン、推し国を作ってみるのも楽しいと思います。