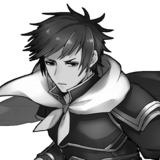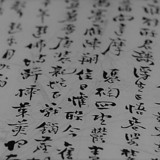孫堅に仕える
■ 孫堅に仕える
孫堅に仕える
黄蓋、字は公覆。荊州南部、零陵郡泉陵県の出身です。祖先は荊州北部に住んでいたようですが、黄蓋の祖父の代から南下して零陵郡に移り住んでいます。零陵郡は荊州の南端にあり、交州近郊の僻地です。異民族も多く暮らしていたと思われます。
黄蓋はそこで貧しいながらも地道に勉学に励み、役人として生計を立て、さらにその努力を認められて孝廉に推挙され、公府に召し出されています。
孫堅に従うようになったのは、孫堅が涼州で辺章や韓遂の反乱の鎮圧から戻った後になるでしょう。荊州長沙郡で区星が一万の兵を率いて反乱を起こしたタイミングです。零陵郡と長沙郡はともに荊州南部、湘水沿いにあります。孫堅はこの長沙郡の太守となるのです。そして黄蓋に出会うことになります。
反董卓連合への参戦
■ 反董卓連合への参戦
反董卓連合への参戦
孫堅は長沙郡の反乱を鎮めた後、さらに郡境を越えて零陵郡、桂陽郡で反乱を起こした賊の周朝と郭石を討伐します。恐らく黄蓋は零陵郡を守るために必死に戦ったはずです。そこに越権行為であることを無視して、孫堅の軍勢が援軍にきました。孫堅のおかげで故郷が救われたことで恩を感じ、黄蓋は孫堅に仕えることを決めたのではないでしょうか。
190年に孫堅は董卓を討伐するために長沙郡を出立します。黄蓋も同行しています。孫堅らは袁術と合流。董卓配下の猛将・華雄を討ち、洛陽に一番乗りを果たしました。黄蓋もその武功により別部司馬に任命されています。軍務副官ですね。
ちなみに孫堅の配下には猛将が四名おり、その四名をして「四天王」と呼んだりもします。黄蓋、程普、韓当、祖茂の四名です。三国志演義では黄蓋は、武将としては珍しく「鉄鞭」の使い手としても紹介されています。
孫策に仕える
■ 孫策に仕える
孫策に仕える
孫堅が191年に戦死すると、その軍勢は孫堅の一族の孫賁に率いられ、袁術の保護下に入っています。その後、孫堅の長子・孫策も袁術に認められ、将として兵を与えられて活躍します。黄蓋がどの時点で孫策の軍勢に合流することを許されたのかは不明ですが、孫策が江東を支配し、江夏の黄祖を攻めたときには黄蓋の名前もあります。黄蓋は常に前線に立って各地を転戦して諸城を攻略したと記録されています。
孫権に仕える
■ 孫権に仕える
孫権に仕える
孫策は200年に刺客に襲われ、その傷がもとで病没します。跡を引き継いだのは弟の孫権でした。黄蓋もそのまま孫権に仕えました。
孫権が支配する揚州南部には異民族・山越が多く住んでいます。彼らは孫権に対して反抗的な態度を取り続けることになります。乱れた県があると黄蓋が県長として出向きました。合計して九県の県長を務めたそうです。
石城県の県長を務めていた頃に有名な話が残っています。ここは役人の統制すらとれていませんでした。そこで役人の監督に二人の掾を抜擢します。事前に不正があったら鞭打ちぐらいではすまさぬと訓令しました。しかし黄蓋が山越討伐に精を出し、文章などに目もくれないことから、二人の掾は次第に怠惰になります。実は黄蓋はしっかりと仕事ぶりを確認しており、不正の証拠もつかんでいました。そして事例を並べて詰問し、罪を認めさせた後に処刑しました。他の役人たちは震えあがったそうです。完全に見せしめですね。黄蓋のこの徹底した統治ぶりは全県に広まったといいます。
人徳者としての名声
■ 人徳者としての名声
人徳者としての名声
黄蓋は乱れた九県の県長を務め、そのすべてに平穏を取り戻しています。その功が認められ、黄蓋は丹陽郡の都尉に任命されました。郡の軍政官です。その活躍ぶりは「強きを挫き、弱きを助ける」ものだったそうです。最初は敵対していた山越族もそんな黄蓋を慕って帰順してきています。
部下からも慕われており、戦場では兵は黄蓋のため、先を争って戦っていたといいます。
曹操もそれを聞いていただけに、208年の赤壁の戦いでは、黄蓋の投降を喜んで迎えたのでしょう。黄蓋の離脱は一部将の裏切りでは済まないような影響力を持っていたからです。
「苦肉の策」
■ 「苦肉の策」
「苦肉の策」
黄蓋は自分の投降を信じさせるために周瑜と示し合わせて、棒叩きの刑にあっています。曹操は密偵からこの報告を聞いて、黄蓋の投降を信じました。ここから、自らの体を犠牲にしてでも起死回生の一手を打つことを「苦肉の策」と呼ぶようになったのです。
苦肉の策は「三国志演義」の脚色でしょうが、黄蓋が偽りの投降を用いたことは確かです。黄蓋が曹操に送った書簡には「衆寡敵せず、あなたにはかないません。しかし周瑜と魯粛だけは馬鹿正直で頭が固く、そのことを理解できていません」と記されています。歳若で無能な周瑜の指示に従っていることに我慢できないということなのでしょう。曹操は黄蓋の寝返りに対し、前例のないほどの爵位と褒美を与えると約束しています。
赤壁の戦いの火計
■ 赤壁の戦いの火計
赤壁の戦いの火計
黄蓋は、蒙衝艦と闘艦数十隻に柴や枯草を積み、油を注ぎ、幔幕でおおって隠し、出発します。さらに小型船も後ろに繋いでおいて脱出用としました。
そして「降伏します」ということを部下たちに叫ばせて曹操の陣に近づくと、いっせいに船に火を放ち、曹操の陣営の船団に衝突させていきます。強風にあおられ、曹操側は岸辺の軍営まで焼かれました。ここで周瑜が軽装の精鋭軍を率いて曹操を追撃し、大勝利することになります。
黄蓋はこの功によって「武鋒中郎将」に任命されています。これだけの成果をあげて、まだ准将軍とは納得いきませんが、黄蓋は素直に受け入れて孫権に忠誠を誓っています。黄蓋が偏将軍となったのはこれより後の話になります。
まとめ、黄蓋の死
■ まとめ、黄蓋の死
まとめ、黄蓋の死
赤壁の戦いでは、火計が成功した後、流れ矢に当たって寒水に落ちています。味方の兵に救われましたが、それが黄蓋だとは気が付かなかったようで、厠に捨て置かれたそうです。このとき黄蓋が声を振り絞って叫んだ名前が、古参の将「韓当」だったそうです。韓当はその声に気が付き、涙ながらにその衣服をとりかえたと伝わっています。韓当が気付かなければ黄蓋は凍死し、赤壁の戦いで命を落としていたことでしょう。
最終的には黄蓋は戦場で死ぬことはなく、太守として任務につきながら病没しています。
孫権は皇帝に即位したときに黄蓋の生前の功績を称えて、黄蓋の子の黄柄を関内侯に封じています。