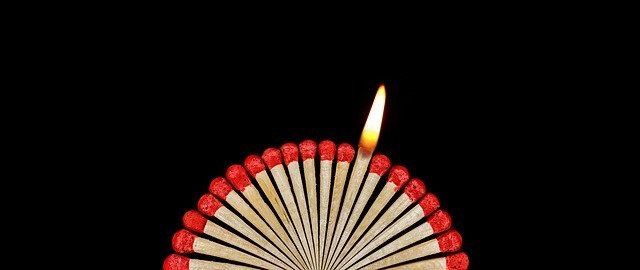【諸葛亮】10万本の矢
■ 【諸葛亮】10万本の矢
【諸葛亮】10万本の矢
三国志でピンチを打破したエピソードと言えば諸葛亮の「10万本の矢」です。このエピソードは赤壁の戦いの際に起こったエピソードとなっています。赤壁の戦いでは、蜀と呉が手を組むのですが、呉の周瑜は蜀の諸葛亮を警戒していました。そこで、無理難題を押し付けて処断してしまおうと考えていたのです。その無理難題とは、10万本の矢を調達するというものです。もちろん、当時の技術では矢の大量生産は不可能であり、実質10万本の矢を調達するのは不可能な状況と言えます。そんなピンチの中、諸葛亮はきっちり10万本以上の矢を調達したのです。
諸葛亮は何艘もの小舟を用意させ、大量の藁人形を詰めておきました。そして、その小舟を曹操陣営に向かわせます。これに対し、曹操陣営は奇襲だと思い一斉に矢を射かけるのです。射かけられた矢は藁人形に突き刺さります。その後、小舟を反転させさらに矢を射させてから、自陣に引き返しました。諸葛亮らは藁人形に刺さった矢を引き抜き、10万本以上の矢を調達したのです。こうして、諸葛亮はピンチを自分の頭脳で切り抜けたのです。このエピソードから、通常なら無理と思われるピンチでも、頭を使えば打破することができるということを学ぶことができます。
【諸葛亮】死せる孔明生ける仲達を走らす
■ 【諸葛亮】死せる孔明生ける仲達を走らす
【諸葛亮】死せる孔明生ける仲達を走らす
同じく諸葛亮のエピソードである「死せる孔明生ける仲達を走らす」も、ピンチを脱出する方法を学ぶことができます。このエピソードは、蜀と魏の戦いである五丈原の戦いで起こりました。五丈原の戦いは俗に言う「北伐」であり、諸葛亮が指揮を執っていました。しかし、諸葛亮は五丈原の戦いの最中に病疫してしまいます。魏の司馬懿は諸葛亮の死を悟り、撤退する蜀軍を追い打ちするのです。まさに、蜀軍にとってはピンチと言えます。
しかし、諸葛亮は死ぬ前に策を授けていたのです。魏軍の追撃に対し、蜀軍は反撃に出ます。そして、諸葛亮が作らせていた自身の木像を見せることで、諸葛亮は亡くなっていないと思わせ、司馬懿を撤退させたのです。つまり、諸葛亮は自身の死によるピンチまでも、策略によって打破したのです。しかも、自分の死を利用して蜀軍のピンチを乗り切らせたと言えます。このエピソードから、ピンチを脱出するためには、利用できるものはすべて利用すべきという教訓を得ることができます。
【黄蓋】苦肉の策
■ 【黄蓋】苦肉の策
【黄蓋】苦肉の策
日本でも使われる故事成語の「苦肉の策」も三国志にゆかりがあり、ピンチを打破するためのヒントを与えてくれます。三国志で苦肉の策と言えば、赤壁の戦いで黄蓋が周瑜に献じた偽計が有名です。赤壁の戦いで蜀と呉は曹操軍の艦隊を焼き払う作戦でした。黄蓋はあえて呉の司令官である周瑜を罵倒し、周瑜は黄蓋を鞭打ちの刑にしたのです。黄蓋はその後、曹操軍に投降しようとします。曹操軍の間者は一連の出来事を報告しており、黄蓋の投降を受け入れるのです。しかし、この投降は偽装であり、黄蓋は艦隊内部から火を放ち、艦隊を焼き払うことができたのです。
苦肉の策とは、「人は自分で自分を害するようなことはしない」と考え、害を受けた人がいれば、それは他人によるものだと思う心理を利用した策のことを指しています。黄蓋の苦肉の策では、周瑜に罵倒して鞭打ちの刑を受けることで、自分を周瑜に害させて、曹操軍への投降が本気であると騙そうとしたのです。赤壁の戦いでは、蜀・呉の連合軍は兵力で負けており、戦いで負ければ領地を蹂躙される恐れがあってピンチでした。そのピンチを打破するために苦肉の策を使ったのです。このエピソードから、ピンチを乗り越えるためには、苦肉の策でも試す必要があることを教えてくれます。
【劉備(玄徳)】長坂の戦い
■ 【劉備(玄徳)】長坂の戦い
【劉備(玄徳)】長坂の戦い
劉備(玄徳)のピンチと言えば、「長坂の戦い」が挙げられます。そして、この長坂の戦いでもピンチでの対応について学ぶことができるのです。長坂の戦いとは、劉備(玄徳)の逃走に対して曹操軍が長坂で追いつて戦闘となったものです。このときの劉備(玄徳)はまさにピンチであり、実際に劉備(玄徳)の妻である糜夫人と嫡男の阿斗(後の劉禅)らは生け捕りにされており、趙雲が阿斗を救ったというエピソードまであります。それほどまでに切羽詰まった状況だったのです。
そんなピンチな状況の中、劉備(玄徳)はひたすら逃げます。妻や子供を置いてでも逃げたのです。これは、劉備(玄徳)には漢王朝の再興が最優先事項だったからです。そのためには、死ぬわけにはいきません。そのため、ひたすら逃げたのです。このエピソードから、大望を成し遂げるためには、ピンチから逃げ出すのもありだと学ぶことができます。重要なのは望みを叶えることであり、ピンチを耐え忍ぶことができれば、その後チャンスはあるのだと考えさせられるエピソードです。
【曹操】赤壁の戦い
■ 【曹操】赤壁の戦い
【曹操】赤壁の戦い
三国志の見せ場である赤壁の戦いでは、曹操がピンチになっています。しかし、曹操もピンチを乗り越えています。赤壁の戦いで、曹操軍は大敗を喫します。そして、敗走する曹操の前に関羽が立ちはだかったのです。まさにピンチだったのですが、関羽は曹操を見逃したことで、曹操はピンチを脱することができたのです。
実は、過去に関羽は曹操に降伏しています。これは劉備(玄徳)の妻子を守るためだったのですが、この際に曹操は関羽を厚く遇したのです。その恩があったため、関羽は曹操を見逃したとされています。このエピソードから、ピンチを打破するためには、日頃の行いが大事であることがわかります。日頃から恩を売っておくことで、ピンチのときに助けてくれることがあるのです。今後ピンチに陥った際のために、日頃から良い行いを心がけるべきでしょう。
ピンチ脱出法まとめ
■ ピンチ脱出法まとめ
ピンチ脱出法まとめ
今回は、三国志から学ぶことができるピンチの脱出法を紹介してきました。三国志には様々なエピソードがあり、登場人物がピンチになることも多々あります。その際に、どうやってピンチを乗り越えたのか知ることで、ピンチを打破するヒントを得ることができるのです。そして、そのピンチを乗り越えるヒントは、現代でも利用することができることも多くあります。そのため、三国志のエピソードから、ピンチを打破するヒントを学んでみてください。また、三国志からはピンチの打破以外にも、多くのことを学ぶことができます。ぜひ、様々なことを三国志から学んでみてください。