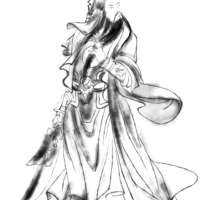どの会社に就職するのか
■ どの会社に就職するのか
どの会社に就職するのか
現代でもどの会社に就職するのかは、人生においてとても重要な問題です。同じような仕事をこなしても、勤める会社によって評価も違えば、給与も差が出ます。キャリアアップも変わってくることでしょう。
一流企業に勤めれば労働条件や給与面などは安定していますが、組織の歯車としての役割だけを要求され、個性を発揮できないかもしれません。
逆に小さな会社であれば、いつ倒産するのかという不安があります。労働環境も劣悪で、給与水準も低いでしょう。しかし任される仕事は大きく、やりがいはあるかもしれません。
現代でも、大きく有名な会社であっても絶対安泰という世の中ではなくなってきました。グローバル化によって国際競争が激しくなり、淘汰されていく一流企業も出てきていますし、一躍大企業の仲間入りを果たすベンチャー企業も誕生しています。
三国志の時代では誰に仕えるのかが重要
■ 三国志の時代では誰に仕えるのかが重要
三国志の時代では誰に仕えるのかが重要
それでは三国志の時代はどうだったのでしょうか。
群雄割拠の戦国時代であり、激動の時代です。誰に仕えるのかによって運命は大きく変わります。現代でいう、どの会社に就職するのか、と同じような問題ですね。
現代では会社が倒産しても、別の会社に再就職すればいい話ですが、戦国の世では主君の滅亡は自分たちの滅亡にもつながる可能性がありました。「生き死に」の問題となるだけにより慎重にならざるをえません。
今回は三国志に登場する有名な君主数名をご紹介しながら、仮に仕えていたらどうなのかを検証していきましょう。
もし「暴虐の王・董卓」に仕えたら
■ もし「暴虐の王・董卓」に仕えたら
もし「暴虐の王・董卓」に仕えたら
「欲望の限りを尽くすことが許される職場」それが董卓に仕えるメリットでしょう。パワハラ、セクハラ、なんでもありです。出世のために同僚を蹴落とすことなど当たり前、能力なんて関係ありません。董卓に忠誠を誓い、董卓のご機嫌をうかがっていればOKです。
取引先に対しても話術や交渉術など必要ありませんし、約定なんて気にすることもないのです。すべて恫喝で片が付きます。多少ミスをしても力づくでもみ消すことが可能です。
悪事を働くことに罪悪感がないのであれば、まさに天国といえるでしょう。しかし、正義の心や良心がわずかでもあるのであれば、地獄のような劣悪な環境です。さらに、同僚や部下にいつ寝首を掻かれることになるか、不安な日々を過ごすことにもなりそうです。
そして、「悪は必ず滅ぶ」の言葉のように、いずれ報いを受けて消滅していきます。
もし「仁徳の王・劉備(玄徳)」に仕えたら
■ もし「仁徳の王・劉備(玄徳)」に仕えたら
もし「仁徳の王・劉備(玄徳)」に仕えたら
「小さな勢力ながら志は高く、個性も尊重してくれる職場」それが劉備(玄徳)に仕えるメリットでしょう。冷酷な指示もなく、正義を貫くことができます。さらに、多くの人々に認められ、歓迎されます。誇り高く生きていくことができるはずです。
しかし、戦争に弱いというデメリットもあります。立ち上がれば潰され、さらに立ち上がれば潰される。その繰り返しになります。戦場で命を落とす可能性が高く、生活場所も転々とすることになるでしょう。
生き残るためには必死にならねばならず、現代のブラック企業など比較にならないような労働時間や労働環境になります。しかし、不平不満など言える状態ではありません。君主である劉備(玄徳)自らがそうであるからです。
お金や出世よりもやりがいを求める人にはピッタリでしょう。
そして最終的には巨大勢力となります。努力が報われる日が訪れるのです。そこまで生き残るためには強運も必要になるかもしれません。
もし「万能の王・曹操」に仕えたら
■ もし「万能の王・曹操」に仕えたら
もし「万能の王・曹操」に仕えたら
「とにかく能力主義、成果主義で、勤続年数など関係なく、若くても結果を出せる力があれば一気に出世することが可能な職場」、それが曹操に仕えるメリットでしょう。序盤は過酷な戦争が連日のように続く事態になりますが、やがて最強の勢力となり、盤石になります。
朝廷をも支配する力を持つことになり、どのような身分の出生であっても成果を出せれば国家権力の中枢で活躍することも可能です。
ただし、曹操自身が天才であり、人の能力を見抜く力に長けています。無能というレッテルを貼られると、どんなに媚びへつらっても出世することはないでしょう。さらに自分よりはるかに経験の少ない若者たちにどんどん抜かれていき、その者たちに顎でつかわれ、プライドを傷つけられることになるかもしれません。
もし「地方自治の王・孫権」に仕えたら
■ もし「地方自治の王・孫権」に仕えたら
もし「地方自治の王・孫権」に仕えたら
「地方を活性化することに情熱を注ぎ、合議制を重んじる職場」それが孫権に仕えるメリットでしょう。開発プロジェクトがどんどん発案され、見違えるように整備されていきます。意見も活発に飛び交い、効果があると採決されれば、アイディアはすぐに実行に移されます。勢力的にも危機的な状況に陥ることがほとんどなく、安心して仕事ができるでしょう。孫権は能力が高く、人望のある者を抜擢する傾向がありますので、上司にも恵まれるはずです。
ただし、辺境の地で頑張る覚悟が必要です。さらにマイノリティーである山越族をどのように懐柔し、どのように倒していくのかという問題は避けて通れません。バランスを間違えると山越族に主導権を握られる可能性もあります。山岳地帯だけでなく、船上の生活にも慣れる必要があります。アウトドア派で、野外の生活もへっちゃらならば問題ないのですが、そうでなければ苦痛の日々が待っています。
まとめ・結局は誰がいいのか
■ まとめ・結局は誰がいいのか
まとめ・結局は誰がいいのか
相対的に比較すると、やはり曹操に仕えるのがもっともリスクが少なく、正当な評価をしてもらえる可能性が高いです。曹操に仕えるのが得策だと考えます。ただし、その分だけ能力の高い人たちが集まっており、活躍するためには自己研鑽する努力が絶えず必要でしょう。
紹介した中で一番避けたいのは董卓ですね。暴力が支配する勢力で、犯罪者の仲間入りをする可能性がかなり高いです。魅力はまったく感じないのですが、一方で、短期間での勢力拡大の振れ幅がもっとも大きいのは事実です。リスキーですが、一攫千金を夢見る人にとってはそれを体験することができます。
やはりどこで働くにも一長一短がありますね。
その人が「どんな人生に価値を見い出しているのか」、それによって誰に仕えるのが得策なのかは決まってくるのではないでしょうか。