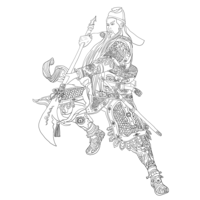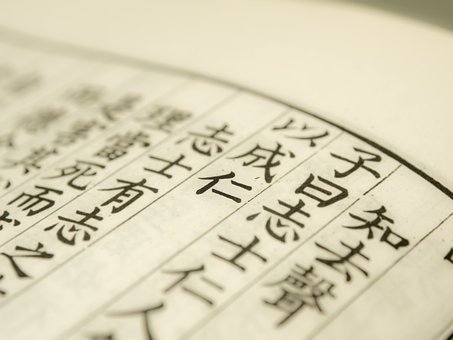大将軍・何進
■ 大将軍・何進
大将軍・何進
後漢末期に肉屋の身分から一躍出世を遂げて、大将軍にまで登り詰めた人物がいます。「何進」、字は遂高です。
何進が特別何かの能力に長けていたというわけではありません。宮中に入った妹が霊帝の寵愛を受けて皇后となったことによる異例の出世です。弟の何苗は車騎将軍となっています。軍の指揮権を握っていたのが何兄弟でした。
しかし対立する勢力もいました。霊帝に直接仕える「宦官」たちです。特に力を持っている「十常侍」を何進らは警戒していました。次期皇帝には何進の妹が生んだ弁皇子(劉弁)が即位する予定でしたから、何進が「外戚」としてさらに権力を強めるためには宦官を抑える必要があります。つまり宦官たちを朝廷から追い出し、後宮に戻さねばならなかったのです。
司徒・袁隗
■ 司徒・袁隗
司徒・袁隗
三公の一つである司徒は、天子を補佐し政治全般を取り仕切る要職です。後漢末期にこの司徒の位に二度就いた人物がいます。「袁隗」、字は字陽です。
四世三公を輩出した名門「袁家」の一人になります。袁隗は大将軍の何進から、いかにして宦官たちを政治から遠ざけるかを相談され、各地の有能な若者を朝廷に出仕させることを提案しました。何進はその案を承諾します。
ちなみに後日、何進も何苗も宦官との政争劇で命を落とすことになりますが、袁隗は生き残り、次期皇帝の少帝(劉弁)の太傅となっています。しかし朝廷を力で牛耳った董卓に睨まれて処刑されてしまいます。
威風堂々・袁紹
■ 威風堂々・袁紹
威風堂々・袁紹
大将軍の何進と司徒である袁隗に招聘されたメンバーの筆頭が「袁紹」、字は本初です。
袁紹は袁隗の甥ですから、出自はやはり名門「袁家」になります。誰が見ても一目で大物であると感じる堂々たる風貌だったそうです。実はこのときすでに十常侍の一人である趙忠に目をつけられていました。要注意人物として警戒されていたということです。
実際に袁紹を見た何進は気に入り、大将軍の副官(掾)に任命しています。その後、霊帝直属の近衛兵団・西園八校尉に抜擢されました。
何進が宦官によって暗殺された際には仲間たちと共に宮中に押し込み、次々と宦官を虐殺していきます。しかし弁皇子を董卓に押さえられてしまい、袁紹は都を脱出して反董卓連合を結成し、盟主となるのです。これに怒った董卓は洛陽に残る袁紹の叔父・袁隗を処刑しました。
三国志を代表する有力な群雄の一人に数えられ、河北を制し巨大な勢力となりましたが、曹操に敗れて衰退していきました。
孔子の末裔・孔融
■ 孔子の末裔・孔融
孔子の末裔・孔融
袁紹と同じくその活躍を期待され招聘されたのが、孔子の子孫で二十代目にあたる「孔融」、字は文挙です。
頭の回転も速く、幼いころから神童と呼ばれていました。孔子の説いた儒教は漢民族の価値観の柱となっており、論語は教科書のようなものです。そのレジェンドの末裔ですから世間からの注目は絶大で、孔融自身も高いプライドを持って出仕しています。
何進は郡の太守と同格である都尉に任じる予定でしたが、孔融は当然のように都尉よりも格上となる校尉または中郎将の官位を希望しました。中郎将とは将軍に次ぐ地位です。何進はその威に押し切られて虎賁中郎将に抜擢しています。
武官として用いられた理由は、孔融に武勇があったわけでも兵法に通じていたわけでもなく、文官として起用すると司徒も司空も孔融に敵わぬと考え、司徒府に出仕させることを袁隗が敬遠したと伝わっています。
その後、青州北海国の相に任じられ、赴任しています。董卓の死後は青州刺史も兼任しました。しかし袁紹の息子である袁譚に青州を奪われてしまいます。このとき、献帝は曹操に保護され許都に遷都しておい、孔融は少府卿として朝廷に出仕することになります。
権力を握った曹操とは折り合いがよくなく、最終的には曹操の逆鱗に触れ処刑されてしまいます。
潁川郡の名士・荀攸
■ 潁川郡の名士・荀攸
潁川郡の名士・荀攸
袁紹や孔融と同じく招聘されたのが潁川郡の名士「荀家」の一人である「荀攸」、字は公達です。
曹操の右腕となる荀彧の甥なのですが、荀彧よりも6歳ほど年上になります。何進に招かれて皇帝の側近に職にあたる侍中府の侍郎に就任しました。官位としては郡の太守と同格です。
何進亡き後も朝廷に残り、暴虐を尽くす董卓暗殺を謀りましたが失敗し、投獄されています。処刑されずに済んだのは、その前に董卓がクーデターによって殺されたからです。
孔融同様、献帝が許都に遷都した際に招聘されて、汝南郡太守に任命されています。さらに曹操からの信頼が厚いため、軍師祭酒として参謀たちのリーダー格となりました。
袁紹との戦いでは囮を巧みに利用する作戦を提案し、猛将である顔良・文醜を倒す功績をあげています。
見た目は荀彧のように凛々しいわけではありませんでしたが、内に秘めた勇気と知略は曹操が一番認めており、曹操は後継者である曹丕に対し、荀攸を手本とするようにとアドバイスしたと伝わっています。
曹操は対象外
■ 曹操は対象外
曹操は対象外
ちなみに「治世の能臣、乱世の奸雄」と評された「曹操」、字は孟徳も同時期に朝廷に出仕し、洛陽北部尉に任じられていますが、これは何進や袁隗の招聘ではないようです。曹操の祖父の曹騰が何進の警戒する宦官だったわけですから当然な話です。
しかし、曹操は何進らに期待されて出仕した袁紹を後々に倒し、孔融を処刑し、荀攸を家臣に迎えるわけですから、世の中どう転ぶかわからないものです。大穴の曹操が一番手に躍り出るあたりが三国志の面白さの一つかもしれませんね。
曹操の後継者である曹丕が献帝から禅譲を受けて魏の皇帝に即位し、こうして後漢王朝は滅びました。
まとめ・何進と袁隗の選択は間違っていなかった
■ まとめ・何進と袁隗の選択は間違っていなかった
まとめ・何進と袁隗の選択は間違っていなかった
メンバーとしては他にも平原郡の陶丘洪や陳留郡の辺讓などがいたそうです。二十人ほどを招聘したようですが、袁紹、孔融、荀攸はその後も活躍し続けていますから、その選択はなかなか的を得ていたのではないでしょうか。
何進が暗殺されずに宦官を一掃し、少帝のもと、袁隗、袁紹、孔融、荀攸らが盛り上げていたら後漢の寿命ももっと延びたかもしれませんね。
そうなると曹操は「治世の能臣」として生涯を終えていたのではないでしょうか。それはそれで少し寂しい気もしますね。「三国志」もきっと成立していなかったことでしょう。