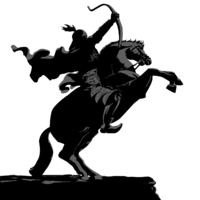曹操が加担した馬騰と韓遂の争い
■ 曹操が加担した馬騰と韓遂の争い
曹操が加担した馬騰と韓遂の争い
馬超(孟起)の父である馬騰(寿成)は家柄こそ由緒あるものの、常に貧しく幼いころから働いて生計を立てていました。成人するころには体格にも恵まれ、涼州の軍に配属されると頭角を現していきます。当時の涼州は反乱が勃発し、羌族などの周辺民族だけでなく、韓遂などの豪族たちも漢王朝に反旗を翻していました。
馬騰は最初に官軍として反乱軍へ対処していましたが、上司が部下に殺されると、逆に反乱軍に加わっていきます。元々少年の頃から苦労してきた馬騰ですので、失うものは無く、思い切った行動が可能だったのでしょうね。馬騰と韓遂はその後、都を牛耳っていた董卓に仕え、両者とも将軍に任じられています。董卓が死ぬと、都は混乱状態に陥り、馬騰も軍が壊滅状態に陥る事態となり涼州へ引き上げました。最初は同盟関係にあった韓遂と馬騰でしたが、次第に疎遠になり、仲たがいをするようになってしまいます。
中央では曹操(孟徳)が袁紹(本初)との対決が迫り、中原の状況は緊迫していました。曹操は涼州の事案を心配し、韓遂と馬騰の仲介に入るべく文官の鍾ヨウ(元常)を派遣して両者を和睦させています。その後、馬騰は曹操によって招聘され、都に住むようになります。馬騰の軍は子の馬超(孟起)が引き継ぐことになりました。
曹操からすれば、袁紹戦に全精力をつぎ込みたいところへ、西方からの憂いを無くしておきたかったことが挙げられます。この曹操の全体を見る視野の広さはさすがというべきですね。
馬超の反乱
■ 馬超の反乱
馬超の反乱
211年には曹操(孟徳)が漢中を支配している張魯討伐へ向けて、鍾ヨウと夏侯淵(妙才)を出陣させました。涼州へ向けた軍ではなかったのですが、馬超と韓遂は狡猾な曹操のことなので、自分たちの領土にまで攻めこんでくると思い、父の遺恨は忘れて共に挙兵しています。
馬超の祖母は羌族出身であり、馬騰の影響力もあって馬超・韓遂軍に羌族が味方をする形になりました。対する曹操は古参の曹仁を潼関で守備に就かせています。一進一退の攻防となった形ですが、馬超・韓遂軍は歴戦の勇士である曹操軍に引けを取らない戦いを演じました。
猛将・馬超の活躍
■ 猛将・馬超の活躍
猛将・馬超の活躍
211年には、曹操自らが布陣し、馬超軍と対峙しています。まずは徐晃(公明)と朱霊(文博)が別働隊の兵4000を率いて陣を設営すると、馬超軍からは梁興が兵5000を率いて迎撃します。しかし、歴戦の勇である徐晃と朱霊の前に梁興は成す術もなく撃破されました。この隙をついて曹操は黄河の北へ渡り、迂回策をとって南下するように考えます。曹操軍が黄河を北に渡る頃、馬超は満を持して追撃を開始し、執拗に攻撃をしかけていきます。馬超は先陣を切って曹操を追い詰め、逃げながら戦うことは極めて難しいことから曹操軍からは馬超の進軍を止めようと数々の将兵が立ちふさがりますが、馬超の槍は行く手を塞ぐことを許さず、曹操軍は大混乱に陥ってしまいます。
曹操は許チョや張コウに守られながら、かろうじて対岸へ逃げることができました。寸前のところで曹操を取り逃がした馬超でしたが、曹操が迂回してくるルートは地質も悪く、簡単に陣を築くことはできないだろうと考え、防御力のない内に叩いておこうとします。一方、散々な目に遭った曹操は、馬超の攻撃力がこれほどまでとは思いもよらなかったとし、早く防御力の高い陣地を築く必要があると考えます。
陣地を築いた曹操が有利に
■ 陣地を築いた曹操が有利に
陣地を築いた曹操が有利に
地質が悪いところへ陣地を築くのは難しく、また馬超軍の追撃もあったことから、なかなか上手く進みませんでした。長期戦となると、遠征軍の曹操陣営は不利になります。曹操は部隊を複数に分けて陣地を築く隊と伏兵を忍ばせておき、攻めてきた馬超軍と戦闘状態にわざとなることで馬超の目を引きつけつつ、別の場所で密かに陣地を築いていました。短期間で固い守りの陣地が出来上がったことに驚いた馬超は、奪取するべく攻撃をしかけますが、曹操は前もってこの陣地周辺にも伏兵を忍ばせておいたので、奇襲を受けた馬超軍は退却しています。
なお、この陣地を築くシーンでは、三国志の魏書や演義に出てくる逸話があります。高い防御力を持った陣をどうやって築くか困り果てた曹操に、ある武将がこの時期は寒いので、柱で骨組みだけをしておき、あとは水をかけておけば氷の要塞ができると進言します。曹操は言われた通りに水をかけて氷の城壁を作って馬超を驚かせたとあります。
演義ではこの武将が仙人のような存在になり、馬超の猛攻を受けて困っていた曹操がたまたま訪れた仙人に礼儀を尽くして智恵を借りたいと所望し、この恩を受けた仙人が氷の城を作るように助言したとあります。しかし、この戦いの時期は7月から9月という設定で、さすがに氷の城壁は作れないだろうというのが通例になっています。
曹操が優勢になる
■ 曹操が優勢になる
曹操が優勢になる
戦闘状態も膠着し始めると、和議を条件として馬超(孟起)・韓遂と曹操(孟徳)の三者は馬上で会談を設けます。馬超は自分の武力を活かして曹操を捕えようと考えます。しかし、護衛に付いていた許チョが常に警戒していたので、馬超は曹操の捕縛を諦めざるを得ませんでした。
この馬超と許チョのエピソードで有名なのは三国志演義にあり、戦いを優位に進めたい馬超が一騎打ちを仕掛け、許チョがこれに応じて両者全くの五分で死闘を演じ、途中で水を飲み、馬を変え、動きにくかった許チョは鎧を外して上半身裸になってまで戦い続けています。結局両者互角のまま一騎打ちは引き分けます。
ここで参謀の賈クが離間の計を授けており、馬超と韓遂は互いを疑うようになっていきます。この内容には諸説がありますが、恐らく会談前には手紙などで韓遂に仕掛けていたと思われます。そして、会談中に曹操から疑わしき発言を韓遂に差し向けることで、馬超の疑心を煽っていたと考えられます。演義では、疑いの晴れない馬超が韓遂の腕を切り落とすシーンが演じられており、両者が手を組まなくなることで曹操軍が両軍を挟み撃ちにして大勝することにつながっていきます。
敗北後の馬超
■ 敗北後の馬超
敗北後の馬超
惨敗した馬超は、そのまま落ち着くかと見られましたが、この反乱を受けて都にいた馬超の父馬騰や兄弟たちが、一連処刑されてしまいます。怒り狂った馬超は再度反乱を起し、猛将の名のまま漢中で大暴れを演じています。しかし、曹操に味方する周辺部族の反抗や涼州司令官の夏侯淵の巻き返しもあって次第に劣勢になっていき、漢中の支配者だった張魯を頼りますが、最終的には蜀へと進んできた劉備(玄徳)の傘下に入ることになります。
一時は曹操を追い詰めた馬超だけに、無念は大きかったことでしょう。劉備(玄徳)陣営に入ってからは劉璋が降伏するなど影響力の大きさも物語っていますが、戦闘では大きな活躍もできないまま47歳の若さでこの世を去っています。