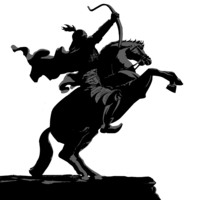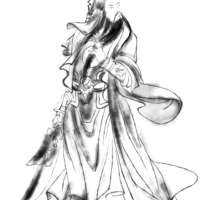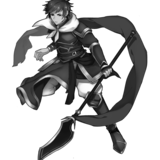同姓同名の武将
■ 同姓同名の武将
同姓同名の武将
三国志を読んでいると同じ姓で、同じ名の武将が登場してくることがあります。例えば張温です。登場する場面はまったく異なりますが、二人います。一方は張温、字は伯慎。後漢において司空や太尉を務め、車騎将軍として涼州の反乱を鎮圧すべく出陣しています。配下には陶謙や孫堅などがいました。もう一方の張温は、字は恵恕。呉の孫権の家臣です。とても才知に長けた人物として張昭から特に期待を受け、太子である孫登の教育係として太子太傅に任命されています。さらに蜀への使者を務め、その人格に驚いた諸葛亮は称賛しています。このように張温はどちらも優れていた人物といえます。
他にも劉岱は二人いたのではないかともいわれています。兗州の刺史として黄巾に殺された名士・劉岱と、徐州で反乱を起こした劉備(玄徳)に捕らえられて曹操に送り返された劉岱です。字まで同一だったのではないかという説があります。三国志演義では完全に混同されており、同一人物として描かれています。
このように稀に同じ姓と同じ名の人物はいるのです。今回はその中でもなかなか紛らわしい呉の馬忠と蜀の馬忠をご紹介します。こちらはかなり似たような時期に登場してきますので、読者も混乱しやすくなっています。
蜀の馬忠
■ 蜀の馬忠
蜀の馬忠
馬忠、字は徳信です。益州巴西郡の生まれで、もともとは狐篤でいう名前でしたが、改名して馬忠と名乗っています。登場するのは222年の夷陵の戦いの後のことです。このとき劉備(玄徳)は孫権配下の陸遜に大敗を喫していました。馬忠は敗北後の劉備(玄徳)の援軍として兵五千を率いて、永安に駐留しました。劉備(玄徳)の評価は高く、夷陵の戦いで黄権が魏に投降していましたが、その代わりに馬忠を得たと喜んだといいます。
馬忠がその真価を発揮したのは南蛮制圧とその治政でしょう。寛大であり、また公正な人柄で、統治している住民からとても慕われていたそうです。戦場でも武功をあげ、羌や反乱を起こした異民族を征討しています。怒りを面に出さず、決断力に長けていたともいいます。そのために劉備(玄徳)亡き後にも諸葛亮に重用されることになりました。諸葛亮が亡くなった後も鎮南大将軍として引き続き蜀を支えています。馬忠が亡くなったときには、その恩恵を受けていた住民たちは泣いて悲しんだそうです。
蜀の馬忠(三国志演義)
■ 蜀の馬忠(三国志演義)
蜀の馬忠(三国志演義)
三国志正史では高い評価を受けている馬忠ですが、三国志演義ではやや扱われ方が異なるようです。やはり南蛮制圧戦に登場していますが、孟獲の妻である祝融と一騎打ちを繰り広げ、敗北し捕らえられているのです。三国志正史では馬忠の配下として登場する張嶷もまた、祝融に一騎打ちで敗れて捕らえられています。なぜこのような役回りになったのでしょうか。困った諸葛亮は計略をもって祝融を捕らえ、人質交換をして馬忠を救い出しました。あまりいいところがないですね。
しかし、諸葛亮に従い北伐に出陣した際には魏の名将を倒す働きをしています。諸葛亮の策にかかり魏延を追撃してきた魏の張郃です。馬忠は伏兵を用いて張郃を襲撃し、射殺しています。張郃といえば魏の五大将軍のひとりに数えられるほどの名将ですから、この活躍は特筆すべきものですね。ちなみに三国志正史でも張郃は諸葛亮を追撃して木門という場所で蜀軍の矢に当たり没しています。
呉の馬忠
■ 呉の馬忠
呉の馬忠
こちらの呉の馬忠は、字が伝わっていません。出身なども不明です。謎の人物といってもいいでしょう。そのため、現代ではたくさんの三国志作品がありますが、この馬忠をあたかも化け物の如く扱っているものもあります。ほとんどの詳細が不明であるにもかかわらず、なぜ呉の馬忠が有名なのかというと、あの関羽を捕らえた人物だからです。劉備(玄徳)の義弟の関羽は、後に神として崇められるほどの英雄であり、一騎当千の猛将ですから、それを生きたまま捕縛したということはかなり大きな武功をあげたことになります。呉の潘璋の家臣ですが、はたして将として兵を率いていたのか、潘璋の警護役のような役割だったのかも謎です。
三国志演義でもやはり関羽を捕らえたのは馬忠となっています。しかも夷陵の戦いでは関羽と同じ五虎大将のひとりである黄忠を迎撃して倒しているのです。追われている潘璋を救出し、返り討ちにしたわけです。こうして見ると、呉の馬忠はかなりの武勇を誇っていたことになりますね。
三国志正史では関羽や関平を捕縛したことしか記されていませんが、三国志演義では黄忠を倒した後、蜀を裏切って呉に投降してきた麋芳と士仁に暗殺されています。麋芳と士仁は再び蜀に寝返るために馬忠の首を手土産にしたのです。しかし劉備(玄徳)はこれを許さず、麋芳と士仁を処刑しています。ちなみに馬忠は関羽を捕らえた褒美として、孫権から赤兎馬を授かっていますが、赤兎馬は何も食べようとせずに亡くなったとされています。
まとめ・蜀の馬忠と呉の馬忠
■ まとめ・蜀の馬忠と呉の馬忠
まとめ・蜀の馬忠と呉の馬忠
同じ馬忠でも、多くの記録が残されているのが蜀の馬忠になります。逆に呉の馬忠はそのほとんどが闇の中です。どのような人物だったのかさっぱり見当もつきません。とても対称的な二人ですね。しかしその功績はどちらも大きいものがあります。三国志演義を参考にすると、蜀の馬忠は魏の名将・張郃を討っていますし、呉の馬忠もまた蜀の関羽・黄忠を倒しているのです。これを比べると、戦場での活躍ぶりとしては、呉の馬忠の方が上のようですね。統治力や人徳に関しては蜀の馬忠の方が上なのではないでしょうか。
私としては呉の馬忠がこれほどの功績をあげながら謎のベールに包まれていることが気になります。そこには何かしらの理由があったのでしょう。しかもあの関羽がそう簡単に捕縛されるとは思えません。いったいどのような手段を用いたのでしょうか。ひょっとすると三国志で最も強い武将は呉の馬忠だったかもしれませんね。潘璋の部隊は数千人規模でしたが精強で、一万の軍勢に匹敵する活躍を常にしていたと記されています。そこには馬忠の圧倒的な武勇が存在していたのかもしれません。
なかなか甲乙つけがたい二人の馬忠。三国志にまた異色の個性を加えてくれていることに間違いはありません。