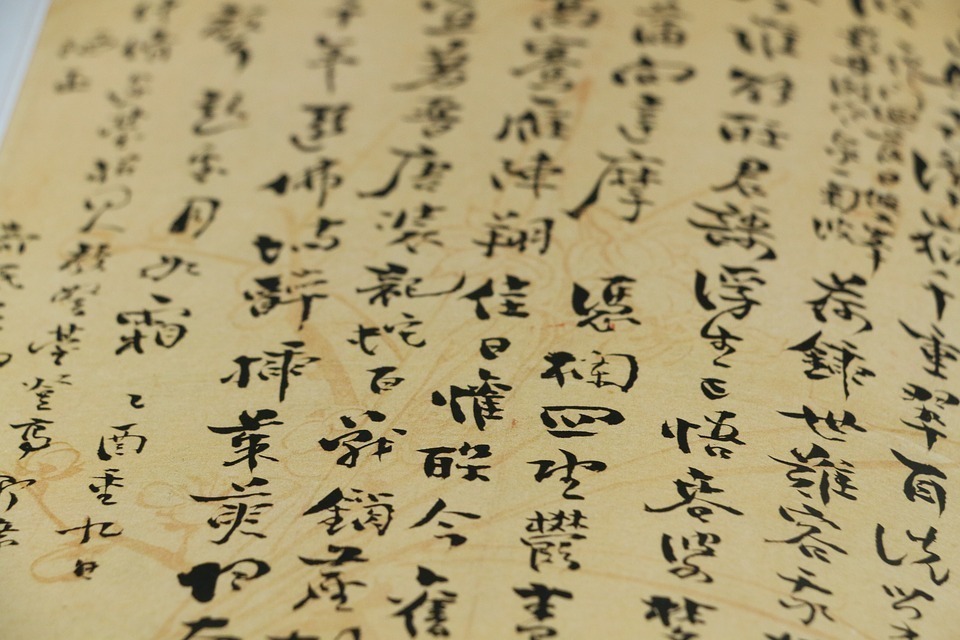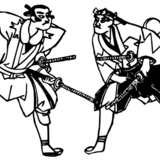夏侯淵(かこうえん)と曹操の関係
■ 夏侯淵(かこうえん)と曹操の関係
夏侯淵(かこうえん)と曹操の関係
夏侯淵(かこうえん)、字は妙才。豫州の生まれです。曹操の親族で、旗上げ当初から曹操に仕えています。同じく古参の将である夏候惇がいますが、こちらは夏侯淵の従兄にあたります。三国志演義では夏候惇の弟として紹介されています。曹操が兗州の牧となると、陳留郡の太守に任命されています。武勇が優れていただけではなく、統率力も曹操に認めらえていたということでしょう。曹操の妻の妹を正妻に迎えており、曹操と夏侯淵の関係は兄弟同然に深かったものだと推測されます。
夏侯淵(かこうえん)の将としての評価
■ 夏侯淵(かこうえん)の将としての評価
夏侯淵(かこうえん)の将としての評価
三国志演義では弓術に長けた武将として登場しています。三国志正史では「白地将軍」と呼ばれており、機動力を活かした部隊の移動や奇襲攻撃は得意でしたが、戦場での駆け引きは苦手だったと記されています。機動力に関しては「3日で五百里、6日で千里」を行軍したそうです。一里がどれほどの距離なのか定かではありませんが、およそ400mほどだと考えられていますから、五百里だと200kmという計算になります。ちょうど洛陽から許昌ぐらいの距離ですね。ちなみに日本の戦国時代、豊臣秀吉が本能寺の変の後に「中国大返し」を行っていますが、この備中高松城から山城山崎までの距離が200kmです。この時は約10日かかっています。平地や山岳地帯、歩兵や騎兵などの条件の違いはあるものの、200kmを3日で踏破する夏侯淵の進軍は凄まじいスピードです。
独立勢力討伐戦
■ 独立勢力討伐戦
独立勢力討伐戦
夏侯淵は辺境で独立する勢力を討伐して活躍します。様々な名将と組んで成果を出せる柔軟性があるのも夏侯淵の特徴でしょう。徐州青海で曹操に何度も逆らった昌豨の討伐には張遼を率いています。昌豨の最期の反乱の際には援軍として討伐に向い、10を超える陣営を陥落させました。これを知った昌豨は親交のある于禁に降伏しましたが処刑されています。青州の済南、楽安で反乱を起こした黄巾の残党・徐和と司馬倶に向けては、臧覇と呂虔を率いて平定しています。さらに揚州の盧江で反旗を翻した雷緒を降し、幷州の太原の賊徒の群れに対しては、徐晃を率いてその首領を討ち取りました。このとき夏侯淵は20の陣営を陥落させたと記されています。勢いに乗せると誰も手が付けられなくなるのが夏侯淵の真骨頂ですね。
涼州討伐戦
■ 涼州討伐戦
涼州討伐戦
辺境での最大規模の反乱といえば、韓遂・馬超らが関中軍閥を率いて潼関に攻め寄せたものでしょう。涼州、雍州一帯を巻き込んだ大きな戦いになっています。夏侯淵は、このとき朱霊や張郃を率いて討伐に参加し、活躍します。馬超を駆逐し、韓遂を倒した後は、さらに異民族である羌や氐を降しています。こうして215年、漢中の張魯を降した曹操は、夏侯淵を征西将軍に任じて漢中を任せることになるのです。西方面の総司令官ですね。このころ漢中の南の益州は劉備(玄徳)の征服されていました。劉備(玄徳)もまた益州への入り口ともいえる漢中の制圧を目指していたのです。
漢中争奪戦
■ 漢中争奪戦
漢中争奪戦
漢中を制圧した曹操は住民を北に移住させる政策をとります。さらに名将・張郃を南下させ巴西を攻め、そこの住民も移住させています。戦乱が続いたこの時代において、多くの田畑は荒廃して農民は逃散しています。生産性を高めるためにも人口は重要な要素を占めていました。張既は漢中の住民数万を長安方面に移住させることに成功します。その後は杜襲が八万人にも及ぶ住民を洛陽と鄴へ移住させているのです。もはや漢中は空っぽの状態です。司馬懿は曹操に対し益州を手に入れるべきと進言していますが、荊州を手に入れた後に勢いだけで孫権を攻めて大敗していることと、その孫権と合肥の戦線で激戦を繰り返していること、漢中の住民を手に入れたことにより、曹操は夏侯淵らを残して撤退します。
巴西を攻めた張郃は、張飛と対峙することになります。張飛は間道をうまく利用し、張郃を撃退します。そしてなんとここから約4年に渡り漢中を巡る攻防戦が続くことになるのです。曹操側の主力は夏侯淵を総大将に、張郃や徐晃。劉備(玄徳)側は荊州を守る関羽以外の総力戦です。劉備(玄徳)側が少しずつ押し始めます。これには西の合肥の戦線が大きな影響を及ぼしていました。曹操は合肥での孫権との戦いに戦力を割き、漢中へのフォローが後回しになっていたのです。
定軍山の戦い
■ 定軍山の戦い
定軍山の戦い
217年3月に合肥で曹操と戦っていた孫権が、曹操が魏王となった機会に突如和睦します。曹操軍はこの機会に北の異民族である烏丸の反乱を平定し、鮮卑も降伏させました。そして218年9月には曹操直々に長安に進出し劉備(玄徳)との決戦に備えることになるのです。
その間に劉備(玄徳)は漢中を攻め、張飛や馬超が武都を攻めます。張飛らは、曹洪らに呉蘭と雷銅を斬られて退却。代わりに劉備(玄徳)は陽平関を奪取します。さらに219年1月、劉備(玄徳)は法正を軍師とし、本陣を定軍山に進めます。漢中を守る総大将・夏侯淵はこの迎撃のために出陣しました。法正はまずは張郃の陣の攻略に戦力を集中します。劣勢になった張郃の援軍のために夏侯淵は兵の半数を割きます。ここで法正の指示に従う黄忠が、夏侯淵の本陣から南に十五里離れた陣を焼き払います。夏侯淵はさらに兵を割き、わずか400の兵で陣の修復に向かいました。その隙に黄忠は襲撃のために険しい山を駆け上り、夏侯淵の本陣の背後を奇襲攻撃。まともに黄忠の逆落としをくらった夏侯淵は討ち取られることになるのです。夏侯淵の長所である即断即決が今回は仇となりました。軍師・法正は見事に夏侯淵を翻弄したといえます。
まとめ 夏侯淵(かこうえん)の死後
■ まとめ 夏侯淵(かこうえん)の死後
まとめ 夏侯淵(かこうえん)の死後
曹操が、奪われた漢中と対峙したのは219年3月のことになります。曹操は夏侯淵の死を嘆き、数ヶ月に渡って劉備(玄徳)と攻防戦を行いましたが、無理に攻めると損害が大きいと判断し、撤退を決断しました。これにより7月には劉備(玄徳)が曹操の魏王に対抗して漢中王を自称しています。黄忠はこの武功が高く評価され、征西将軍・後将軍に昇進しました。五虎大将軍の仲間入りですね。夏侯淵の遺体は張飛が引き取り埋葬したともいわれています。理由は張飛が夏侯淵の血族にあたる女性を妻に迎えていたからです。この夫人は夏侯月姫とも呼ばれています。やがてそのつてを辿り、夏侯淵の息子である夏侯覇が蜀に亡命してくることになるのです。