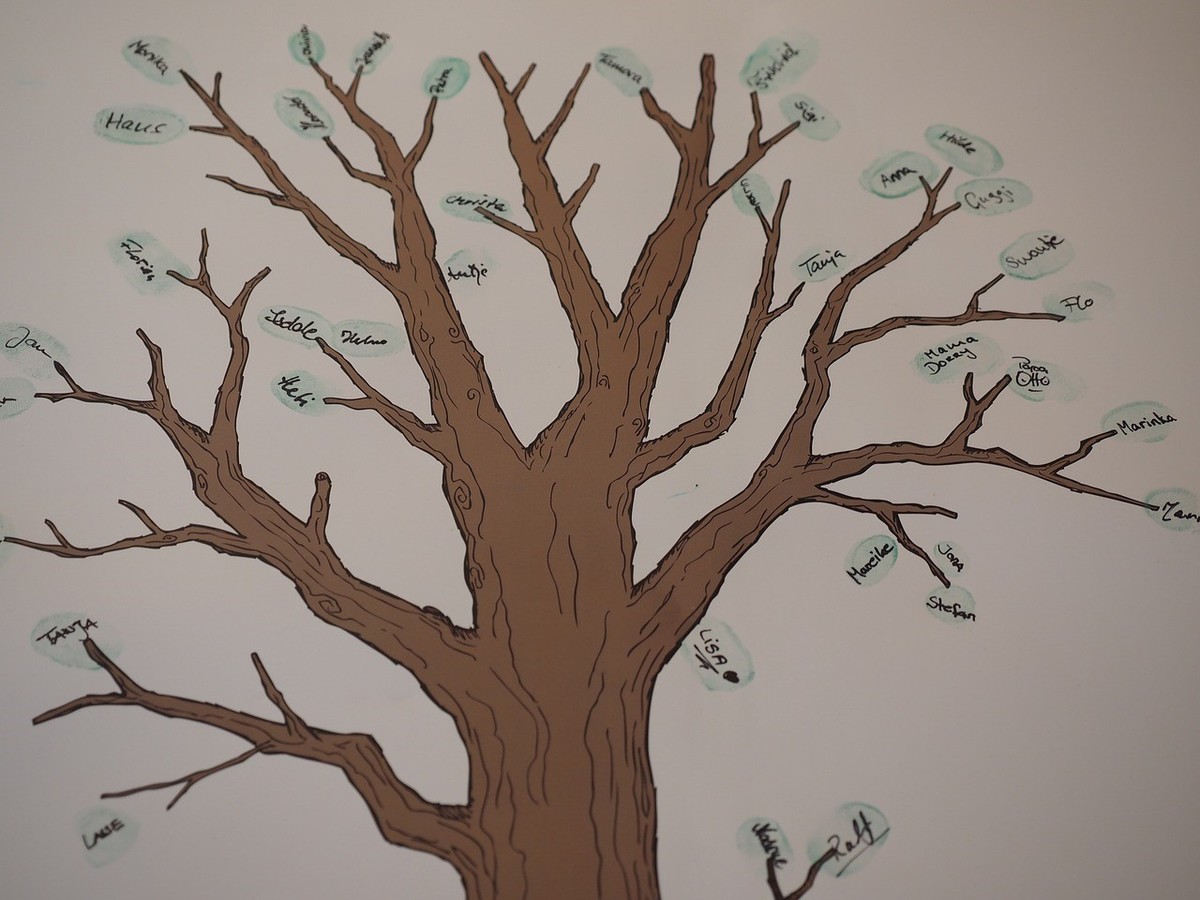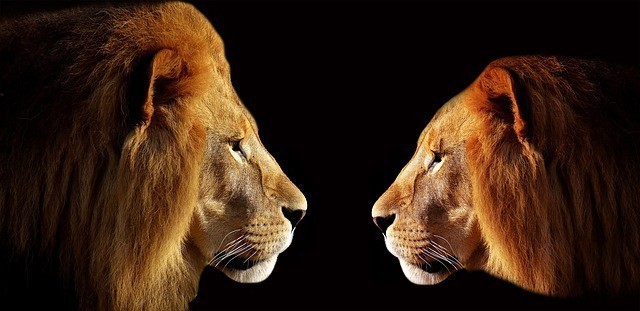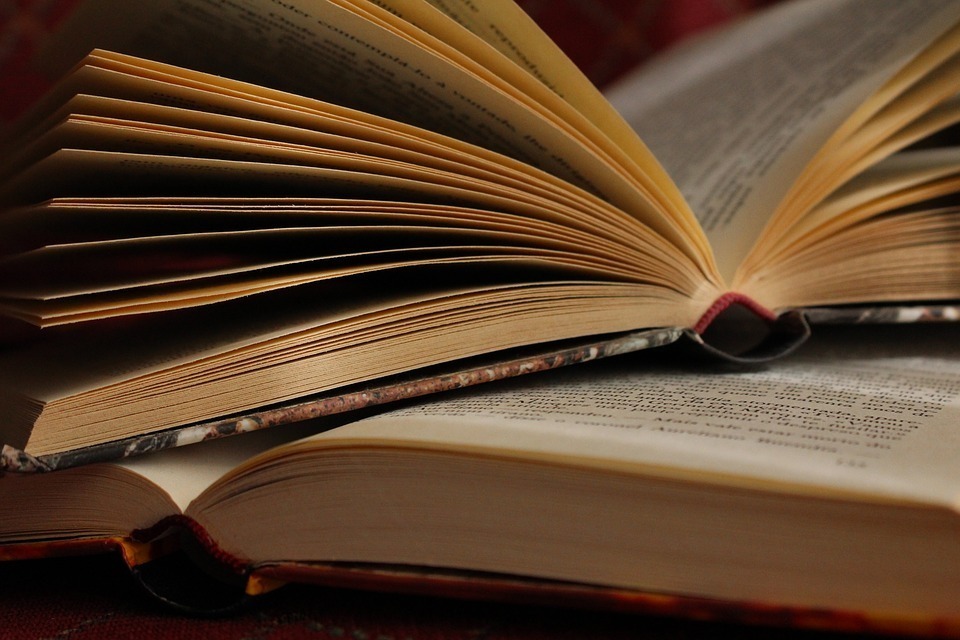夏侯惇と夏侯淵は曹操の親族
■ 夏侯惇と夏侯淵は曹操の親族
夏侯惇と夏侯淵は曹操の親族
曹操の父である曹嵩が夏侯氏の出で、宦官である曹騰の養子になっているので、曹操と夏候惇や夏侯淵は従弟という親族関係になります。
曹操の挙兵当初から将として活躍しており、夏候惇は後に魏の「大将軍」として軍部のトップまで昇進していますし、夏侯淵も漢中において「征西将軍」として、張郃や徐晃などの勇将を率いて、劉備(玄徳)の軍勢と戦いました。
夏侯惇と夏侯淵は、共に曹操軍の太い柱のような存在だったのです。曹操は親族ということ以上にその高い能力を評価して、絶大な信頼を二人に寄せていたようです。
しかし、「三国志演義」中心に三国志を読んでいると、そこまで活躍したシーンがこの二人にはありません。一軍の将として多くの戦場を渡り歩き、多くの武功をあげているのですが、三国志演義にはほとんど取り上げられていないのです。
三国志演義では、夏候惇と夏侯淵はどのような戦いぶりをしているのでしょうか?
夏侯惇の一騎打ち(前半)
■ 夏侯惇の一騎打ち(前半)
夏侯惇の一騎打ち(前半)
夏侯惇、字は元讓、豫州沛国の出身です。子供の頃には学問の師を侮辱した相手を殺害、気性の荒さを物語っています。その勇猛果敢ぶりは曹操配下になっても変わっていません。呂布に兗州を奪われた際には留守役をしており、兗州の各地が呂布に帰順する中で、荀彧と共に最後まで抵抗しました。一時は呂布軍に捕らわれることにもなったようです。
そんな夏候惇の三国志演義における一騎打ちの経歴ですが、最初は第6回になります。反董卓連合として董卓軍と戦った際です。曹操軍は徐栄の伏兵に破れ、曹操は命からがら退却するのですが、この時に、夏候惇は敵の大将・徐栄と対戦。数合打ち合った後に見事、徐栄を討ち取っています。
その後、第10回では徐州の曹豹と対戦。こちらは一合打ち合っただけで、突然の突風が起こり、引き分けで終了しています。続く第11回でも、張遼と対戦。こちらも決着がつかず、引き分けでした。
第12回では呂布とも対戦していますが、夏侯淵や典韋、許褚などの複数で仕掛けて、呂布を退かせています。一騎打ちとは言いにくいものの、夏候惇の勝利です。
さらに第18回で、呂布の重臣である高順と対戦。こちらは五十合打ち合ったところで、不利を悟った高順が退却し、夏候惇の優勢勝ち。
その後、呂布軍の曹性と対戦し、曹性の放った矢で左目を射抜かれる重傷を負いますが、夏候惇は「親に貰った大切な身体を捨てられるか」と叫んで、左目を引き抜いて自らそれを食べ、さらに曹性の額を一突きして討ち取りました。
左目を失ったことにより、夏侯惇は夏侯淵と区別するために「盲夏侯」とも呼ばれるようになっています。
夏侯惇の一騎打ち(後半)
■ 夏侯惇の一騎打ち(後半)
夏侯惇の一騎打ち(後半)
第25回では徐州の関羽と対戦。ここでは夏候惇はわざと負けたふりをして退却していますので、引き分けですね。
第28回でも、曹操の下を去った関羽を追撃し、対戦しています。十合ほど打ち合いましたが、決着はついていません。関羽とは二度対戦して二度引き分けています。
第39回では荊州を攻め、今度は劉備(玄徳)配下の勇将・趙雲と対戦。数合ほど打ち合いましたが、趙雲はわざと退却していますので、これも引き分けとなります。
夏侯惇の登場はここまでです。話はここから赤壁の戦いへと進んでいくことになりますが、夏候惇は特に活躍せず、曹操が亡くなった同じ年に体調を崩して亡くなりました。
夏侯淵が赤壁の戦い後もよく登場するのとは対称的です。
曹操は夏候惇を特別視していたようで、魏の官位には就けず、漢の官位のままにしています。これは「不臣の礼」という、家臣とは扱わないことを意味しており、曹操は夏候惇に対し、車への同乗も許可していました。
三国志演義だけでは、大軍を率いて劉備(玄徳)を攻め、諸葛亮(孔明)の策に破れるというシーンが有名なので、あまり戦上手という印象はありませんが、「三国志正史」には多くの武功が記されています。
夏侯淵の一騎打ち(前半)
■ 夏侯淵の一騎打ち(前半)
夏侯淵の一騎打ち(前半)
夏侯淵、字は妙才、豫州沛国の出身です。曹操が罪で罰せられた際には、身代わりとして出頭しています。三国志演義では夏候惇の弟という設定ですが、父親が兄弟ですので、従弟にあたります。夏候惇同様、曹操の挙兵当初から将として活躍しています。
そんな夏侯淵の一騎打ちの回数は、夏候惇よりも少な目です。
最初の対戦は夏候惇や許褚と協力しての呂布戦。多勢に無勢で呂布を退けています。
夏侯惇が赤壁の戦い前で登場がほぼ終了するのに対し、夏侯淵は前半にほとんど活躍の場がありません。
三国志正史ではその迅速な進軍は、敵の脅威になっていましたが、三国志演義で夏侯淵にスポットライトが当たるのは、馬超が西で反乱を起こして以降になります。そしてそこから先は西の総司令官として劉備(玄徳)の前に立ちはだかることになるのです。
夏侯淵の一騎打ち(後半)
■ 夏侯淵の一騎打ち(後半)
夏侯淵の一騎打ち(後半)
第58回では、夏侯淵は馬超の反乱に協力した豪族・成宜と対戦し、見事に討ち取りました。
その後の漢中の張魯攻めでは、まずは楊任と対戦。ここは十合ほど打ち合って引き分けました。さらに昌希と対戦して、三合ほど打ち合って討ち取ります。そして楊任と再戦し、数合打ち合った末に討ち取りました。
龐徳とも対戦しましたが、こちらは数合打ち合って、夏侯淵がわざと退却して龐徳を誘導しています。引き分けですね。
そして運命の第71回、定軍山の戦いでは、蜀の黄忠と対戦。初戦は二十合ほど打ち合って引き分け、二戦目は味方の援軍のために兵を割いたところを奇襲を受けることになり、黄忠によって一刀両断にされてしまいました。
黄忠はこの武功を認められて五虎大将軍のひとりに抜擢されることになるのです。
唯一の敗北によって、夏侯淵は蜀に討ち取られてしまいました。曹操は夏侯淵の軽率な行動を嘆きました。
まとめ・夏侯惇と夏侯淵で合わせて17戦8勝(勝率47.1%)
■ まとめ・夏侯惇と夏侯淵で合わせて17戦8勝(勝率47.1%)
まとめ・夏侯惇と夏侯淵で合わせて17戦8勝(勝率47.1%)
ということで、魏を代表する武将・夏侯惇と夏侯淵は、三国志演義において17回の一騎打ちを行い、8度の勝利を収めています。敗北は夏侯淵が黄忠に討ち取られる一度のみです。
勝率はそれほど高いものではありませんが、相手は関羽や趙雲、呂布や張遼などのトップクラスの武将が多いので、充分健闘していると言えるでしょう。
魏ファンとしては、もっとももっと二人の活躍したシーンが見たいところですが、蜀の活躍がメインで語られている三国志演義ですから、仕方のないところなのかもしれません。