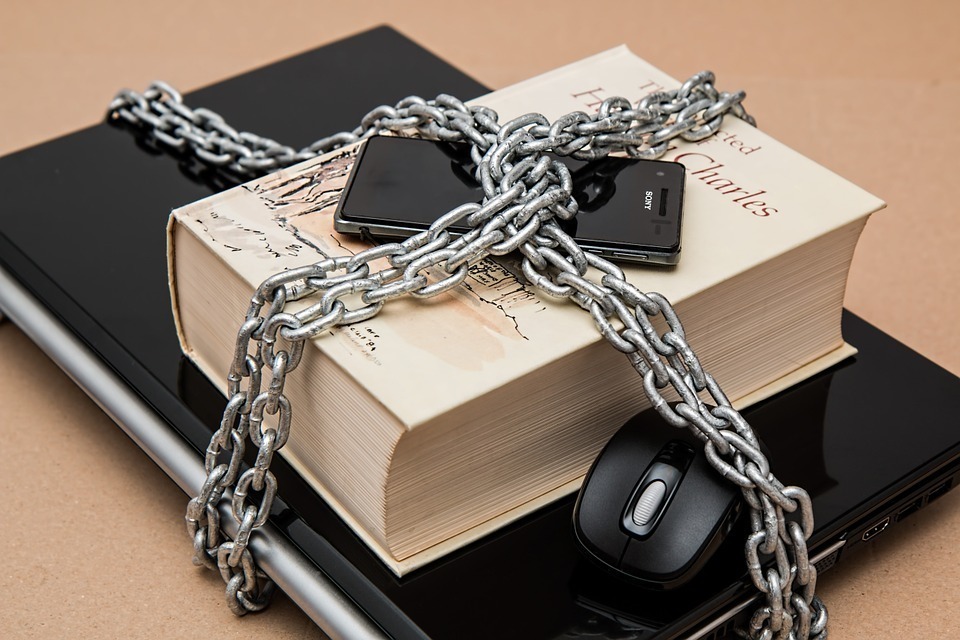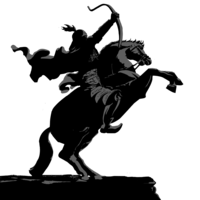当初は劉備(玄徳)にも仕えていた陳グン
■ 当初は劉備(玄徳)にも仕えていた陳グン
当初は劉備(玄徳)にも仕えていた陳グン
陳グン(チングン 生年不明―236年)は名家に生まれ、若かりし頃から優秀で、名声がありました。故郷で刺史(シシ 州の長官にあたる)を一時務めていた劉備(玄徳)(リュウビ 161年―223年)に召し抱えられています。当時(193~194年頃)は中央を圧政していた董卓が死に、曹操や袁紹(エンショウ 154年―202年)、袁術(エンジュツ 生年不明―199年)、呂布(リョフ 生年不明―198年)といった面々が力を付けて台頭していました。
劉備(玄徳)は董卓や曹操に匹敵する力を持った陶謙(トウケン)に気に入られ、彼の死の間際に徐州を譲られます。陳グンは袁術や呂布に接している徐州を今獲るべきではないと進言しますが、劉備(玄徳)には採用されませんでした。結局のところ呂布に攻められて劉備(玄徳)は徐州を手放すこととなり、陳グンの先見の明は優れたものがあったことがうかがえます。
曹操配下で実力を発揮していく
■ 曹操配下で実力を発揮していく
曹操配下で実力を発揮していく
曹操が呂布を倒すと、陳グンは曹操の配下に加わります。陳グンは名家の出身らしく礼儀を重んじ、公正公平に物事を判断していました。とりわけ曹操の若き軍師として脚光を浴びていた郭嘉(カクカ 170年―207年)に対して、その素行を悪さから何度も注意し、曹操にも郭嘉を重用しないように進言しています。郭嘉はその優れた智略で絶大に信頼されており、曹操は郭嘉を処罰することはありませんでした。一方で曹操は、自身の側近に対しても大いに意見を述べて注意する陳グンの公平さを評価しています。
法律を専門に活躍し「九品官人法」を制定
■ 法律を専門に活躍し「九品官人法」を制定
法律を専門に活躍し「九品官人法」を制定
陳グンは人を見る目が優れており、多くの優秀な人材を推挙しています。陳グンは曹操の死後に跡を継いだ曹丕(ソウヒ 187年―226年)にも信頼されており、主君が変わっても重宝されていました。
また、陳グンは法律の知識にも長けており、新しい官僚の人事制度となる九品官人法を制定し、これは300年以上にも渡り各王朝の人事登用制度として存在していました。陳グンは政権の中枢を担うまでに出世し、魏の建国後も貢献していきます。
曹氏3代に仕える
■ 曹氏3代に仕える
曹氏3代に仕える
曹丕が若くして亡くなると、司馬懿(シバイ 179年―251年)と共に皇太子の曹叡(ソウエイ)を盛り立てていきます。また、大将軍となっていた曹真(ソウシン 生年不明―231年)が蜀への遠征を計画していると、すかさず反対し、赴くにしても慎重に行動するように曹叡に進言しています。結果、この蜀への南征は大雨の影響で進軍するのもままならず、何の効果も見出すことができずにおり、諸葛亮(ショカツリョウ 181年―234年)の策略によって、魏の猛将であった張コウ(チョウコウ 生年不明―231年)が討ち取られています。
陳グンは236年に没し、子の陳泰が跡を継ぎました。魏の地盤を作った曹操の功臣20名には陳グンも含まれており、後世にいたるまでその名を残しています。
名臣である父親の跡を継いだ陳泰
■ 名臣である父親の跡を継いだ陳泰
名臣である父親の跡を継いだ陳泰
陳泰(チンタイ 生年不明―260年)の母は魏の名臣である荀彧(ジュンイク 163年―212年)の娘であり、陳泰は陳グンや荀彧といった魏の中枢を担った血を受け継いでいました。陳泰は并州(ヘイシュウ 中国北部)の刺史となって北方の異民族である匈奴(キョウド)を撃退していきました。武力のみで支配するだけでなく、人心掌握に長け、温情を以って接したために異民族からも一目置かれていました。
また、中央の実力者たちが匈奴ら異民族を奴隷として扱えるように金品を届けましたが、陳泰はこれに応じず、中央に帰還したときに金品ごと突き返したといいます。
蜀の北伐に対抗する
■ 蜀の北伐に対抗する
蜀の北伐に対抗する
蜀では諸葛亮の死後に軍権を期待されたのが姜維(キョウイ 202年―264年)です。姜維は諸葛亮を初め、魏の武将からも評価されていました。249年には姜維が魏の西部へ進撃し、異民族の羌族を味方に付けています。同年には姜維が羌族を連れて魏へ侵攻してくると、対蜀の司令官でもあった郭淮(カクワイ)は、并州から中央寄りへ赴任していた陳泰に相談を持ちかけます。
陳泰は蜀軍が通る山道は険しく、兵糧の輸送も上手くいかない、姜維が異民族を完全に手なずけていないことを指摘し、十分に勝機があることを説きます。陳泰は輸送路を絶ち、蜀軍を兵糧攻めにすることを進言しています。
魏軍は蜀軍と対峙してもむやみに仕掛けず、陳泰の作戦通りに兵糧攻めに徹し、蜀軍は退却していきました。
その後253年にも姜維が大軍をもって攻めてきますが、陳泰は落ち着いて対処し、蜀軍を撃退しています。
姜維を完全に封じ込めた軍略を見せる
■ 姜維を完全に封じ込めた軍略を見せる
姜維を完全に封じ込めた軍略を見せる
郭淮の死後、陳泰は対蜀の前線を任されていました。255年には姜維がまたも北伐を実行し、大軍をもって攻めてきます。陳泰は序盤こそ姜維に攻め込まれ、漢中へと続く城(狄道城)を攻め込まれ、一軍を壊滅させられます。配下で優秀な将軍であるトウ艾(トウガイ 生年不明―264年)は、その後方の領地を守るべく後退すべきであると進言しますが、陳泰は姜維が先勝したのを受けて、逆に虚を突いて蜀軍を攻め、一気に疲弊させるべきであると述べており、狄道城を攻撃している姜維軍を攻めるように命じます。
険しい山道であるために、姜維は万が一用の伏兵を用意していましたが、陳泰はこれを見破っていました。別ルートで姜維軍へと進むと、あまりにも速い進軍だったので、態勢が崩れた姜維軍は混乱し、姜維は退却を命じています。
出世を続けるも皇帝である曹髦の暗殺を嘆く
■ 出世を続けるも皇帝である曹髦の暗殺を嘆く
出世を続けるも皇帝である曹髦の暗殺を嘆く
蜀を抑えた陳泰は、中央に呼び戻され、以降も順調に出世を重ねていきます。256年に呉が攻めてきたときには軍を率いて守りを固めており、呉の大将軍である孫峻を退けています。司馬懿の跡を継いだ息子の司馬昭(シバショウ 211年―265年)らの専横を防ごうと、魏の第4代皇帝の曹髦(ソウモウ)はわずかな兵で挙兵します。
事前に密告を受けていた司馬昭は配下に鎮圧を命じ、曹髦はわずか19歳で殺されてしまいました。陳泰は若き皇帝が暗殺されたのを知ると、遺体に駆けつけて大泣きし、後か現れて今後のことを相談してきた司馬昭に対し、断固たる厳しい態度で対応しています。陳泰は同年に死去しており、一説にはこの時勢を憂いて自殺したともいわれています。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志の時代では、大活躍した武将の親や子どもたちは一貫して不遇の晩年を迎えているものですが、陳グン・陳泰の親子は名臣として敬われ、国の発展に大きく貢献していきました。特に大国となった魏が司馬一族に専横されていく中でも、その権力を以って誅殺されることなく、逆に輝きを増していくのは極めて珍しいものといえるでしょう。