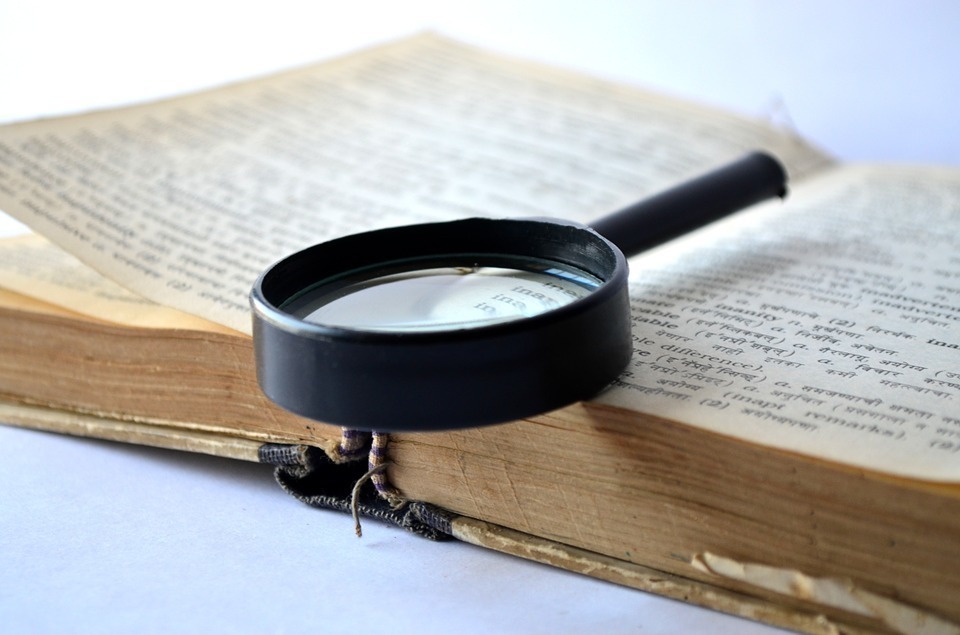三国志に登場する有名な戦い
■ 三国志に登場する有名な戦い
三国志に登場する有名な戦い
三国志では有名な戦いがいくつも登場します。袁紹の大軍を相手に、曹操が奇跡の逆転劇を演じた「官渡の戦い」。魏の重臣・夏侯淵が劉備の軍を相手に討ち死にするという「定軍山の戦い」。劉備(玄徳)の大軍を相手にして陸遜が火計で勝利した「夷陵の戦い」。魏の司馬懿と蜀の諸葛亮の対陣が百日も続いたという「五丈原の戦い」。
数多くの戦いが群雄たちの間で繰り広げられてきたわけですが、その中でも最も有名な戦いといえば208年の「赤壁の戦い」です。
曹操、劉備(玄徳)、孫権の三勢力が敵味方に分かれて戦いました。
2008年、2009年に公開された映画「レッドクリフ」はまさにこの赤壁の戦いを舞台にしています。この映画を入り口にして三国志の世界に興味を持った人も多いのではないでしょうか。
映画「レッドクリフ」と三国志演義
■ 映画「レッドクリフ」と三国志演義
映画「レッドクリフ」と三国志演義
三国志の小説、漫画、ドラマ、映画、ゲームまで含めると、膨大な種類が存在します。
それぞれにオリジナルのエピソードをあり、「三国志はこうあるべきだ」という固定観念を持ってしまうと違和感を感じたり、受け入れられなくなる作品もでてきます。
映画レッドクリフの主役は劉備(玄徳)の軍師・諸葛亮と孫権が全幅の信頼を寄せる将軍・周瑜です。ストーリーの柱が「三国志演義」だからこのような設定になっています。赤壁の戦いの見どころを、曹操VS諸葛亮VS周瑜という知恵対決という点に注目して描いているのが三国志演義の特徴です。そして私たちが知っている赤壁の戦いとはこのようなイメージでできあがっています。
三国志演義はこの赤壁の戦いを大いに盛り上げて描いているのです。
曹操側の赤壁の戦い
■ 曹操側の赤壁の戦い
曹操側の赤壁の戦い
曹操は河北を平定した後、南下して荊州の劉表を攻めます。折しも劉表は病死し、これに後継者争いが加わって荊州では曹操と戦うどころではなくなります。劉表の跡を継いだ劉琮は側近のアドバイスを聞いてすぐに曹操に降伏しました。客将として劉表のもとにいた劉備は降伏を認めず落ち延びていきます。曹操は無傷で荊州の領地と水軍を手に入れたのです。ここはついでに最大の敵対勢力である江東の孫権を滅ぼしてしまおうと決断します。
曹操は孫権に80万の大軍であることを豪語していますが、実際は北から率いてきた30万に荊州で加わった10万を合せて約40万ほどだったのではないかといわれています。
水増しして兵力を数え、敵を委縮させ、味方を鼓舞するのはいつの時代でも見られます。
孫権側の赤壁の戦い
■ 孫権側の赤壁の戦い
孫権側の赤壁の戦い
孫権は内政を充実させ、着々と領土を広げていました。隣接する仇敵である江夏の黄祖を亡ぼし、いよいよ本格的に荊州攻めというタイミングで敵が劉表から曹操に変わったのです。孫権軍は約10万です。兵力に大きな差がありましたし、曹操は戦場での経験も豊富で参謀、名将が配下に揃っています。とても勝ち目はありません。重臣の張昭が中心となって和睦すべきという意見が強まります。この場合、和睦というより降伏です。
しかし敢然と立ち向かうことを主張する主戦派もいました。それが周瑜であり、魯粛でした。曹操は水戦に慣れていないというハンデがあったのです。さらに慣れない水のため疫病がまん延していました。勝ち目がまったくないわけでもなかったわけです。
劉備(玄徳)側の赤壁の戦い
■ 劉備(玄徳)側の赤壁の戦い
劉備(玄徳)側の赤壁の戦い
劉備(玄徳)は荊州を南下して曹操の追撃から逃れます。そして江夏にいた劉表の長男・劉琦と合流して、態勢を整えます。劉琦を旗印として荊州支配の正統性を訴えたことで荊州に住む名士は曹操派と劉備派に分裂したそうです。兵力はわずか2千ほどだったともいわれています。単独での曹操への対抗は不可能であり、劉備(玄徳)は軍師である諸葛亮を孫権のもとに遣わせて同盟を結びました。
このとき、諸葛亮は孫権配下の和睦派を論破し孫権を交戦に傾けたとされています。まずここが三国志演義の脚色です。しかし孫権の決断を促すような話をしたことは正史にも書かれています。曹操が鄴の銅雀台に孫策と周瑜の妻をはべらせたいと詠っていると周瑜をたきつけるシーンもありますが、こちらもフィクションです。銅雀台自体が赤壁の戦い以降に作られています。
正史における赤壁の戦い
■ 正史における赤壁の戦い
正史における赤壁の戦い
陳寿が記した三国志「正史」では赤壁の戦いについて詳細は語られていません。魏が正統な王朝であるという立場から書いているため、魏に不利になるようなことは省略されているのです。武帝紀には「疫病が流行り、死者が多く出たので帰還したとあります」。呉書の周瑜伝でも「偽りの投降をした黄蓋が密集した曹操の船団に突っ込んで火を放ち、東南の風に乗じて大勝した」と簡潔にまとまっています。
つまり正史だけでは「赤壁の戦い」は詳細がよくわからず、盛り上がることもないのです。
ですからより詳細に書かれている「三国志演義」の話に惹かれます。多分に脚色があるものの、味気のない正史に比べると読んでいてはるかに面白いのが三国志演義なのです。
三国志演義における赤壁の戦い
■ 三国志演義における赤壁の戦い
三国志演義における赤壁の戦い
赤壁の戦いを盛り上げる脚色だろうシーンをあげていくと、
① 外交に訪れた諸葛亮が孫権の配下をどんどん論破していくシーン
② 曹操が周瑜と親交のある蒋幹を送り込み、それを逆手にとって周瑜は曹操の水軍を率いる蔡瑁をスパイ容疑で殺させるシーン
③ 10日以内に10万本の矢が欲しいと周瑜に頼まれて、諸葛亮が承諾。空船20艘で濃霧の中を曹操軍に奇襲を仕掛けて大量の矢を射かけさせて10万本の矢を揃えたシーン
④ 周瑜が黄蓋を鞭打ちして偽降させる「苦肉の計」のシーン
⑤ 龐統が曹操に、揺れが少なくなるよう軍船を鎖でつなぐことを助言する「連環の計」のシーン
⑥ 諸葛亮が東南の風を呼ぶために祭壇を築いて祈るシーン
となります。特徴は諸葛亮が大活躍をするという点です。特に火計を成功させるために欠かせない東南の風は諸葛亮が呼んだことになっているのです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
東南の風については、冬至のあと、この地方では一時的に東南の風が吹くことがあり、周瑜と黄蓋は事前にそれを知っていたのだろうというのが定説です。
赤壁の戦いで曹操に隙を作り、その大軍を火計で破ったのは紛れもなく周瑜の手柄なのです。
後世にそう伝わらなかったのは、正史から意図的に詳細が削除されたこと。
蜀びいきの「三国志演義」が諸葛亮の神算鬼謀の凄さを引きたてるために周瑜を利用していること。この二点でしょう。
赤壁の戦いで最も功績をあげたのは「周瑜」である。そう断言してもいいのではないでしょうか。