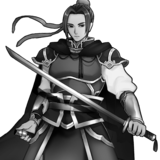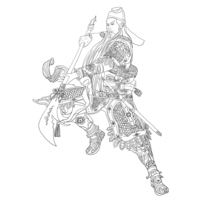危急存亡の秋
■ 危急存亡の秋
危急存亡の秋
危急存亡の秋という故事成語は、蜀の宰相、諸葛亮(孔明)が記した『出師の表(すいしのひょう)』が原典となっています。
『出師の表』とは臣下が君主に奉る文書のことです。
中でも諸葛孔明が劉禅に奉った上奏文が名文として有名です。
劉禅
■ 劉禅
劉禅
章武3年(223年)、父の劉備の崩御に伴い、劉備の子である劉禅(りゅうぜん)が17歳で蜀の二代目皇帝に即位しました。
魏の曹丕、呉の孫権が国を強固にまとめる中、豪族のおぼっちゃんとして育った劉禅は、特にこれといった危機感を感じることなく暮らしていました。
出師の表
■ 出師の表
出師の表
※秋は穀物が実る季節、つまり万物が成熟する大事な時であることから、「大切な時、重要な時期」という意味があり、「あき」ではなく「とき」と読みます。
実際のことは不明ですが、諸葛孔明が『出師の表』として送った文書の通り、益州(蜀)は滅亡してしまったのですから、諸葛孔明は、確かな感覚を持っていたことにもなります。
どうしようもない阿斗(劉禅の幼名)
■ どうしようもない阿斗(劉禅の幼名)
どうしようもない阿斗(劉禅の幼名)
劉禅の「暗愚」「無能」イメージには、いくつかのエピソードがあります。
劉禅は美しい女性を、後宮(妃が住まう場所)に増員していたようです。
諸葛亮の死後、蔣琬、費禕が国政を担当し、その後、「黄皓(こうこう)」という宦官を器用してしまいます。
黄皓は劉禅を政治から遠ざけ、政治を混乱させました。
家臣たちの対立、例えば、特に軍事を司る「姜維(きょうい)」との対立
蜀の国の混乱に乗じ、魏が263年、蜀の攻略に乗り出し、蜀の防衛を担当していた姜維はこれを察知し、何度も援軍の要請をしましたが、宦官の黄皓に邪魔されたりしました。
援軍の要請をためらい滅亡へと導いてしまいました。
劉禅は魏に降伏したのち、魏の首都の「洛陽」に移送されました。
魏での宴会の席で蜀の音楽が流れ、蜀の旧臣たちは涙を流すのですが、劉禅は笑って楽しんでいたそうです。
このエピソードから中国では無能な人物の事を「どうしようもない阿斗(劉禅の幼名)」と言われています。
ただ、近年、暗愚の象徴される蜀の皇帝「劉禅(りゅうぜん)も、40年間は弱小国を守ったことから、再評価の機運もあります。