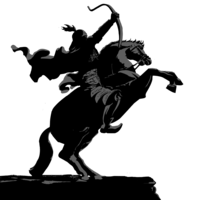1.孫策の生涯を紹介!
■ 1.孫策の生涯を紹介!
1.孫策の生涯を紹介!
孫堅の長男として誕生
■ 孫堅の長男として誕生
孫堅の長男として誕生
孫策は、175年生まれで孫堅の長男として誕生しています。孫策の父である孫堅は、反董卓連合軍の1人であり、董卓軍に大勝利するなどの戦果を挙げています。孫策・孫権の父である孫堅も、十分英雄として誇れるほどの活躍をしているのです。
父の孫堅が戦っている最中は、孫策は寿春にて母や孫権らと暮らしています。実は、このときには周瑜と仲良くなっています。189年には、周瑜の招きで廬江郡に移住し、周瑜は孫策らに大きな屋敷を譲っているのです。孫策と周瑜は、古くから家族ぐるみの付き合いをしていたのです。
17歳で父を亡くす
■ 17歳で父を亡くす
17歳で父を亡くす
191年に父・孫堅は、襄陽の戦いで亡くなってしまいます。このとき孫策は17歳であり、孫家は主家にあたる袁術に吸収される形になります。当然、孫策も袁術の部下になったのです。若干17歳の孫策にはまだ荷が重く、初陣では一揆の首領である祖郎に大敗しています。しかし、次第に頭角を現すようになり、祖郎を敗走させるなどの活躍をしているのです。
そして、194年に孫策は主家である袁術に対し、父・孫堅が持っていた兵力の返還を要求します。このとき孫策は19歳であり、もうすでに小覇王としての片鱗を見せていたのです。この要求に対し、袁術は1000人ほどの軍勢を孫策に返します。実は、この軍勢には孫権の時代に大活躍する武将が大揃いしていました。黄蓋や韓当、程普などが含まれていたのです。
大躍進の20代
■ 大躍進の20代
大躍進の20代
孫権は20代になると大活躍をしています。しかも、孫策は独立する機会を窺っており、着実に孫策は人材登用をしていきます。周泰や蒋欽、張紘など多くの有能な人材を確保していったのです。そして、袁術と劉繇が争っているのを利用し、孫策は独立を画策します。孫策は、自分の配下だけでの劉繇討伐を申し出るのです。
袁術は孫策を警戒し始めていたこともあり、喜んで討伐の許可を出します。これにより、孫策は合法的に袁術から分離に成功したのです。その後、孫策の元には周瑜が加わり、さらに孫堅時代からの兵が続々と集まってきます。5千もの兵力に膨れあがり、195年に孫策は劉繇に大勝します。逃亡する劉繇ですが、さらに追い打ちをかけ勢力を拡大していったのです。こうして孫策の独立は成功し、呉の基礎を作り上げていったのです。
26歳の短命
■ 26歳の短命
26歳の短命
袁術からの独立後も、孫策の勢いはとどまりません。どんどん勢力を拡大しながら、人材登用も積極的に行っていきます。その中には、呂蒙や虞翻なども含まれており、優秀な人材を確保していったのです。孫策は江東一帯を一気に制覇したわけですが、その分多くの抵抗勢力が存在していました。
そして、200年に許貢の刺客に襲われてしまいます。この時の負傷が元で、孫策は26歳で亡くなったのです。死期を迎えた際には、弟である孫権を孫家の長に指名し、補佐として張昭を指名しています。17歳で家督を継ぎ、孫家を再興して呉の基礎を作ったのは、まさに孫策なのです。
2.長生きなら天下統一の可能性はあったの?
■ 2.長生きなら天下統一の可能性はあったの?
2.長生きなら天下統一の可能性はあったの?
26歳以降をシミュレーションしてみよう!
■ 26歳以降をシミュレーションしてみよう!
26歳以降をシミュレーションしてみよう!
孫策が長生きなら天下統一できたのかは、まずは26歳以降をシミュレーションしてみるのが一番です。孫策が亡くなったのは、200年4月のことです。そして、その年の10月に袁紹と曹操は「官渡の戦い」を行っています。実は、孫策は袁紹と曹操が激突するタイミングで、曹操の本拠地である許都を攻略する計画だったとされています。
この計画を実行できれば、曹操を負かすことができた可能性が高いです。当時の曹操軍が、袁紹軍と孫策軍のどちらにも対処するだけの余裕はありません。しかも、官渡の戦いには曹操軍の中心武将が数多く参戦しており、本拠地は手薄となっています。それだけに、ベストタイミングで孫策軍が動けば、曹操の本拠地を制覇することができた可能性が高いのです。
仮に曹操の本拠地を制覇できたら…
■ 仮に曹操の本拠地を制覇できたら…
仮に曹操の本拠地を制覇できたら…
シミュレーション通り、孫策軍が曹操の本拠地を制覇したとします。この場合、史実とは違って官渡の戦いで曹操軍が負ける可能性が高いです。なぜなら、本拠地が奪われたとなれば、兵士は離反する可能性が高くなり、袁紹と戦っている状況ではなくなるからです。
そうなれば、孫策は袁紹と対立することになるでしょう。袁紹は劉表とも手を結んでいるため、なかなか難しい状況です。兵力の面では、袁紹の方が有利な状況となっています。ここでポイントになるのが、曹操に従っていた武将らがどう動いたのかです。曹操軍を上手く吸収することができれば、孫策軍は人材面で袁紹に対抗することができるはずです。
ポイントは孫策のリーダーとしての器量
■ ポイントは孫策のリーダーとしての器量
ポイントは孫策のリーダーとしての器量
孫策が天下統一をできるのかのポイントは、孫策の器量次第かもしれません。シミュレーション通りになった場合、重要なのは孫策が大勢力となってからのリーダーとしての資質です。26歳という若さで亡くなった孫策は、大勢力のリーダーとしての資質は未知数です。そのため、国内の統治や人材活用がどうなっていったのかは微妙でしょう。ただし、生前の孫策は人材登用に積極的だったことを考えれば、大勢力のリーダーとしての資質はあるかもしれません。
可能性だけならあったのかも!
■ 可能性だけならあったのかも!
可能性だけならあったのかも!
結論から言えば、孫策が長生きした場合の天下統一の可能性は、「あり得た」のではないでしょうか。シミュレーション通りになれば、曹操の本拠地を制覇していてもおかしくありません。そうすれば、一大勢力を築き上げることができます。もし、曹操の配下の武将らを取り込むことに成功すれば、人材面でも不安はありません。
しかも、弟の孫堅や信頼できる周瑜がいます。孫堅や周瑜らは、孫策亡き後に呉を建国して天下三分の計を担っているほどです。そのため、仮に孫策に大勢力のリーダーとしての資質がなくても、孫堅や周瑜らのサポートがあれば、十分に統治することができるでしょう。これらのことから、孫策が長生きしていれば、「天下統一していた」なんて未来もあったのかもしれません。
3.まとめ
■ 3.まとめ
3.まとめ
今回は、小覇王として知られる孫策の生涯ともし長生きしていたらについて紹介してきました。孫策は、17歳で家督を継ぎ袁術からの独立や勢力の拡大など、呉の礎を築いた人物です。しかし、26歳の若さで亡くなっています。もし、長生きしていれば、天下統一の可能性はあったかもしれません。歴史に「もし」というのは意味がないことですが、三国志好きとしてはつい想像してしまいます。他の三国志の君主や武将でも、「もし」を想像してみてください。