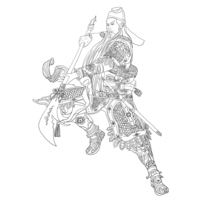夷陵の戦いへ
■ 夷陵の戦いへ
夷陵の戦いへ
関羽の死後、呂蒙と曹操が相次いで亡くなり、三国はそれぞれ激動の一過を辿っていきます。中でも魏は功労者の曹操の跡を継いだ曹丕が献帝から禅譲を受けて魏の皇帝となり、後漢が滅びました。漢王朝の復興を掲げていた劉備(玄徳)は関羽の死と合わせてショックを受け、臣下の勧めもあって蜀王朝を興しました。
関羽の弔い合戦を模索していた劉備(玄徳)でしたが、今度はいざ出陣の前に腹心の張飛までも失います。張飛は部下の裏切りに遭い、配下たちは呉へと亡命しました。関羽と張飛の弔い合戦となったことで、劉備(玄徳)は諸葛亮の諌めを聞くことなく自ら指揮官となって数万の軍を率いて進軍していきます。
孫権は劉備(玄徳)の大軍が差し迫っていると聞き、まずは和睦の使者を送りますが、劉備(玄徳)の怒りを抑えることができず失敗に終わると、陸遜を大都督として劉備(玄徳)軍を迎え打ちます。陸遜は数万規模の軍を率いるのは初めてとなりますが、極めて冷静沈着に勤めようとし、劉備(玄徳)の布陣を研究していきます。
実戦経験の少なさを問題とせず軍を率いる
■ 実戦経験の少なさを問題とせず軍を率いる
実戦経験の少なさを問題とせず軍を率いる
戦歴という点では董卓や黄巾の乱といった歴戦を経験している劉備(玄徳)のほうが圧倒的に上であり、まだ実戦経験の乏しい陸遜では劉備(玄徳)を相手にするのは難しいと呉の諸将らは考えていました。そのため、陸遜の命令に従わない意思を明確にする将軍までいました。
このことは劉備(玄徳)も考えており、たとえ関羽を貶めたとはいえ、呂蒙や曹仁といった古参の将軍たちがいたから陸遜の策が冴え渡ったものであり、決して大軍を率いて勝負できるものではないと踏んでいました。
呉の陣営では孫策時代からの諸将であったり、孫氏の一族でもあることで、陸遜に不服を唱えるものが相次ぎました。前途多難といえましたが、陸遜は一向に臆せず、剣を手に取り、厳しい態度で軍令を守らせました。
陸遜は慎重な行動を促し、討って出ることを主張する諸将たちと衝突します。陸遜の消極的な姿勢に劉備(玄徳)も軍を二手に分けて挑発しますが、これは陸遜が防ぎました。迎撃するべきであると諸将が迫っても陸遜は自身の案を引かず、大軍の劉備(玄徳)と応戦した孫桓が包囲されたときも、孫桓を信じることで援軍を出さないでいました。
火計で劉備(玄徳)を死地に追いやる
■ 火計で劉備(玄徳)を死地に追いやる
火計で劉備(玄徳)を死地に追いやる
まだ若い孫桓でしたが、懸命に堪え、何とか突破されるのは防ぎます。陸遜は劉備(玄徳)軍と応対し、その都度退却をしては時間を稼ぎます。すでに呉の領土にまで侵入してきた劉備(玄徳)軍の勢いを止めることは難しく、呉の諸将たちも焦りが生じてきました。
一方の劉備(玄徳)軍では臣下の黄権が侵入し過ぎなので総大将は後方にいるようにと進言しています。しかし、呉軍の弱さを突いた劉備(玄徳)は応じることはなく、むしろ黄権を後方に置いて、自分はさらに進軍していきました。
陸遜は大規模に軍を動かさず、局地的に劉備(玄徳)軍と戦うことで、相手方の陣容を把握していきます。劉備(玄徳)陣営は進路と退却路の確保に数十ある陣を密集させていました。陸遜はこの布陣が火計に弱いと踏み、夜襲をかける決断をします。
陸遜の号令とともに大半の軍を持って襲撃した呉軍は、劉備(玄徳)の陣に向けて火を放ちます。たちまち陣から陣へと火が移り、劉備(玄徳)軍は大混乱を喫してしまいます。特に水上から後方の陣を焼き放つと、劉備(玄徳)軍は大きく後退し、撤退を余儀なくされます。陸遜はあらかじめ退路を断つように布陣しており、劉備(玄徳)は四方から呉軍に攻めたてられ、馬良など多くの有能な家臣が戦死しました。
蜀の地で待機していた趙雲は事態の急変を察知し、独断で救援に駆けつけ、劉備(玄徳)はかろうじて脱出することができました。しかし、度重なる臣下の死や後漢の衰退、大敗北を受けて60歳を過ぎていた劉備(玄徳)は、心労から倒れてしまい諸葛亮に後事を託して死去しました。これにより、蜀は荊州から完全に撤退することになり、陸遜は呉内部でも大きな発言力を持つようになります。
呉で評価が上昇していく
■ 呉で評価が上昇していく
呉で評価が上昇していく
陸遜の大活躍を受け、これまで批判を繰り返してきた古参の諸将は、陸遜から孫権への報告を恐れていました。孤立していた孫桓も、当初は陸遜を恨んでいましたが、その類まれない智謀の深さを恐れ入るようになっていきます。
一方の陸遜は、古参の将軍たちが刃向い、命令を無視したことを孫権へ一向に報告せず、咎めることもしませんでした。これに対し、諸将は陸遜を信頼し、尊敬するようになっていきます。また、孫権も諸将の報告をしなかった陸遜の振る舞いを大いに評価しています。
演義では諸葛亮に敗れた陸遜
■ 演義では諸葛亮に敗れた陸遜
演義では諸葛亮に敗れた陸遜
小説の三国志演義では夷陵の戦いで続きがあり、劉備(玄徳)の救援に駆け付けたのは趙雲だけでなく、諸葛亮自らも動いたとされています。石兵八陣という迷路のような巨大な石を用いて突風や波が起こるように細工され、陸遜ら呉軍が舞い込むと、自らの力では抜け出せないようになっています。
とても恐ろしい陣で、諸葛亮は本気で陸遜の抹殺を図りますが、見かねた老子が山を下り、陸遜に力を貸して脱出させています。陸遜は諸葛亮を恐れてそれ以上追撃せず、魏の侵攻に対処するという話になっています。もちろん、周瑜でも勝てなかった諸葛亮ですから、陸遜が叶わなかったとしても致し方ないといえるでしょう。
魏との戦いを進言
■ 魏との戦いを進言
魏との戦いを進言
本拠地に戻った陸遜でしたが、今度は蜀を奪い取ろうという案が浮上します。これには劉備(玄徳)が白帝城に留まり、諸葛亮や主だった臣下が揃っていたため、荊州に近いここを急襲すれば蜀を滅ぼせると踏んだからです。
孫権は蜀攻撃はと慎重派の意見をまとめ、陸遜の考えを聞こうとします。陸遜は今は劉備(玄徳)ではなく、北にいる曹丕への警戒をするべきであると促します。ちょうどその頃、曹丕は孫権が魏に対し臣下の礼を取るべく太子を人質に送る条件を守っていないという口実を取って、蜀との決戦で援軍を送るという名目で大軍を南下させていました。
陸遜はこの魏軍が援軍なのではなく、呉を奪い取ろうという魂胆であることを見抜き、劉備(玄徳)と和睦して魏に備えるべきであると進言します。
劉備(玄徳)は魏が侵攻する報告を聞くと、挟撃するために呉へ向けて再度侵攻するという手紙を送りますが、陸遜は今の蜀にそんな余裕はないと見抜き、和睦を成立させます。対蜀は落ち着きを取り戻したことで、呉軍は対魏へと全力を傾けることができ、曹丕ら大軍を退けることに成功しています。