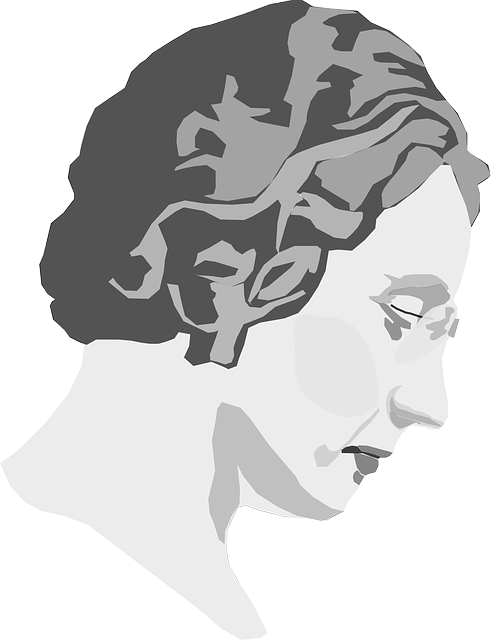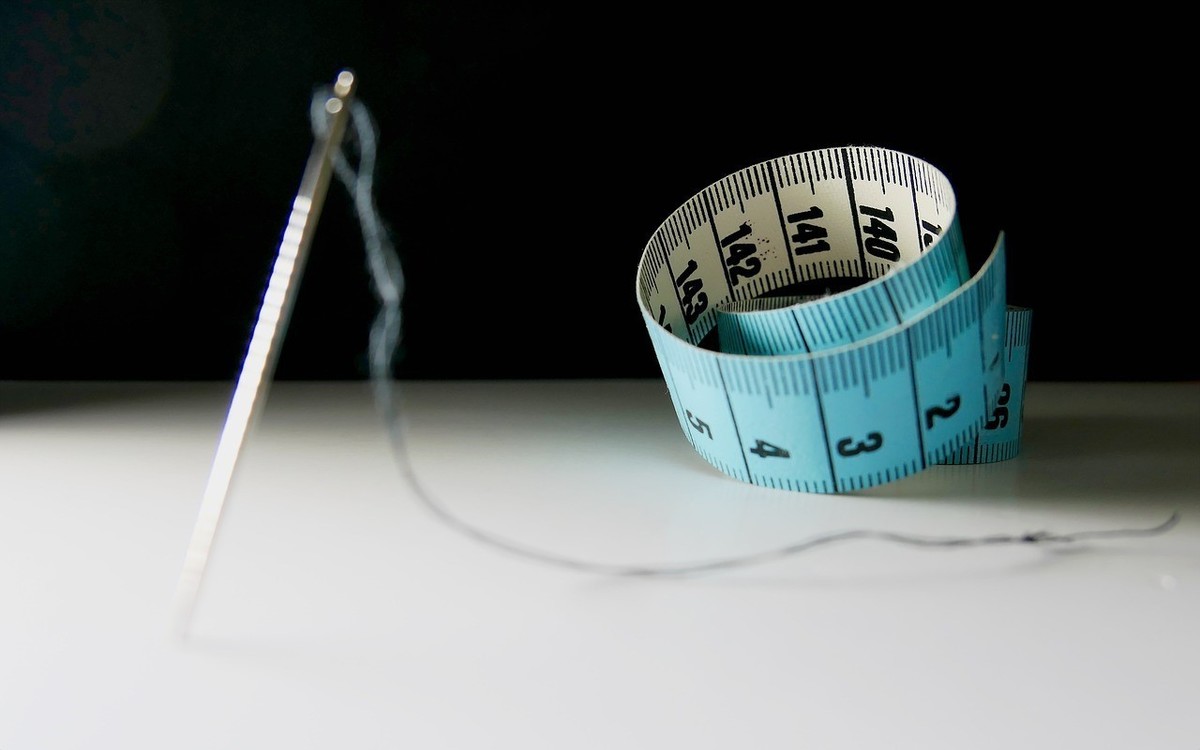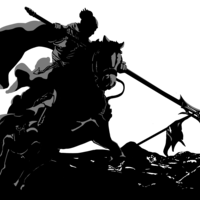側室が少ないところも人気の一つ?劉備(玄徳)にまつわる女
■ 側室が少ないところも人気の一つ?劉備(玄徳)にまつわる女
側室が少ないところも人気の一つ?劉備(玄徳)にまつわる女
皇帝は多くの側室を設けるという流れがあった三国時代でしたが劉備(玄徳)は最小限の夫人しかいなかったためフェミニストだったのではないかと言われています。
劉備(玄徳)の周りには最初の正妻である甘夫人、側室の麋夫人、および孫夫人しかいません。中でも孫夫人は政略結婚でしたが呉の策略通りいかないとされたため孫夫人は呉に連れ戻されてしまったため実質の側室は麋夫人のみでした。
そういったところも民衆の支持を集めたのではないかと思います。しかし後を継いだのが劉禅(公嗣)という事を考えるともう少し宮女を設け有能な子供をもうけておけばよかったのにと思わずにはいられません。
宮女を囲わないというのは経済的を圧迫することがないため国力が下がることがないと考えられがちですが、いい跡継ぎが生まれないというデメリットも生じてしまいます。とはいえいい跡継ぎが多くても跡目争いが起こりかねないので、一概に宮女が多いからいい、少ないからいいという訳でもなさそうです。しかし多くの君主は自分の欲望のために奥の宮女を囲うという事も少なくなく、恐らく民衆からはそういった目で見られていたのではないかと思います。それを考えると宮女が少ない劉備(玄徳)は理想的な君主だと思われていたことでしょう。
女によって皇帝となることができなかった董卓(仲穎)、人生を狂わされた呂布(奉先)
■ 女によって皇帝となることができなかった董卓(仲穎)、人生を狂わされた呂布(奉先)
女によって皇帝となることができなかった董卓(仲穎)、人生を狂わされた呂布(奉先)
三国志の前半、最も権力を持ち、最も皇帝に近かったのが董卓(仲穎)です。野心にあふれやりたい放題していたため、生きていたら間違いなく皇帝となっていたでしょう。しかし身内の呂布(奉先)によって阻まれました。そして呂布(奉先)が董卓(仲穎)を討つ原因を作ったのが女である貂蝉でした。
結果的には絶世の美女として知られる貂蝉の取り合いから二人の争いが勃発し、最終的に呂布(奉先)が董卓(仲穎)を討ち晴れて貂蝉を自分の妻にするという算段でした。
ところが貂蝉は呂布(奉先)の妻になることは全く望んでおらず董卓(仲穎)が討たれるとすぐに自決し、呂布(奉先)はすぐに「貂蝉にはめられた」と気づいてしまうのです。
貂蝉が現れなかったら董卓(仲穎)は皇帝になれたし、呂布(奉先)は丞相となり少なくとも彼らが生きている間は各地で殺戮が繰り返すのをよしとした世の中が出来上がったかもしれません。
こいつの宮女にだけはなりたくない!やばすぎる男孫晧(元宗)
■ こいつの宮女にだけはなりたくない!やばすぎる男孫晧(元宗)
こいつの宮女にだけはなりたくない!やばすぎる男孫晧(元宗)
三国志において最も残虐な人間は?と聞かれると多くの人が「董卓(仲穎)」と答えることだと思います。もしくは「曹操(孟徳)」と答える人もいるでしょう。しかし私は孫晧(元宗)こそが残虐な人間で最悪な君主だったと思っています。
まず董卓(仲穎)と曹操(孟徳)は生まれのアドバンテージがあった物の、自分の力でトップまで上り詰めて国を治めるという能力がありました。
しかし孫晧(元宗)は周りが敷いたレールを進んだだけです。しかも彼は幼少期からちやほやされていたため自分が正されるという事をしてきませんでした。
そのため自分の思い通り事が運ばないと他人を処刑し、そうしてもいいものだという思考回路になっていました。
さて、この孫晧(元宗)、腐っても皇帝という位置づけなのでもちろん多数の宮女がいました。その数5千とも言われています。数が多くどうしようもない皇帝ですが、それ以上に見過ごすことができないのが彼のふるまいです。
孫晧(元宗)は宮女に対し暴力をふるったり切り刻んだりしていたというエピソードもあります。なんでも思い通りになり、何をしても許されると思っていることがここからも見て取ることができます。
そのため呉が晋に討ち滅ぼされた際に「これでよかった」と思った人間は少なくないという記述すらあります。そして女中が最もそう思っていたのではないでしょうか。
最終的な宮女の数は1万人!司馬炎(安世)の宮女について
■ 最終的な宮女の数は1万人!司馬炎(安世)の宮女について
最終的な宮女の数は1万人!司馬炎(安世)の宮女について
三国志の中で最も宮女を囲っていたのは間違いなく司馬炎(安世)です。彼はとにかく酒色が好きで囲っていた宮女の数は1万人ほどと言われていました。
それもそのはず、司馬炎(安世)は長きにわたって覇権争いを行っていた三国時代に終止符を打ち三国を統一した人物だから「何をしてもいい皇帝」でした。
何をしてもいい皇帝が酒色好きとなったら宮女の数が多くなるのは必然的です。しかし司馬炎(安世)のそれはとにかく度を越えていました。元々宮女が5千人ほどいたと言われていますが、さらに上で挙げた孫晧(元宗)が囲っていた宮女5千人を加え総勢1万人の宮女を囲うことになりました。
三国を統一した司馬炎(安世)ですが、息子の司馬衷(正度)に皇位を継がせ酒色にふける生活を送っていました。求心力のない司馬衷(正度)は国力を下げせっかく統一した中華もすぐに分裂してしまうようになりました。
宮廷にいた男について
■ 宮廷にいた男について
宮廷にいた男について
宮廷に男が入ることはご法度とされていました。それは宮女と間違いがあって皇帝の子かその男の子か分からなくなるという可能性があったからです。そのため男は隔離されていたわけですが、宦官となれば別です。
宦官とは男性器を取った男性を指します。男にして宮廷にいる。そして皇帝の一番近くにいたため位は高かったようです。いい暮らしができるのであれば男性器を取ってもいいと考える者は少なくなかったためそこそこ人気はありました。
確かにどうしようもなく生活苦で超貧困を極めるのであれば「宦官となって安定した生活を」と思うこともあるかもしれませんね。余談ですが、宦官にはプライドが高かったり野心が強かったりする者が多かったと言われています。
きっと「自分は一番大事なものを失ったんだからその見返りがあって当然だ」とどこかで思っていたのでしょう。
そんなもの達が皇帝の一番そばに仕えているため皇帝の考えが屈折していくことは容易に想像がつきます。その結果が十常侍だったわけですが、この制度が廃止されることはなかったようです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志の女にまつわる話をまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。女に溺れる者、女によって人生が狂わされたものなど多々います。とはいえやはり合戦などとは違いサイドストーリー的な要素が強いので肩の力を抜いて楽しんでもらえれば幸いです。