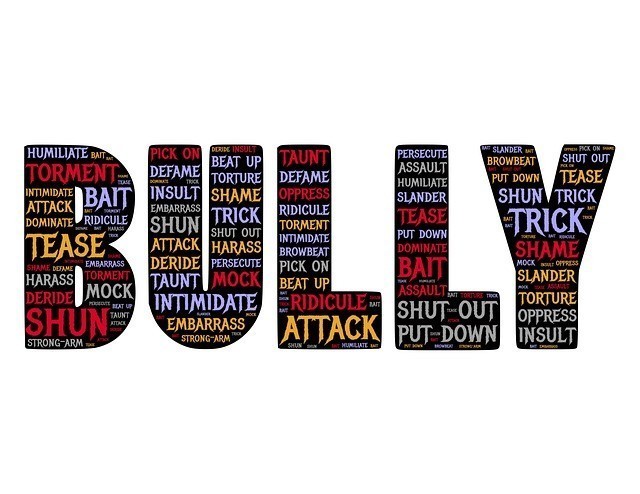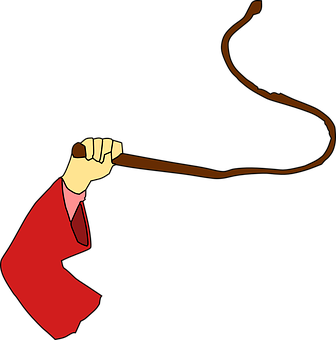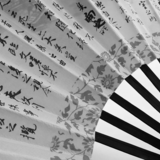劉備(玄徳)の黄巾討伐はフィクション
■ 劉備(玄徳)の黄巾討伐はフィクション
劉備(玄徳)の黄巾討伐はフィクション
「三国志演義」では、桃園の誓いの後、劉備(玄徳)らは義勇兵を募って黄巾討伐のために、幽州の太守のもとへ向かいます(幽州刺史なのか、どこかの郡の太守なのかは不明)。
幽州の太守を務めていた劉焉は、義勇兵募集の高札を立てていたからです。
劉焉は劉備(玄徳)らを迎え入れ、校尉である鄒靖の部隊に組み込み、見事に大興山に陣取る大将の程遠志と副将の鄧茂を討ち取ります。
「三国志正史」によると劉焉は冀州刺史こそ歴任したことはありますが、幽州では刺史も太守も務めていません。黄巾の乱が発生して以降は、益州の牧として、幽州から遥か遠くで反乱軍を鎮撫しています。
なぜ三国志演義は劉焉と劉備(玄徳)を無理やり結びつけたのでしょうか?
それは蜀の基盤を築いたのが劉焉だからです。劉焉から子の劉璋に益州は受け継がれ、そして劉備(玄徳)に奪われます。
三国志演義は、劉焉と劉備(玄徳)を結び付けておくことで、劉備(玄徳)が益州を制圧する正統性を少しでも高めたかった狙いもあったのでしょう。
劉備(玄徳)は程遠志らを討った後は、豫州で地公将軍・張宝を撃破、さらに荊州では孫堅と協力してどんどん黄巾の反乱を鎮圧していきます。
しかしこれも三国志演義の創作で、三国志正史には、鄒靖に従って黄巾を討伐したとしか記されていません。
三国志演義では主役の劉備(玄徳)をヒーローにすべく脚色されているのです。
冀州安喜県尉となる
■ 冀州安喜県尉となる
冀州安喜県尉となる
黄巾の討伐に参加した劉備(玄徳)は、その功績によって冀州安喜県尉に任命されます。こちらは三国志正史にも記載されています。三国志演義では、あれだけ活躍したはずなのに地方の下役人にしかなれなかったと恨み節です。それでも劉備(玄徳)は不平不満も漏らさずに、着任して善政を敷き、領民に慕われるようになります。
「尉」というのは、武官系の官位で、軍事や警察、刑罰などを扱っていたようです。朝廷には「太尉」という官位があり、こちらは三公のひとつになります。郡には都尉がおり、県には県尉が置かれました。
劉備(玄徳)は地元警察のような役割で、悪を取り締まったのではないでしょうか。なにせ側近には猛将として名高い関羽と張飛がいます。逆らえる者がいるはずがありません。
この時期は朝廷の権威も失墜していましたから、反乱なども各地で発生しています。劉備(玄徳)はそのような戦乱から領民を守り抜いて名声を高めたのでしょう。
しかし、ここにお邪魔虫が登場してきます。それが「督郵」です。
督郵とは個人の名前ではない
■ 督郵とは個人の名前ではない
督郵とは個人の名前ではない
三国志正史においても、三国志演義でも、そんな劉備(玄徳)の善政をぶち壊すべく登場するのが督郵になります。かなりインパクトのあるシーンなので、三国志において、督郵の名は有名です。しかし個人の名前ではありません。官位です。
督郵とは、郡太守の視察官になります。所轄する県の役人の治績や法規などを監察し、評定するのが役目です。犯罪行為を行っている役人を取り締まるわけですから、風紀を正しには必要な役職なのですが、劉備(玄徳)のもとに派遣された督郵は悪人でした。
督郵は劉備(玄徳)に対して横柄な態度で、劉備(玄徳)が皇族宗家を騙っていると侮辱します。劉備(玄徳)の善政も否定しました。それでも劉備(玄徳)はこらえます。さらに督郵は、劉備(玄徳)が賄賂を贈らない姿勢を見せたことから怒り、劉備(玄徳)を犯罪者に仕立てあげようとします。まさに官の腐敗を象徴するような場面です。
イメージするのならば、忠臣蔵に登場する浅野内匠頭と吉良上野介の関係に似ているかもしれません。頭にきた浅野内匠頭は、江戸城松之大廊下で刀を抜いて吉良上野介に斬りかかっています。
督郵反撃を受ける
■ 督郵反撃を受ける
督郵反撃を受ける
ここからのお話は諸説あります。
まず一番有名なのは、三国志演義のシーンでしょう。張飛の怒りが爆発して、督郵を縛りつけ、木に吊し上げると、柳の枝で滅多打ちにするのです。
劉備(玄徳)はそんな張飛を止めて、諫める役目です。我慢強く、仁徳深い劉備(玄徳)らしい行動ではないでしょうか。
この後、劉備(玄徳)は関羽とも話し合い、張飛を連れて出奔します。ここは自分の活躍する場所ではないと悟ったからです。督郵の悪行など氷山の一角に過ぎず、民に善政を敷くためには国全体を正す必要性を感じたのでしょう。
この三国志演義の原典が「平話」なります。民衆が愛した三国志の話ですが、ここに登場する張飛は、枝で打つといった優しい対応はしていません。督郵を縛り上げて殺害し、さらに首や手足をバラバラに切り刻んで、それを門に吊るしました。
ホラー映画も真っ青の残酷なシーンになります。しかし民衆には、権力に暴力だけで立ち向かう張飛像は受け入れられていたようです。
それでは、三国志正史にはどのように記されているのでしょうか?
こちらでも横柄な態度を取る督郵は、劉備(玄徳)の面会要求を拒否しました。三国志正史の劉備(玄徳)像は、乱世の英雄らしく猛々しさを有しています。劉備(玄徳)は怒って督郵が滞在している場所に押し入り、縛り上げた挙句、杖で200回ほど打ちすえたのです。
杖で200回も打ちすえられたのでは、普通に考えて死亡しています。まさに悪を取り締まる警察官の役目をまっとうしたわけですが、やり過ぎといった気もします。とても仁徳深い人間の所業ではありません。
まとめ・三国志演義はちょうどバランス良く話をまとめた
■ まとめ・三国志演義はちょうどバランス良く話をまとめた
まとめ・三国志演義はちょうどバランス良く話をまとめた
ということで、三国志正史の話をまともに扱ったのでは、読者が混乱する可能性があり、下手をするとアンチ劉備(玄徳)を生み出しかねません。ということで三国志演義では却下されたのです。
ですから劉備(玄徳)が官の腐敗に対して納得がいかないのは変わりないのですが、乱暴を働くのは張飛の役目になります。かといって殺してしまうのはさすがに問題あるので、柳の枝で打つぐらいで抑えられています。
あくまでも劉備(玄徳)は理想の仁君であり、腐敗に染まることもなく、また冷酷な行動もしません。勇んだ張飛をなだめるのがちょうどいいくらいです。
もしかしたら本当の劉備(玄徳)は関羽や張飛以上に荒々しく、一度火が付くと手が付けられなかったかもしれません。だとしたら、逆に現代でも劉備(玄徳)の人気は衰えることがなかったのではないでしょうか。
理想像を押し付けられた劉備(玄徳)ではなく、素の劉備(玄徳)をぜひ知りたいですね。