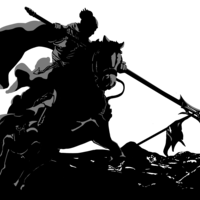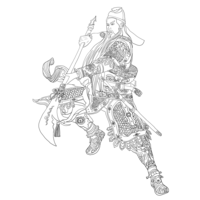呂布
■ 呂布
呂布
呂布、字は奉先。幷州五原郡九原県の出身です。
魏・呉・蜀のどこにも所属しておらず、三国志では前半だけに登場するのですが、最強を誇った武将として強烈な個性を放っています。
読者に与えるインパクトは、その武勇だけではなく、主君を二度も裏切り殺害するという忠義心ゼロのヒール性にもあります。裏切りは、戦国の世ではよくあることではありますが、三国志演義の設定では、義理の親子関係を結んだ丁原、董卓と、呂布は主従関係以上に重用されているにも関わらず恩を仇で返しています。しかも完全に自分の利益を優先しただけの行動で、もちろん大義などありません。
しかし、呂布は三国志の中で指折りの人気者です。その徹底した悪役ぶりと、颯爽とした強さが魅力になっているのです。容姿にも優れ、美女・貂蝉との悲劇の恋愛は、京劇にも取り上げられているほどです。
呂布の活躍
■ 呂布の活躍
呂布の活躍
三国志正史での呂布の活躍シーンは大きく分けて三つになります。
ひとつは、朝廷を牛耳っていた董卓を司徒・王允と協力して暗殺し、長安の都を占領したシーンです。ここでは、呂布は董卓の侍女と密通していたと記されています。その露見を呂布は恐れて、王允に手を貸したようです。
次の活躍の場は、長安から落ち延びた呂布が、陳宮や張邈と協力して曹操の拠点である兗州の大部分を支配したシーンです。この時、曹操は徐州を攻めており、兗州を留守にした状態でした。最終的には曹操が勝つものの、かなり追い込んだのは事実です。
もうひとつは、徐州に逃れた呂布が、支配者であった劉備(玄徳)から徐州を奪い取ってしまうシーンです。曹操に敗れ落ち延びてきた呂布を劉備(玄徳)は歓迎してくれたのに、ここでも恩を仇で返す行為をしています。
三国志演義では、さらにここに反董卓連合との戦いである「虎牢関の戦い」が加わります。この戦いで呂布は圧倒的な武勇を示すことになるのですが、三国志正史にはそのような記載はありません。三国志演義の脚色ということになります。
呂布の一騎打ち(虎牢関の戦い)
■ 呂布の一騎打ち(虎牢関の戦い)
呂布の一騎打ち(虎牢関の戦い)
それでは無類の強さを誇る呂布の一騎打ちの場面を振り返っていきましょう。
三国志演義では第5回になります。ここではまず、董卓配下の猛将・華雄が大活躍するのですが、最期は関羽に一刀両断にされてしまいます。
そして真打ち、呂布が登場するのです。
最初の相手は、河内太守・王匡の配下で鑓の使い手として武名を知られている方悦になります。しかし呂布と五合あまり打ち合った後に、突き殺されてしまいました。呂布の楽勝でまずは1勝目です。
次は上党太守・張楊の配下の穆順です。穆順も槍をしごいて呂布に挑みましたが、こちらは一撃で敗れています。先ほど以上の楽勝ぶりで呂布の2勝目。
さらに北海国相・孔融の配下で鉄槌の使い手、武安国が呂布に挑みますが、数十合ほど打ち合った末に腕を斬り落とされてしまいます。これで3連勝です。
ここで登場するのが公孫瓚です。ここまで呂布の相手をしてきた武将たちは三国志演義の架空の人物であるのに対して、公孫瓚は実在した人物になります。ただし、三国志正史によると董卓との戦いには参戦していません。
しかし三国志演義では劉備(玄徳)を引き連れ、第十四鎮として呂布と対戦。公孫瓚は呂布と一騎打ちを演じますが、数合も打ち合わないうちに敗走しています。
代わりに登場するのが張飛です。五十合打ち合っても呂布は張飛を倒せませんでした。引き分けなのですが、やや張飛が不利だと感じたのか、ここで劉備(玄徳)・関羽も参戦して呂布を仕留めにかかります。
三人対呂布ひとりですから、通常の一騎打ちとは設定が異なりますが、呂布は三人相手に奮戦。しかし最後はさすがに不利になって呂布は撤退しています。ここで呂布は初黒星です。
呂布の一騎打ち(兗州戦)
■ 呂布の一騎打ち(兗州戦)
呂布の一騎打ち(兗州戦)
曹操の拠点である兗州を奪った呂布は、本格的に曹操と対峙することになります。
まずは曹操配下の猛将・許褚と一騎打ちをし、二十合ほど打ち合います。結果としては引き分けですが、曹操は許褚では呂布に勝てないと判断しました。
ここに典韋・夏侯惇・夏侯淵・李典・楽進が加わり、六人対呂布ひとりとなります。それでも持ちこたえるのが呂布の凄さです。この六人相手にひとりで戦えるのは呂布ぐらいなものでしょう。しかし、さすがに厳しくなり、最後は呂布も退却しています。これで2敗目となりますが、負けはどちらも複数相手の戦いですから仕方ありません。
兗州戦での呂布は一騎打ちで成果をあげていません。もはや呂布は独立した勢力になっており、全軍の統率がメインの役割になっていますから、一騎打ちが少なくなるのは当然のことです。
呂布の一騎打ち(徐州戦)
■ 呂布の一騎打ち(徐州戦)
呂布の一騎打ち(徐州戦)
曹操に負けた呂布は徐州に落ち延び、劉備(玄徳)と合流しますが、劉備(玄徳)が袁術と戦っている最中に徐州を奪ってしまいます。
その後、劉備(玄徳)は曹操と手を結んで呂布と戦うことになります。
そんな呂布が一騎打ちをする相手がまたもや張飛です。まさに因縁の相手と呼べるでしょう。第十六回では、呂布と張飛が百合も打ち合いますが勝敗がつきません。
さらに袁術も呂布討伐の軍を派遣してきますが、李豊を三合も打ち合わずに撃退しています。呂布にとっては久しぶりの一騎打ちの勝利です。
第十九回でも呂布は張飛と三度目の一騎打ちをしています。しかし、ここでも互角で勝敗はつきませんでした。さらに呂布は関羽とも一騎打ちをし、こちらも引き分け。
関羽・張飛が呂布に匹敵する武勇であることを強調しています。
まとめ・12戦で5勝
■ まとめ・12戦で5勝
まとめ・12戦で5勝
こうして最強を誇った呂布は、味方に裏切られて捕らえられ、最期は曹操の命令で処刑されてしまいます。
一騎打ちの通算成績は12戦5勝です。勝率41.7%ですね。三人相手や六人相手にしたのを含まなければ10戦5勝で無敗。それでも勝率は50%となります。最強というにはイマイチな結果ですね。
もちろんこれは劉備(玄徳)を主役にした三国志演義のお話です。ですから敵対する呂布が関羽や張飛の引き立て役になってしまっているのも仕方のない話でしょう。
ちなみに三国志正史ではこれらの一騎打ちは一切記されておらず、逆に董卓配下の猛将・郭汜と一騎打ちをしたことが記録されています。もちろん呂布の勝ちですが、優勢勝ちといった感じで、郭汜を討ち取ってはいません。三国志正史では勝率100%ということです。
三国志正史に記されている一騎打ちは、この呂布対郭汜の戦いの他、あと二つしかありません。
武将同士の一騎打ちは三国志の名物シーンですから、これではちょっと寂しいですね。やはり三国志演義の演出があってこその盛り上がりではないでしょうか。そうなると必然的に呂布の対戦成績も下がってしまうのですが・・・