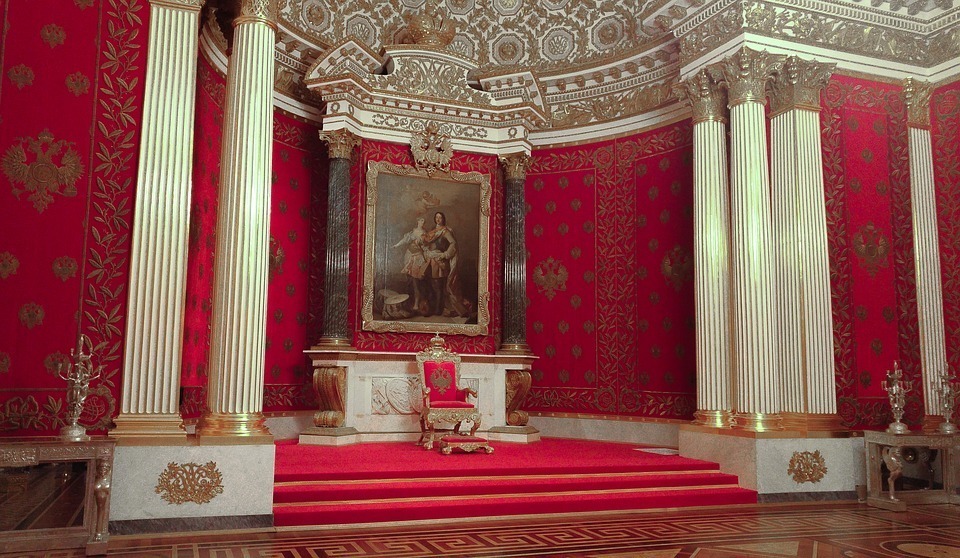何皇后の標的にされ、母が毒殺されてしまう
■ 何皇后の標的にされ、母が毒殺されてしまう
何皇后の標的にされ、母が毒殺されてしまう
後漢王朝の最期の皇帝と称されるのが献帝です。父は第12代皇帝の霊帝で、母は側室ながら霊帝の寵愛を受けていました。生まれてからは劉協と名付けられ、皇族の一員として属しますが、母は何皇后の嫉妬を受けて毒殺されてしまいます。
生後間もなく母を亡くした劉協でしたが、当然何皇后の標的にされてしまいます。しかし、不憫に思った、霊帝の母に育てられて守られていきます。この何皇后はもともと平民でしたが、その美貌を見込まれて霊帝の妾となり、皇后にまで登りつめます。兄も屠殺業を営み、妹のおかげで出世し、いつの間にか大将軍となった何進で、兄妹で権力を握っていたと考えられます。
何進や皇后は平民出の一族だけに、宮中では敵も多く、特に霊帝の付き添いでもある宦官たちと火花を巡らせていました。劉協には何皇后が生んだ兄の劉弁がおり、どちらが後継者になるか意見は分かれていたといいます。
霊帝崩御後、権力闘争に巻き込まれる
■ 霊帝崩御後、権力闘争に巻き込まれる
霊帝崩御後、権力闘争に巻き込まれる
189年に霊帝が崩御すると、兄の劉弁が小帝として即位します。劉協は暗殺されることもなく、渤海王として封じられ、後に陳留王に移封されています。朝廷内では宦官の十常侍が権力を握っていましたが、小帝と血縁関係にある何進が宦官を抑え込もうとして対立していきます。
しかも、大陸全土では政治の混迷によって世の中の秩序が乱れており、太平道を指示する民衆によって反乱が起きています。いわゆる黄巾の乱が勃発していました。何進は各地の将軍たちに制圧を指示させていましたが、黄巾の乱は一旦収束を見せるものの、各地では小規模の軍勢となって反乱を起こし、それを鎮圧していたのが地方の豪族たちでした。
何進は都に各地の将軍を集めて十常侍を牽制しますが、何皇后に取り入った宦官によって和解します。しかし、この和解は偽りであり、何進は袁紹が止めるのも聞かずに単身宮廷に赴き、暗殺されてしまいます。
何進が殺されたことを受けて、配下だった袁紹や袁術は宮廷内に攻め込み、十常侍を討ち取っていきます。さながら宮廷は地獄絵のようになっていきますが、小帝と劉協は助け出されて無事でした。
董卓の専横で献帝となる
■ 董卓の専横で献帝となる
董卓の専横で献帝となる
二人を保護したのは、西涼の将軍董卓でした。董卓は実力者の丁原を騙し討ち、配下の呂布を引き込みます。一気に権力を手中にした董卓は、政治の実権を握ります。董卓はとても善政を敷くことなく、民衆を圧迫し、中央はますます混迷していきました。
しかも、董卓は小帝を廃して暗殺し、劉協を皇帝へと即位させました。これが献帝です。半ば強引に即位させられた献帝でしたが、味方になれるのはごくわずかな側近のみという苦しい状況に追い込まれました。
献帝は自分の窮地を救ってくれる英雄の登場を待ちわびており、董卓の圧政から民衆を救ってあげたいと実に願っていたといいます。朝廷内に政治が腐敗していることが分かると、各地の豪族たちが権力を欲し、自衛の目的もあって領土を制圧していきます。袁紹や袁術も自領土に戻り、君主として君臨していきました。
政治的能力を開花させることができない献帝は、側近に相談すると、各地の豪族を呼び寄せて反董卓連合を組ませようと計画します。その筆頭に名家の袁紹を担ぎ上げ、孫堅や袁術など、三国志でも有名な群雄たちが兵力を持参して洛陽を目指していきます。
董卓の暗殺
■ 董卓の暗殺
董卓の暗殺
董卓軍と連合軍の戦いは、董卓軍が序盤を制していましたが、主力の呂布が古参の武将たちを折り合いが合わず、仲たがいをしてしまいます。その隙をついた孫堅によって攻め込まれ、董卓軍は敗走していきます。焦った董卓は献帝を引き連れ、洛陽を燃やして長安に遷都しました。
董卓は長安でも暴虐を繰り返し、とても人道とはかけ離れた所業を尽くしていきます。見かねた司徒の王允は、董卓暗殺計画を練り、身辺警護を伴っていた呂布を誘います。呂布も董卓に見切りを付けており、王允の誘いに乗りました。
献帝は病気になったと偽り、董卓が快気祝いに参上したところを呂布が襲い、董卓は命を落としました。こうして王允と呂布によって、董卓の専横から救われた献帝でしたが、今度は董卓の残党が牙をむいて来ます。
王允の死後、李カク・郭汜によって隔離される
■ 王允の死後、李カク・郭汜によって隔離される
王允の死後、李カク・郭汜によって隔離される
王允は董卓の残党を許さず、殲滅を呂布に言い渡します。しかし、李カク・郭汜ら董卓軍の残党は、参謀の賈クによって長安を攻め、呂布軍は敗れていきます。李カク・郭汜らが長安になだれ込むと、呂布は王允に逃げるように言い放ちますが、王允は残された若い献帝を不憫に思い、「陛下をお守りする」と言い残して呂布と別れました。
王允は李カク・郭汜らによって殺害され、献帝は保護下に置かれてしまいます。さすがに献帝も李カク・郭汜を諌めますが、軍勢を持っているので、言う事を聞くことはありませんでした。
賈クや董承によって長安を脱出
■ 賈クや董承によって長安を脱出
賈クや董承によって長安を脱出
政治の実権は李カク・郭汜が握り、献帝は傀儡とされていきます。反董卓連合軍も解散し、元の所領へと戻ったため、献帝を守るものは出現しませんでした。参謀の賈クは当初、人事を担当し、これまで不当な扱いを受けてきた有能な人材を要職に就けるなど、李カク・郭汜でも簡単に手が出せない仕事をこなしていきます。
しかし、賈クが親の介護で都を離れると、次第に李カクと郭汜は董卓のような暴政を尽くし、人心が離れていき、そのため、中央の政治は混乱を極めました。しかも、両者が次第に争い、権力闘争が勃発してしまいます。献帝は力こそないものの、世間への影響力は抜群にあり、どちらに付くかということで献帝は権力闘争に巻き込まれていきました。
宮廷も混沌としていた折、賈クが復帰して李カクと郭汜を和解させます。その機を狙い、董承ら献帝の側近たちが洛陽へと帰参する段取りをつけています。献帝一行は洛陽を目指しますが、心変わりをした郭汜が献帝奪還を目論見、道中では戦闘が勃発していきます。
わずかな供を引き連れて洛陽に到着
■ わずかな供を引き連れて洛陽に到着
わずかな供を引き連れて洛陽に到着
献帝を狙う軍勢はさらに増え、これまで従っていた勢力も参戦し、献帝に付き添っていた官職の人材も討ち取られていきます。献帝は自分の命が狙われていることに、常に恐怖を感じながら逃げていたことでしょう。十常侍や董卓、李カク・郭汜らによって、残虐な暴政を目の当たりにしてきた献帝でしたが、これ以上自分の為に人が死んでいくのは耐えられないことだったに違いありません。
献帝一行は水路を使って逃げ続け、敵軍を振り切り、わずか数十人という供を伴いながらかろうじて逃げ切りました。何とか洛陽に到着した献帝ですが、そこは董卓が焼き払ったおかげで宮殿はボロボロで焼け野原とかしていました。何とか修繕していきますが、今度は追従してきた供の中で仲間割れが生じ、安住とはいきませんでした。
献帝は今後、曹操の登場によって窮地を救われていますが、それは後漢王朝の衰退を大きくしていくものとなっていきます。