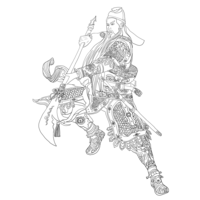呂布(奉先)董卓(仲穎)の養子になる
■ 呂布(奉先)董卓(仲穎)の養子になる
呂布(奉先)董卓(仲穎)の養子になる
元々呂布(奉先)と董卓(仲穎)は敵対していました。董卓(仲穎)は自分の野望(帝を交代させ自分が帝を操ろうとしていた)を叶えようとしていましたが、丁原がそれを反対していました。董卓(仲穎)にとって丁原自体は大したことない相手だったのですが、その養子であった呂布(奉先)の強さに手を焼いていました。それでは「呂布(奉先)を仲間にしてしまおう」というのが董卓(仲穎)陣営の考えでした。
呂布(奉先)に赤兎馬を与え董卓(仲穎)陣営に入るとこんなメリットがあると伝えました。すると呂布(奉先)はあっさりと董卓(仲穎)の養子となり彼のボディーガードとなってしまったのです。
その後最強・呂布(奉先)手に入れた董卓(仲穎)の勢いは一層増し、誰も董卓(仲穎)を抑えることができなくなりました。しかし董卓(仲穎)は最終的にこの呂布(奉先)に殺されてしあいます。
そのため長い目で見たら呂布(奉先)を養子にしたのは失敗だったといえるでしょう。
関平、関羽(雲長)の養子になる
■ 関平、関羽(雲長)の養子になる
関平、関羽(雲長)の養子になる
三国志では多くの者が誰かの養子になりますが、私の知る限り一番あっさり養子となったのが関平です。元々は関定という男の息子でしたが、関羽(雲長)がたまたま関定の家に立ち寄った際に初めて二人は会いました。
関定には自分の元にいるよりも関羽(雲長)についていった方が、関平が大成するという想いがありました。そのため関羽(雲長)に「うちのせがれを養子にしてください」と直談判しました。(同姓ということも一つの要素ではありました)
関羽(雲長)は
1、 関平の体が立派だった
2、 関平の立ち振る舞いがよかった
3、 劉備(玄徳)から「お前には子どもがいないから養子にもらったらどうだ?」と言われた
これらの要因が重なり「あい、わかった」とすぐに養子にしてしまったのです。
そしてこの、関平十分すぎるほどの活躍をし、蜀にとってなければいけない武将になるまで成長しました。
劉封、劉備(玄徳)の養子になる
■ 劉封、劉備(玄徳)の養子になる
劉封、劉備(玄徳)の養子になる
劉備(玄徳)には劉禅(公嗣)という息子がいました。しかし、劉封を一目見るなりその体格を気に入り養子にしたいと思ったのです。
元々劉封には両親がおらず、おじである劉泌の世話になっていました。劉備(玄徳)は劉泌と話して「是非譲ってくれないか?」といってあっさりと養子にしてしまったのです。
しかし劉備(玄徳)には劉禅(公嗣)がいたため関羽(雲長)はこの養子縁組に関しては反対でした。
劉封はこのことを根に持っていました。関羽(雲長)が呉軍から攻め込まれていたため劉封に対して援軍の要請をしましたが、劉封は最終的に援軍を出すことはしませんでした。
劉封の援軍が来なかったため関羽(雲長)は敵兵に囲まれ死んでしまいました。これを知った劉備(玄徳)は激昂し、劉封を処刑してしまうのです。しかし処刑した後に劉封が亡命しなかったという事実を知り処刑したことを後悔してしまうのです。
諸葛喬(伯松)、諸葛亮(孔明)の養子になる
■ 諸葛喬(伯松)、諸葛亮(孔明)の養子になる
諸葛喬(伯松)、諸葛亮(孔明)の養子になる
三国志において「諸葛」の文字をよく見ることでしょう。それもそのはず、兄弟にして違う国で働いていて、さらには優秀なものが多かったためです。そのため「諸葛」一族に対しては話がごちゃごちゃになってしまうというケースが少なくありません。
そして諸葛一族を一番厄介にしているといっても過言ではないのが諸葛喬(伯松)の存在です。
諸葛喬(伯松)は元々、孫権(仲謀)に仕える諸葛瑾の次男で生まれは呉でした。しかし父の勧めで当時まだ子供がいなかった諸葛亮(孔明)の養子になってしまったのです。その後、諸葛亮(孔明)には諸葛瞻(思遠)という息子が生まれました。それでも諸葛亮(孔明)は変わらず寵愛しました。
ところが彼は才能を発揮する前に漢中で病死してしまいました。ちなみに諸葛喬(伯松)の息子である諸葛攀は呉に仕えるなど最初から最後までこの一族は三国志に携わりました。
とはいえこの一族を見ていると「国よりも一族のつながりの方が強い」と実感させられるため「武将と言えど国にがちがちに縛られていない」という様子が伺えます。
夏侯楙(子林)、夏侯惇(元譲)の養子になる
■ 夏侯楙(子林)、夏侯惇(元譲)の養子になる
夏侯楙(子林)、夏侯惇(元譲)の養子になる
魏で曹一族を支えた重鎮として忘れてはならないのが夏侯一族である。特に夏侯惇(元譲)、夏侯淵(妙才)と言ったら従弟である曹操(孟徳)の右腕、左腕と言っても過言ではない将軍で、彼らがいなかったら曹操(孟徳)があそこまで名を馳せていたことはなかったのではないだろうか。
そしてそんな二人を凌ぐ境遇に置かれたのが夏侯楙(子林)です。夏侯楙(子林)は夏侯淵(妙才)の息子でありながら夏侯惇(元譲)の息子となったのです。まさに夏侯一族を牛耳る体制は整ったといったところでしょうか。さらにそれだけでなく妻は曹操(孟徳)の娘というのだからもうガチガチに周りを固められた将軍と言っても過言ではありません。
そんな夏侯楙(子林)ですが、生まれつき武に関しては全くダメでした。その反面金儲けと女が好きだったためかなり使えない将軍でした。多くの娼婦を囲っていたため妻と仲が悪くなった。戦に出れば連戦連敗を喫した。親の七光りというがまさに親のコネを使いまくった挙句他国に逃げ込み、最終的には魏に戻らなかった。優秀ぞろいの夏侯一族にあって足を引っ張りまくった人物もいるということだけ覚えていただけたらと思います。
ちなみにこの夏侯楙(子林)、三国志演義では字が子休という設定で、何の能力もない使えない武将として描かれています。
「夏侯一族の将軍を討ち取った」と言ったら後世に語り継がれるものでしょうが夏侯楙(子林)を討ち取ったところで何の価値も見いだせられなかったことでしょう。
まとめ
■ まとめ
まとめ
養子になった将軍たちをまとめてみましたがいかがだったでしょうか。今の時代に養子となるといったらとてつもなく大きいことのように思えますが、当時ではそこまで重いことでないことが分かったのではないでしょうか。
戦略的に養子にする場合もあれば子供がいないから世継ぎのために養子になる場合もあります。さらには「気に入ったから」という単純な理由まで存在してしまうのです。多くは引き取る側が「こいつを養子にしたい」と思うケースが多いのですが、夏侯楙(子林)の例もあるので一概にそうは言えないのでしょう。