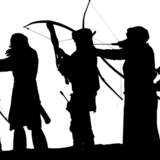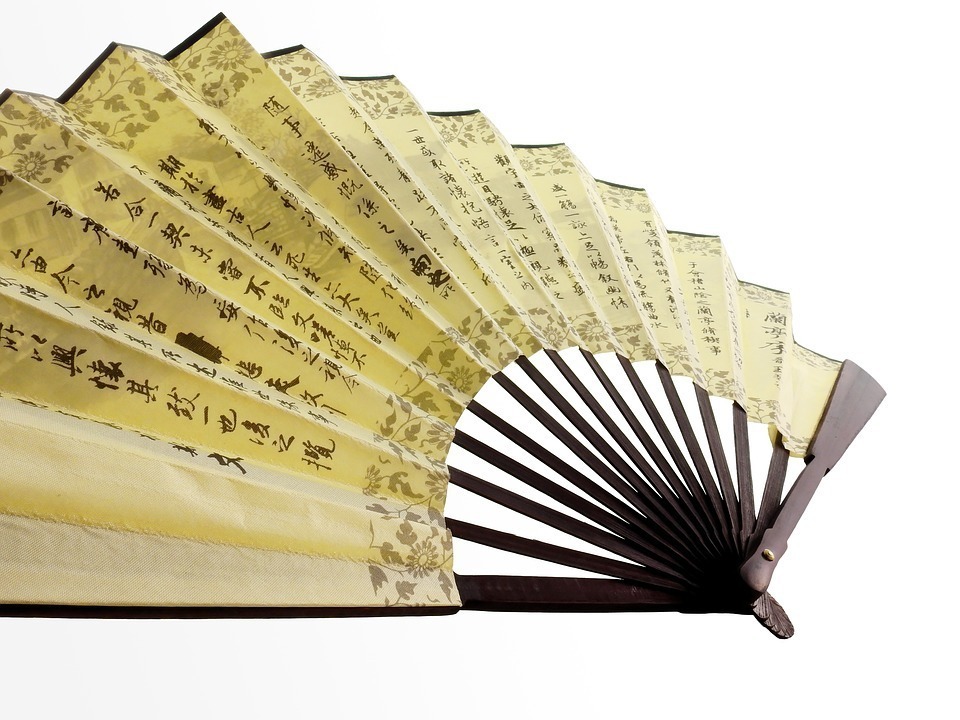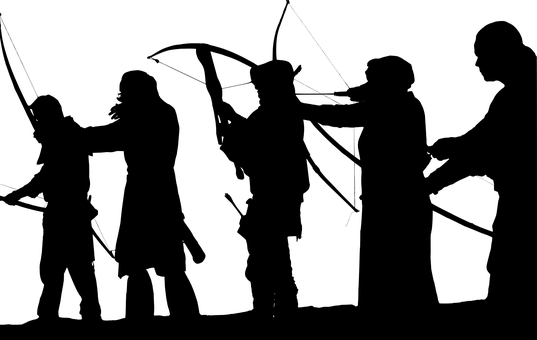マイナーだけどぜひとも知ってほしい連弩
■ マイナーだけどぜひとも知ってほしい連弩
マイナーだけどぜひとも知ってほしい連弩
三国志演義では関羽(雲長)の愛刀である青龍偃月刀や張飛(翼徳)の愛刀である蛇矛(じゃぼう)など、世の人々を魅了してきた武器が登場します。そこまで有名ではないものの、三国志演義の話中で諸葛亮(孔明)が発明した当時は画期的な新兵器だった幻の連弩を紹介していきます。
元祖マシンガンと呼べる連弩
■ 元祖マシンガンと呼べる連弩
元祖マシンガンと呼べる連弩
遠距離から目標を攻撃することを可能とした弩は古来より狩りや戦争でよく用いられてきました。弓を扱うためには相当な訓練期間が必要で、名手と呼ばれる達人であっても標的を外すことはしばしば。さらに弓を作る過程で、それを引く強さは個人差があり大量生産するには不向きな武器でした。それを解消したのが弩という武器で、ボウガンのような代物です。一定以上の力があればだれでも矢をつがえることができるし、トリガー部分の装置を操作するだけなので訓練をちゃんと受けていなくても扱うことができます。まさに平時は農業を営み、戦のあるときにだけ参加していた雑兵たちに持たせるには持ってこいの武器でした。しかし、その弩にもひとつだけ欠点がありました。矢をつがえてから狙いを定めて発射するまでの動作には一定の時間が必要で、修練を重ねていないと連発射撃をすることはできませんでした。この欠点を補うために諸葛亮(孔明)は一度に複数の矢を放つことのできる連発式の弩を自ら発明・製造しました。このように連射式の弩のことを連弩といって通常の弩とは区別されています。
連弩の設計思想が誕生したのは紀元前5世紀
■ 連弩の設計思想が誕生したのは紀元前5世紀
連弩の設計思想が誕生したのは紀元前5世紀
連弩の設計思想は紀元前5世紀ごろには誕生していた考えられています。紀元前5世紀といえば中国に180の大小の国々が乱立していた春秋戦国時代のころで、各国で盛んに武器の発明やより効率的な用兵の研究がされていた時代に該当します。紀元前3世紀には初めて実戦に投入された形跡が見られていて、その連弩は非常に大型の兵器でした。その連弩は複数名の兵士によって運用されるサイズで、持ち運ぶことはせず城門や拠点に設置して用いる兵器でした。その後連弩はとても便利な兵器だったのでなんとかして移動できるように改良されました。連弩車と呼ばれる戦車(馬車)に設置して用いる兵器でまだまだ兵士に持たせて使わせることのできないサイズでした。
諸葛亮(孔明)考案 幻の元戎
■ 諸葛亮(孔明)考案 幻の元戎
諸葛亮(孔明)考案 幻の元戎
先ほど紹介した初期の連弩の設計を参考にして、個人で携帯して用いることのできる連弩を開発したのが、三国史で2代目の主役格となる諸葛亮(孔明)です。諸葛亮(孔明)が開発した連弩は「元戎(げんじゅう)」と命名されました。元戎(げんじゅう)の外見や仕組みに関する詳しい情報は残されておらず、実際にどのような武器であったのかは不明です。わかっているのは、約20センチほどの短いやを10本まで一度に発射することができ、当時は画期的な新兵器だったという情報だけです。
諸葛亮(孔明)はこの元戎(げんじゅう)を大量生産して連弩部隊を編成しました。連弩平の単一兵科による本格的な部隊編成を考案したのは史実上諸葛亮(孔明)が初めてだと言われています。
明の時代になって再現された元戎
■ 明の時代になって再現された元戎
明の時代になって再現された元戎
諸葛亮(孔明)が発明した元戎(げんじゅう)は、諸葛亮(孔明)の死後約1200年を経た中世に復元、戦線投入されました。元戎(げんじゅう)はその性能に謎の多い半ば伝説的な連弩ですが、14~17世紀にかけて存続した明王朝で、個人が携帯して運用する元戎(げんじゅう)に近いコンセプトの連弩が開発されました。この連弩はかつて元戎(げんじゅう)を開発した諸葛亮(孔明)にあやかって諸葛弩と名付けられました。諸葛弩は長さ80センチほどの木製の連弩で、上部には矢を収納するための弾倉が取りつけられていました。その弾倉は取り外すことが可能で、通常の弩としても利用することができました。そしてこの弾倉に入れる矢は木と竹で作られたもので長さは25センチ。弾倉には一度に10本までの矢を収納することができました。
諸葛弩は本隊に取りつけられたレバーを引くと弦が引き延ばされて矢が装填されました。本体の株には引き金が装備されていて、その引き金を引くと弦が元の戻り、その反発力によって矢が放たれるという仕組みでした。簡単な操作で矢を連射できることが強みでしたが、小型化を追求したため翼(弦を張る弓の部分)が小さくなり、射程と威力が弱いのが難点でした。
連弩は勝敗を決める武器へと成長した
■ 連弩は勝敗を決める武器へと成長した
連弩は勝敗を決める武器へと成長した
諸葛弩のほかにも、明代には設置型の連弩が開発されました。この連弩は同時に複数の矢を発射する多発式の連弩で、神臂床子連城(しんぴしょうしれんじょう)と呼ばれていました。神臂床子連城(しんぴしょうしれんじょう)は長い射程を確保することを目的に作られた連弩だったので、サイズが大きく、専用の土台に固定して運用される兵器でした。矢を装填してから発射するまでの動作はすべて一人で行うことができたのですが、弩を移動させることは難しく、計画的な運用が求められる武器でした。
今はみることができない連弩だが…
■ 今はみることができない連弩だが…
今はみることができない連弩だが…
残念ながら今は連弩を実際に使っている様子や実用できる連弩を見ることはできません。しかし、弩は今も根強く残っています。その背景にはクジラの研究をするために捕鯨の道具として長く研究開発がされていた経緯や銃の発明によりどんどん弓が戦場から姿を消していったのに対して、武器の使用に求められる習熟度が低く、銃とほとんど使用方法が変わらないことからごく最近まで現用の武器として使用されていたからです。大規模な戦争では第一次世界大戦で使用された実例があります。しかも本来の使用用途である矢を発射する目的ではなく手榴弾などの投擲兵器を飛ばすためのツールとして使われていたようです。また、発射時の音が小さいということで隠密行動を行うスパイが銃の消音装置が高性能になるまで使用していました。なんと1970年代まで特殊作戦部隊は弩を隠密作戦で利用していました。さらに弩は英語表記のクロスボウという名で競技化されています。アーチェリーと同じく、色のついた的に矢を発射して中心に近いほうから得点が高くなっています。
まとめ
■ まとめ
まとめ
諸葛亮(孔明)の発明した元戎(げんじゅう)の設計書は現存していません。そのため、諸葛弩はあくまで名前を使用しているだけで元戎(げんじゅう)とはまったくの別物です。おそらく諸葛亮(孔明)は精錬をする匠と同じように自分の死後に魏や呉に元戎(げんじゅう)の製造方法が流出することを恐れてあえて設計書や手がかりとなる資料を残さなかったのではないかと思います。