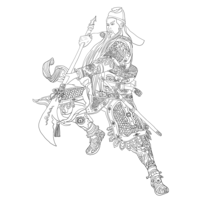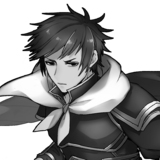第五位:馬超 vs 許褚
■ 第五位:馬超 vs 許褚
第五位:馬超 vs 許褚
では、まず第五位からいってみましょう。第五位は、馬超 vs 許褚です。
演技では父馬騰を殺された馬超が復讐の念に燃えて、韓遂と組んで曹操に対して兵を起こしたとありますが、正史では全く逆です。馬超が韓遂と組んで反乱を起こしたので、都にいた馬騰が処刑されました。しかも、馬超は反乱を起こす時韓遂に、
「私は今の父を捨て、あなたを父とします。一緒に曹操を倒して天下を取りましょう」
と持ちかけます。うーん、演義で馬超ファンになった方には知りたくない情報だったかもしれませんね。で、兵を起こした馬超の軍勢が猛烈な勢いなのは正史と演技共にあります。曹操に対して、色々と迫りますが、許褚が身を挺して曹操を守ります。そして、許褚が馬超に一騎打ちを申し込み、それを馬超が受け立つ・・・というのは演義のみの話です。実際には曹操が馬超と対面して話をすることになり、曹操は許褚だけを従者として連れて行きます。馬超はその場で曹操を殺そうと考えていました。どうも史実の馬超はだいぶ演義とはイメージが違う印象です。しかし許褚の武勇の噂を知っていたので、手が出せず終わったということです。
演義で白熱のバトルを繰り広げられますが、正史では馬超と許褚の一騎打ちのシーンは存在しません。
最強の曹操軍に対して猛烈な攻めを見せた馬超。その馬超ですら二の足を踏まざるを得なくなる許褚の武勇。その2つが合わさって演義にあるこの二人の一騎打ちのシーンが生まれたのではないでしょうか。
第四位:関羽 vs 龐徳
■ 第四位:関羽 vs 龐徳
第四位:関羽 vs 龐徳
第四位は陸戦/水戦の限りを尽くした決戦、関羽 vs 龐徳です。
演義では息子関平をあしらわれた関羽が龐徳に一騎打ちを挑み、百合以上打ち合っても決着がつかなかったという迫力のある場面です。残念ながらこれは演義オリジナルの場面のようで、正史には関羽と龐徳が直接打ち合ったという記載はありません。正史と演義で一致するのは
・関羽軍と于禁/龐徳軍が激突
・大雨により魏(于禁/龐徳)軍が水没
・関羽に降ろうとした配下を龐徳が惨殺
・関羽に囚われても降伏せず処刑される
などです。日本でも備中高松城の戦いなどのように、古来より水攻めというのは相手の戦意を奪い、降伏させるには有効な作戦です。上司である于禁が降伏し、そのことを曹操に
「30年以上私に仕えた于禁が龐徳に及ばないとは」
と嘆かれたといいますが、于禁がだらしないというより、龐徳の戦意が凄すぎるのだと思います。
この凄まじいまでの戦意と絶体絶命でも降伏しない忠節を後世の人がたたえて、関羽との一騎打ちという名シーンに加えられたのではないでしょうか。
第三位:黄忠 vs 夏侯淵
■ 第三位:黄忠 vs 夏侯淵
第三位:黄忠 vs 夏侯淵
第三位に輝いたのは定軍山で激突した、黄忠 vs 夏侯淵です。
演義では黄忠、夏侯淵は共に弓矢の名手として描かれている武将ですね。黄忠と軍師法正が定軍山を奪取に来て、それを夏侯淵が迎え撃ちます。そして、黄忠が夏侯淵を一騎打ちで打ち取り、定軍山を奪取というのは、演義での話。正史では夏侯淵が戦死したという記載はされておりません。ひょっとしたら黄忠が直接叩き切ったのかもしれませんし、名もない雑兵の手によって討たれたのかもしれません。あるいは流れ屋や落馬などで命を落としたかもしれません。
一騎打ちが実際にあったかどうかは不明ですが、状況としては、夏侯淵が張郃らを率いて、漢中の定軍山を守っていたことや法正が軍師として出陣していたことはほぼ同じです。そして、劉備軍の武将として黄忠最大の見せ場ということで第三位です。
第二位:関羽 vs 顔良
■ 第二位:関羽 vs 顔良
第二位:関羽 vs 顔良
第二位は三国志前半部分でのクライマックスとも言うべき関羽 vs 顔良です。
200年の白馬の戦いで袁紹軍の猛将顔良の前に大将が立て続けに討ち取られ、徐晃までも敗走。最後の切り札として客将関羽が出向いたところ、顔良を一撃で切り落とした!と、関羽ファンならずとも大いに盛り上がるところです。この白馬の戦い、正史にも記載されております。その中で、
「関羽は顔良を刺殺し、その首を持って帰った」
と書かれています。ちょっとだけ惜しいのは、顔良が演義のように圧倒的強さを発揮していたのではなく、曹操軍の計略に引っかかり、包囲されているところを関羽に刺し殺されているところです。一騎打ちというよりはとどめを刺された感じになってしまったようです。
演義では「華雄」「紀霊」「顔良」「文醜」「五関の六将」「蔡陽」「黄忠」「龐徳」と数多くの猛将と一騎打ちを繰り広げてきた関羽ですが、正史に載っているのは残念ながら「顔良」戦のみ。ですが、関羽が後世まで猛将として伝えられ、神様にまでなってしまった一戦ということで第二位にランクインです。
第一位:孫策 vs 太史慈
■ 第一位:孫策 vs 太史慈
第一位:孫策 vs 太史慈
栄えある第一位に輝いたのは孫策 vs 太史慈でした。
では、何故この一騎打ちが第一位なのでしょうか?実はこの勝負、正史である三国志呉書に記載されているのです。大まかな内容としては、
「劉繇軍を攻めてきた孫策軍の偵察に太史慈が出た。たまたま孫策を見つけ一騎打ちを挑んだところ、孫策も応じて打ち合った」
とあります。正史に大物同士の一騎打ちが記載されているのは非常に珍しいです。この一騎打ちに決着はつきませんでしたが、それだけでも価値のある一騎打ちです。もしも、近い将来にタイムマシンが開発されたら、この一騎打ちだけは見ることが出来るのです。そう考えると見に行ってみたくなりますね。
まとめ
■ まとめ
まとめ
いかがでしたでしょうか。白熱の一騎打ち五番勝負は楽しく読んでいただけましたか。
実際、正史には一騎打ちはほとんど登場していません。大軍を預かる武将が自ら先頭にたってあっさり死んでしまう訳にはいきませんから、当然のことでしょう。どんなにすごい勝負であっても何百回も打ち合っているのを周りの兵士たちが黙って見ているわけでもありません。何しろ自分たちの大将に勝ってもらわないと、命すら危ないのですから。
ですが、男としてはやはり一人で先頭に立って、相手の大将を打ち破って合戦に勝つという夢を持っていた人間は多かったと思います。そういった武将たちの思いが創作である演義に数多く登場する一騎打ちに反映されているのではないでしょうか。