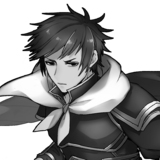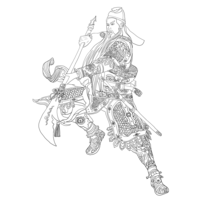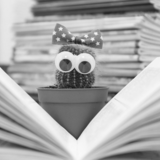夏侯惇(元譲)VS姜維(伯約)
■ 夏侯惇(元譲)VS姜維(伯約)
夏侯惇(元譲)VS姜維(伯約)
この二人はともに「熱すぎる!」といっても過言ではないのではないでしょうか。夏侯惇(元譲)は目に矢が刺さったらその矢を目ごと引っこ抜いて、「親からもらった体だから」といって目玉を食べてしまったというエピソードがあります。さらに出世しても金品を周りに分け与え、私財をほとんど持たなかったという無欲さもありました。
一方姜維(伯約)は元々魏兵でしたが、蜀に降伏してからというもの、周りが魏に対して降伏しても自分は最後まで抗うというスタンスを持ち続けていました。諸葛(孔明)の後継者的存在の姜維(伯約)は、暴走とも捉えられかねないほど何度も北伐を繰り返しました。成功はしませんでしたが北伐に対しての熱い思いだけは誰にも負けていません。
こんな二人が戦うとあれば目を離すことはできないでしょう。二人とも三国志の中でトップレベルの武力を誇り、一人で戦局を変えるほどの影響力を持っていました。夏侯惇(元譲)は数々の猛者を葬った武将ですが、姜維(伯約)の執念と知略はその上を行きます。そのため戦うのが叶わないほどの年齢差ですが、もし戦ったとしたら姜維(伯約)が勝つでしょう。
黄蓋(公覆)VS黄忠(漢升)
■ 黄蓋(公覆)VS黄忠(漢升)
黄蓋(公覆)VS黄忠(漢升)
どちらも「黄」がつくこの二人。共通して言えるのは年齢不詳ではあるものの、恐らく「老人だった」という漠然としたイメージを持たれているところにあります。
黄蓋(公覆)は赤壁の戦いの際の最大功労者の一人といっても過言ではない働きを見せました。戦闘力もありますが、なんといっても忠誠心と策略は彼の右に出るものはいません。バランスもとれている頼りになる将軍です。
一方黄忠(漢升)は老人ながらに蜀の五虎将軍を任されるほどの力の持ち主。さらに曹操(孟徳)の懐刀的存在である夏侯淵(妙才)を倒してしまうなど、戦闘力は折り紙付きです。
この二人が一騎打ちをしたとしたら老兵達は盛り上がってしまうこと間違いなしでしょう。
戦闘力で言ったら圧倒的に黄忠(漢升)が勝るものの、なりふり構わずといった戦術を立てる黄蓋(公覆)がボロボロになりながらも最終的に勝ちます。
呂蒙(子明)VS甘寧(興覇)
■ 呂蒙(子明)VS甘寧(興覇)
呂蒙(子明)VS甘寧(興覇)
どちらも呉の将軍でさらに呂蒙(子明)は甘寧(興覇)の兄貴的存在であるため、(甘寧(興覇)を登用する際に周瑜(公瑾)と共に君主である孫権(仲謀)に推薦しているくらいです)二人のバトルは起こりえませんが、実際戦ったら面白いものがあると思います。
二人ともいわば街の不良上がりのようなもので、今でいう暴走族の総長を務めていました。力も強く血気盛んでどうしようもない二人のバトルは一歩も引かないことが予想されます。
単純な力やヤバさでいえば甘寧(興覇)の方が上の気がします。しかし一方で呂蒙(子明)は呉のリーダー的存在となった後、あらゆる才能が開花したように見受けられます。そのため知力に勝る呂蒙(子明)が紙一重の差でこの対決を制すことでしょう。
この二人のバトルを目にしたらえげつないものが見られるのではないかという気になってしまいますね。
関羽(雲長)VS張飛(翼徳)
■ 関羽(雲長)VS張飛(翼徳)
関羽(雲長)VS張飛(翼徳)
多くの三国志ファンが抱いている疑問の一つに「結局のところ関羽(雲長)と張飛(翼徳)はどっちが強いの?」という疑問があるのではないでしょうか。
実際に一騎打ちの数では関羽(雲長)の方が多く、しかもかなり腕の立つ敵将をことごとく葬っています。まさに困ったときの関羽(雲長)といったところではないでしょうか。
一方張飛(翼徳)も度々曹操軍の猛者たちを退けています。
関羽(雲長)が「弟分の張飛(翼徳)の方が俺より強い」といったため「そうなのかも?」という認識をさせられていますが、定かではありません。
ただ単に腕相撲をさせて「どっちの力が上か?」という勝負であれば張飛(翼徳)に分があるかもしれませんが、実際武器を持たせて戦わせたら関羽(雲長)の方が強いのではないかという印象があります。さらに関羽(雲長)には赤兎馬という最強の相棒がいるので、関羽(雲長)の勝利です。
張遼(文遠)VS孫策(伯符)
■ 張遼(文遠)VS孫策(伯符)
張遼(文遠)VS孫策(伯符)
呉にとって「遼来遼来」と口にしてしまうほど恐れられている張遼(文遠)。彼がいなかったら最終的な三国志の覇者は孫権(仲謀)になっていたかもしれないというくらい、三国志に影響を及ぼしている人物だと思っています。まさに無敵で、「こいつを倒すにはどうしたらいいんだ」という言葉しか口から出てこないのではないでしょうか。
一方破天荒ぶりでいえば右に出るものがいない孫策(伯符)。小覇王の異名を持っていて、自分の立場というものを考えず、三国志において最強クラスの太史慈(子義)と一騎打ちしてしまうのです。自信の表れなのか、はたまた何も考えていないのか。部下泣かせの君主ですが、彼ほど見ていてすがすがしい気持ちにさせてくれる人物はいないでしょう。
「平地でばったり二人が合ってバトル開始」というシチュエーションであれば孫策(伯符)が勝ちます。しかし孫策(伯符)が攻めに出て、城を落としたいから張遼(文遠)に「一騎打ちをしてくれ」といった場合張遼(文遠)が勝つのではないかと思っています。
これはイメージ的な問題かもしれませんが、守るものがある時の張遼(文遠)は最強です。
周瑜(公瑾)VS曹仁(子考)
■ 周瑜(公瑾)VS曹仁(子考)
周瑜(公瑾)VS曹仁(子考)
天才で諸葛(孔明)のライバルとして持ち上げられることの多い周瑜(公瑾)ですが、実は戦闘力もなかなか高いものがあります。軍師のため一騎打ちということはありませんが、実際一騎打ちをさせてみたらほとんど負けない気がします。
一方曹操(孟徳)から絶大の信頼を得ている曹仁(子考)もなかなかの腕前です。若いころから弓術と馬術に優れていてさらに力もありました。人望も厚く、統率力も高いものがありました。
この二人が戦ったら「かなりいいものが見られるのではないか」という想いがあります。
周瑜(公瑾)を亡くしたら呉は再建不能というくらい大打撃を受けてしまうことでしょう。一方曹仁(子考)がいなくなったら魏のまとまりは一気に崩壊してしまう可能性もあります。
デメリットがありすぎるこの一騎打ちは行われないでしょうが、戦ったら周瑜(公瑾)が勝ってしまうのでしょう。
まとめ
■ まとめ
まとめ
「架空一騎打ち」いかがだったでしょうか。三国志を楽しむにおいて自分独自の軍を作ってみたり、将軍同士を戦わせたりというのは面白いものです。答えはありませんが、「二人が戦ったらどちらが勝つのだろう」と想像することで、巡り巡ってより三国志の知識を広められることでしょう。