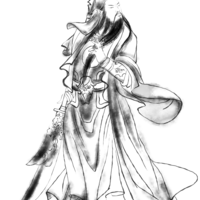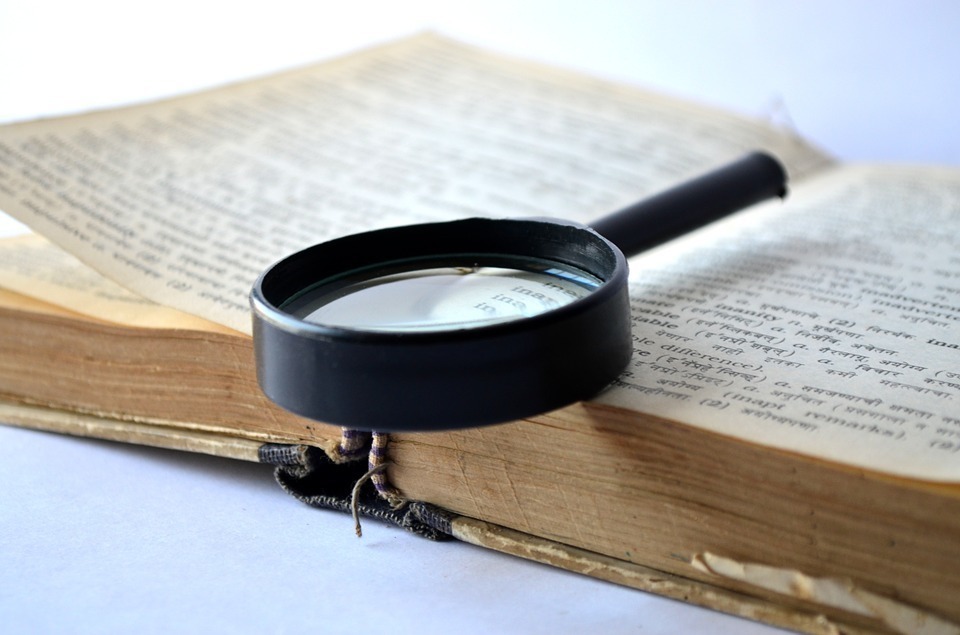日本の漢詩ブーム
■ 日本の漢詩ブーム
日本の漢詩ブーム
日本で漢詩が一大ブームを引き起こしたのは、都を奈良から京都に遷した9世紀ごろになります。日本と唐の間では遣唐使などによって交流が盛んになっており、晩唐の影響を強く受ける結果となっていました。これが日本の文化では「弘仁・貞観文化」(平安時代前期)にあたります。代表的な人物では、「嵯峨天皇」「最澄」「空海」があげられるでしょう。
この時期は信仰仏教の転換期でもあり、南都の大寺院を政治から切り離して密教が台頭しています。同様にブームになったのが漢詩です。空海は漢詩集として「性霊集」を著していますし、「文鏡秘府論」では漢詩文を評論しています。勅選漢詩集も多く編纂され、「凌雲集」「文華秀麗集」「経国集」などが立て続けに発表されています。教育でも貴族専門の寄宿施設「大学別曹」として「弘文院」「観学院」などが登場しましたが、教育の中でも特に重要視されたのが漢詩や中国史を学ぶ「紀伝道」でした。まさに漢詩が日本の文化の柱となっていたのです。
唐詩の主役・杜甫と李白
■ 唐詩の主役・杜甫と李白
唐詩の主役・杜甫と李白
中国の古典文学といえば「漢詩」です。その古典文学の頂点に立ったのが盛唐の時代の「杜甫」と「李白」になります。嵯峨天皇や空海もその影響を強く受けたことでしょう。6世紀の古墳文化の時期に日本には「漢字」とともに「詩経」が伝来しています。詩経は漢詩の原型です。詩経は四言が主流であり、「詩仙」と呼ばれた李白の漢詩は五言、七言となっています。「詩聖」と呼ばれる杜甫もまた同様です。詩経と漢詩の間には、唐成立以前に変革期が存在するのです。実はそれが三国志の時代になります。
後漢末期の五言ブーム
■ 後漢末期の五言ブーム
後漢末期の五言ブーム
四言から五言に移っていくきっかけは「民意」です。三国志の時代は、今のようにテレビや新聞、インターネットなどの情報網が発達していた文明ではありません。朝廷としても庶民の考えや希望を確認することがなかなか困難だったのです。個人の主張は聞けても、多数派の民意を確認するのは骨の折れる作業になります。そこで採り入れられたのが「楽府」という役所でした。ここでは、庶民の間で流行している歌謡を調べて民意を知り、それを政治に活かそうとしていました。このときに庶民の間に流行していたのが五言だったようです。ですから楽府でまとめられた詩は五言が主流となっています。これを「楽府詩」と呼ぶことになり、後漢末期の文人の多くがこの楽府詩を参考にして詩作したため、いつしか五言が定着していきます。
天才・曹操の登場
■ 天才・曹操の登場
天才・曹操の登場
そしてこの五言の楽府詩に新しい息吹を吹き込み、大成したのが魏の「曹操」です。三国志の主役ともいえる英雄・曹操は、あれだけの激戦を繰り広げながら、詩作にも時間を割いていました。音楽にも精通し(これは呉の英雄・周瑜にも当てはまります)、書道や囲碁も優れていたようです。もちろん兵法の面でも突出しています。文武両道の名将は数多くいますが、曹操ほどその両方を追及した英雄はいないのではないでしょうか。
曹操も袁紹や袁術らと同様にエリートの生まれです。幼いころから充分な教育を受けてこられたことがその基礎となっているのでしょう。しかし、曹操の天才的なところは、「独創性」です。真似ではなく、オリジナルを作り出す才能を持っているものです。民意を表すような普遍的な人間の感慨とは別に、曹操は曹操個人の情感を五言詩で詠んだのです。文学という世界の中で個性の情感を表現したという点において曹操はパイオニア的存在でした。
蒿里行より抜粋
■ 蒿里行より抜粋
蒿里行より抜粋
190年に反董卓連合が結成され、盟主を袁紹に据えて、朝廷を牛耳る董卓に対抗することになりますが、連合の結束力は弱く瓦解してしまいます。日々宴会を楽しみ動こうとしない諸侯にしびれを切らし、曹操は無謀にもわずかな兵で董卓軍に攻め込みますが、大敗を喫しました。このときの曹操の思いを「蒿里行」として詠っています。
「軍合力不斉 躊躇而雁行」
「勢行使人争 嗣還自相戕」
・・・
「白骨露于野 千里無鶏鳴」
「生民百遺一 念之断人腸」
日和見で動こうとしない諸侯たちが内輪もめまでしていることを嘆き、併せて世の中が荒廃し、苦しみもがいている庶民の姿を見ても嘆いています。もしかするとそれに対して何もできない自分の無力さを一番嘆いているのかもしれません。ここでは曹操個人の感慨が如実に詠われています。
曹操に続く文化人たち
■ 曹操に続く文化人たち
曹操に続く文化人たち
この曹操の漢詩に強い影響を受けたのが、曹操の息子たちです。魏の初代皇帝に即位することになる「曹丕」、その弟の「曹植」の詩は、時代を問わず受け継がれていくことになります。さらに曹操が理解を示し、曹丕が高く評価した「建安七子」(阮瑀、孔融、陳琳、王粲、徐幹、応瑒、劉楨)も登場しました。彼らの漢詩は後に盛唐の李白や杜甫にリスペクトされることになります。阮瑀の息子である阮籍もまた個人の内面世界を独特に表現しており、「竹林の七賢」の一人として名を残すことになります。皆、詩作において曹操の遺伝子を受け継いでいるといえます。
まとめ・曹操の偉業を三国志演義は皮肉る
■ まとめ・曹操の偉業を三国志演義は皮肉る
まとめ・曹操の偉業を三国志演義は皮肉る
日本で一大ブームを起こした漢詩はルーツを辿っていくと、三国志の曹操に辿り着くのです。空海と曹操には、時代の垣根を飛び越えて結びつくような共通点があったのかもしれません。まさに曹操の影響力の大きさを物語っていますね。
劉備(玄徳)が主役で、曹操がヒール役となっている「三国志演義」では、そんな曹操の偉業に対してケチをつけています。それが「赤壁の戦い」を前にして銅雀台で曹植が詠んだとされる「登台賦」です。孫策と周瑜の夫人を手に入れて銅雀台で楽しむという内容で、それを諸葛亮から聞かされた周瑜が激高して赤壁の戦いが始まることになっています。実際に曹植の登台賦にはそのようなフレーズは存在しなく、そもそも銅雀台が完成するのが赤壁の戦いの2年後になりますので、詠んだ時期に矛盾が生じてきます。曹操親子の漢詩の才能をねたんだことからねつ造されたフィクションだといえるでしょう。
このような面から見ても、曹操はもっともっと高い評価を受けていい存在なのではないでしょうか。三国志演義の影響を受け過ぎるのは、三国志の世界を歪ませてしまう可能性がありますね。