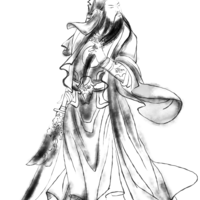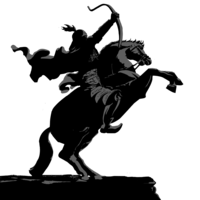恐らく最強の二代目・孫策(伯符)
■ 恐らく最強の二代目・孫策(伯符)
恐らく最強の二代目・孫策(伯符)
江東の虎との異名を持つ孫堅(文台)には二人の優秀な息子がいました。一人は孫策(伯符)でもう一人は孫権(仲謀)です。孫権(仲謀)五十年間という長い間呉を治めた帝王で三国志をちょっとしか知らないという人でもその存在を知っていることだと思います。しかし孫家の初代を孫堅(文台)とした際、二代目は?と聞かれたらやはり孫策(伯符)になります。
孫策(伯符)は孫堅(文台)の長男でしたが早くに亡くなったためすぐにバトンを孫権(仲謀)に渡さなければいけなくなりました。
長年呉をまとめ上げた孫権(仲謀)の手腕は目を見張るものがありますが、周りの評価は明らかに兄の孫策(伯符)の方が上でした。行動力があり、武に優れ小覇王という異名を持っていた天才軍略家です。
歴史に「もし」を使いだしたらキリがありませんが、もし呉を弟の孫権(仲謀)が帝王として君臨し、兄の孫策(伯符)が武将として暴れまわっていたら呉が三国を統一していたかもしれません。というのも、孫策(伯符)なら張遼(文遠)を倒すことが出来たのではないかと思うからです。もし赤壁の戦い後に曹操(猛徳)軍を落とす際の壁となった張遼(文遠)を倒せたらきっと魏は相当やばかったです。
それほど孫策(伯符)は優秀でした。しかし、早死にしてしまい多くの功績を残すことはできませんでした。
文武に優れたバランスのいい二代目
■ 文武に優れたバランスのいい二代目
文武に優れたバランスのいい二代目
親が諸葛亮(孔明)なのでそれと比べたらかわいそうですが、子の諸葛瞻(思遠)もなかなかの英傑でした。
ついに魏が本腰を挙げて蜀に攻め込んできた際、鍾会(士季)と鄧艾(士載)の攻撃を全然止めることが出来ず、あっさり侵略されてしまいました。蜀には二人に対抗できる将軍がいなかったのですが、皇帝である劉禅(公嗣)が泣いて諸葛瞻(思遠)に助けを求めました。
諸葛瞻(思遠)のかく乱作戦により蜀軍が大勝を治めました。結局後におびき出されなくなってしまうことになり、諸葛瞻(思遠)のいなくなった蜀はガタガタになり滅びました。
一時でも父親譲りの奇策を使い勝利を挙げた諸葛瞻(思遠)はその能力を見せつけることが出来ました。また、子供の諸葛尚も優れていたため子供を育てるという面でも優れていたのではないかと思います。
もしかしたら親以上?張苞
■ もしかしたら親以上?張苞
もしかしたら親以上?張苞
張苞は張飛(翼徳)の子供で親譲りの豪傑です。劉備(玄徳)頼もしい張苞の姿に張飛の再来を思わせる武者ぶりに喜んだとしています。この時張飛は部下に暗殺されていました。そして親と同じように関羽(雲長)の子である関興と義兄弟の契りを交わらせました。
ただし関羽(雲長)と張飛(翼徳)が兄弟の関係だったのに対し、張苞の方が関興より一歳年長だったため張苞の方が兄となりました。単騎で老将を次々と助けたためその武力は父に匹敵するとまで言われていました。
さらに父のように酒に酔ってそそうをしでかすということが無かったため、扱いやすさという意味では張飛(翼徳)以上だったでしょう。もし私が諸葛(孔明)の立場だったら張飛(翼徳)より張苞の方がありがたい存在だと思います。
諸葛(孔明)は張苞の存在を大いに喜びましたが、病で早くに死んだことを嘆き、血を吐いて昏倒したほどです。もし張苞が長生きしていたら蜀の運命は大きく変わっていたのは間違いないでしょう。
若い時から有望視された司馬師(子元)
■ 若い時から有望視された司馬師(子元)
若い時から有望視された司馬師(子元)
司馬師(子元)は司馬懿(仲達)の長男で父の司馬懿(仲達)が曹爽を倒すクーデターの計画を成功させた人物です。若いころから将来を有望視されていた逸材で、父の死後大将軍の職につき、国政の実権を握りました。
皇帝の曹芳が司馬一族の力を懸念したため司馬師(子元)の暗殺を謀りましたが、これを鎮圧し、共謀者である李豊らを皆殺しにしてしまいました。
これによりさらに司馬一族の魏での権力はさらに拡大し、曹一族の衰退することとなりました。
また、対国外という意味では呉に侵攻し、諸葛恪(元遜)、姜維(伯約)と言った三国志の晩年を支える各国のエース級の武将ともやり合いました。
司馬師(子元)は司馬懿(仲達)の長男でしたが早死にしてしまったため司馬一族の跡継ぎは司馬照(子上)となりました。
司馬昭(子上)が司馬一族の地位をゆるぎないものにした
■ 司馬昭(子上)が司馬一族の地位をゆるぎないものにした
司馬昭(子上)が司馬一族の地位をゆるぎないものにした
司馬懿(仲達)の二世という観点では司馬師(子元)が真っ先に挙げられますが、後世に影響力を及ぼしたという意味では司馬昭(子上)の方が上だと思います。
司馬昭(子上)は兄である司馬師(子元)の後を継いで軍を掌握し大将軍に就任すると兄同様国政の実権を握りました。そして兄の時と同じように皇帝が身の危険を感じ司馬昭(子上)を討伐しようとしますがこれを退け、違う皇帝を立ててしまいました。
ほとんど兄とやっていることは変わらないように見えますが、司馬昭(子上)はさらにこの後相国(今の日本で言う内閣総理大臣のようなもの)になり事実上の皇帝となりました。
(しかし帝位につくことはなく息子の代で初めて皇帝となる)
結局息子の司馬炎(安世)が皇帝に就任し魏を廃し、晋を建国しますが、司馬昭(子上)のお膳立てがあったからここまで完璧にできたと言えるでしょう。
超サラブレット陸抗(幼節)の評価が凄すぎる
■ 超サラブレット陸抗(幼節)の評価が凄すぎる
超サラブレット陸抗(幼節)の評価が凄すぎる
呉、一のサラブレットと言っても過言ではないのが陸抗(幼節)です。陸抗(幼節)は丞相である父・陸遜(伯言)と小覇王・孫策(伯符)の娘との間にできた子供です。(つまり孫策(伯符)が生きていれば彼の孫にあたります)
陸抗(幼節)の永遠のライバルは晋の将軍羊祜(叔子)です。晋の中核を担う名称で規律を重んじる軍隊を作り上げました。その羊祜(叔子)が陸遜(幼節)がいるから簡単に呉に攻め入ってはいけないと進言するのです。
結局陸抗(幼節)は病死してしまうのですが、彼がいなくなった後呉はボロボロになり、最悪のラストエンペラーとの呼び声高い孫晧(元宗)の我儘をだれも止めることが出来ずに、国は滅亡する羽目になりました。
司馬昭(子上)のように陸抗(幼節)も呉でクーデターを起こしたらもっとましな国ができて、晋と互角に渡り歩くことが出来たかもしれませんね。
まとめ
■ まとめ
まとめ
いかがでしたでしょうか。三国志には残念な二世はいっぱいいますが、優秀な二世も存在しました。(と言っても割合的には3割くらいだと思います)やはりいつの時代も親と比べられるとだめになってしまうのでしょうか。
中には光った二世もいるので上記に挙げた二世を称えてもらえたら嬉しいです。