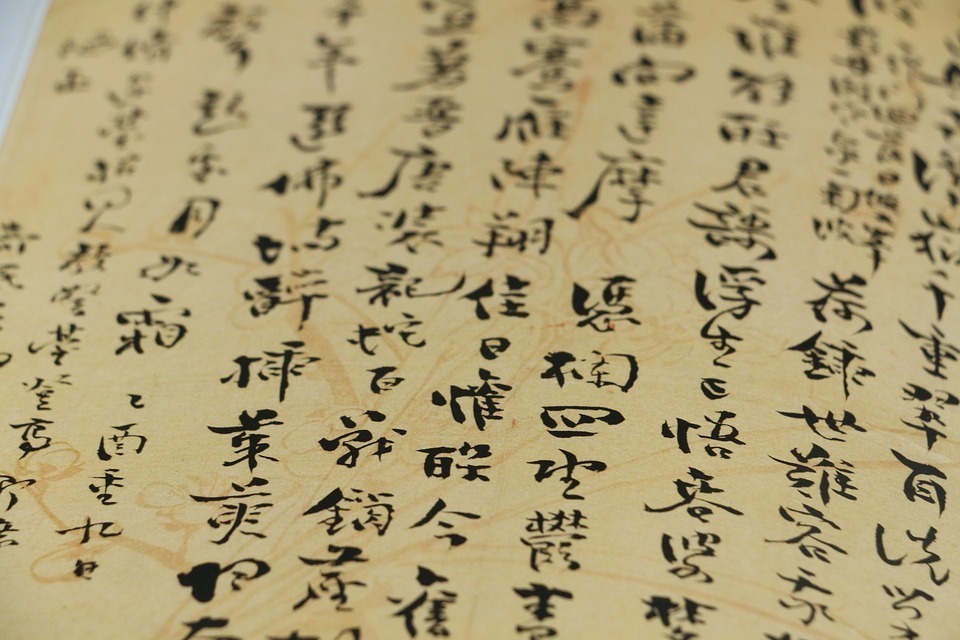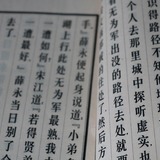魏の軍師たち
■ 魏の軍師たち
魏の軍師たち
三国志では武勇に優れた個性的な武将たちが戦場で大活躍し盛り上げます。呂布、関羽、張飛、馬超、太史慈、張遼、夏侯淵、あげるときりがないほどです。しかし三国志の魅力は武将たちだけではなく、知略を巡らす軍師・参謀の存在も重要な要素を占めています。有名なところでは諸葛亮、そしてその宿敵・司馬懿、呉には天才・周瑜、曹操の腹心・荀彧、曹操を追い詰めた賈詡、劉備を破った陸遜、こちらもあげるときりがありませんね。
特に魏は知恵者が多く集まっています。曹操がそういった能力の高い人材をどんどん起用していったからです。知恵者が惹かれる魅力を曹操が兼ね備えていたともいえます。荀彧は当初は冀州の袁紹のもとを訪れていましたが、その器量に愛想をつかして曹操に仕えました。賈詡は完全に敵対関係でしたが、主君である張繍が曹操に降伏した際に智謀を買われて重用されています。司馬懿はまったく仕官をする気がなかったのですが、曹操に脅される形で参加しました。他にも荀攸、郭嘉、劉曄そして今回の主役である程昱などが魏の軍師としてあげられます。
程昱はもともと別の名だった
■ 程昱はもともと別の名だった
程昱はもともと別の名だった
程昱は本来、程立という名前でした。程立、字は仲徳。兗州東郡の出身です。東郡といえば曹操が太守を務めた場所でもあります。程昱は曹操とは対照的に大柄だったそうです。190cmを超えるほどだったとも伝わっています。もしかすると魏で一番大柄だったのは程昱かもしれません。この体格からすると武将としても活躍できそうですね。実際に兵を率いて敵を撃破した話はいくつか残されています。程昱が程立として名を広めることになったのは黄巾の乱の頃になります。東郡東阿県に住んでいた頃に県が黄巾の襲撃に遭います。県令は脱出し、黄巾に内応する官吏も出る始末でした。程昱は敵情を偵察、隙を見つけ出し、さらに逃げ出した官民を城に呼び戻します。それをまとめあげて敵を打ち破ったのです。こうして程昱は知勇に優れた人物であると評判になりました。
仕官する先は
■ 仕官する先は
仕官する先は
程昱はその後も兗州に住み続けます。兗州刺史である劉岱は、袁紹と公孫瓚の板挟みとなり程昱にアドバイスを求めたと記されています。程昱はこのとき在野の士です。州刺史が今後の進むべき道を尋ねるわけですから、やはり程昱はかなりの評判を集めていたのでしょう。程昱は劉岱から度々仕官を求められていましたがすべて断っています。しかし相談にはしっかり答えたようで、袁紹と公孫瓚の実情を細かく分析し、袁紹の勝利を予想しました。劉岱も程昱の分析を信用しており、その予想に従って袁紹側についています。このとき袁紹は見事に公孫瓚を撃退しました。劉岱としては相談役として傍にいてほしかったのでしょうが、改めて程昱に仕官を求めても断られています。
その後、兗州は黄巾の残党百万ともいわれる大軍の侵攻を受けます。刺史の劉岱は兵を率いて果敢に出撃しますが敗死しました。その跡を継いだのが曹操です。程昱は曹操の招聘には素直に応じています。曹操は程昱の才能を見抜き、県令代行に抜擢しました。
兗州の反乱
■ 兗州の反乱
兗州の反乱
194年、曹操は徐州に侵攻しており兗州を留守にしていました。留守役は曹操と親交の厚い陳留郡太守・張邈や腹心の荀彧、程昱といったメンバーで、ほとんどの武将は徐州に出払っています。ここで好機到来と反乱を起こしたのが呂布や陳宮を呼び込んだ張邈でした。張邈は名士であり、人望も厚かったので兗州のほとんどの郡と県が曹操から離反します。張邈に寝返らなかったのはわずか三つの城しかありませんでした。一つは荀彧と程昱が守っていた甄城です。程昱は残り二つの城を死守すべく動きます。まずは范城に行き、県令を説き伏せました。このとき范の県令は呂布らに妻子を人質に取られていましたが、それを説き伏せたのです。おそらくこの県令の妻子は処刑されたはずです。さらに程昱は自分の故郷である東阿県にも向かいます。程昱は倉亭津を封鎖して城を守り抜きました。もし程昱の活躍がなければこの段階で曹操は滅んでいたかもしれません。曹操は徐州攻略を断念し、即座に兗州に戻りました。そしてこの三つの城を拠点にして呂布に対して反撃を始めるのです。
改名して程昱となる
■ 改名して程昱となる
改名して程昱となる
兗州に帰還した曹操は荀彧から詳細について報告を受けるのですが、その際に程昱の昔話になります。程昱はその昔、泰山に登り、そこで太陽を掲げる夢をよく見たそうです。まさに皇帝を支える役目を示しています。曹操はこの話を聞き、程昱をさらに重用するようになりました。名も日を掲げるという意味から「立」を「昱」に改名させます。ここに至り、初めて「程昱」が誕生したわけです。その後は弱気になった曹操を励ましたり、献帝を迎い入れることを進言したりと活躍しています。性格はかなり強気で、曹操家臣の中でも屈指の不屈の精神を宿した人物です。ただ強情すぎる一面もあり、他の曹操家臣との軋轢もあったようです。
三国志演義の程昱の策
■ 三国志演義の程昱の策
三国志演義の程昱の策
三国志演義ではヒール役の程昱。どちらかというと悪だくみに長けた人物として描かれています。特筆すべきは袁紹との戦いで強力な戦術を駆使したことでしょうか。官渡の戦い後、曹操は再び袁紹と激突します。「倉亭の戦い」です。曹操は程昱の作戦通り夜襲を仕掛けて追撃させ、敵が押し寄せてきたところを埋伏した兵で奇襲しました。10部隊が埋伏されており、それが退却する袁紹に順次襲いかかるのです。30万にも及ぶ大軍がこの「十面埋伏の計」によって1万まで減らされたと記されています。もちろん三国志正史にはそのような作戦は記載されていません。三国志演義ならではの話を盛り上げる脚色ですね。それにしても壮大な伏兵作戦ですね。
まとめ・程昱の逸話
■ まとめ・程昱の逸話
まとめ・程昱の逸話
程昱はその後も的確なアドバイスをして曹操を助け、曹丕を補佐しましたが、三公まで昇格することはありませんでした。理由は定かではありませんが、兗州が蝗害によって食料不足に陥った際に程昱は略奪を行って兵糧を補い、不足分は人肉で補ったという噂が広がったために三公には就けなかったともいわれています。そこが根底にあり、「程昱=非情」というイメージに繋がっていったのかもしれませんね。