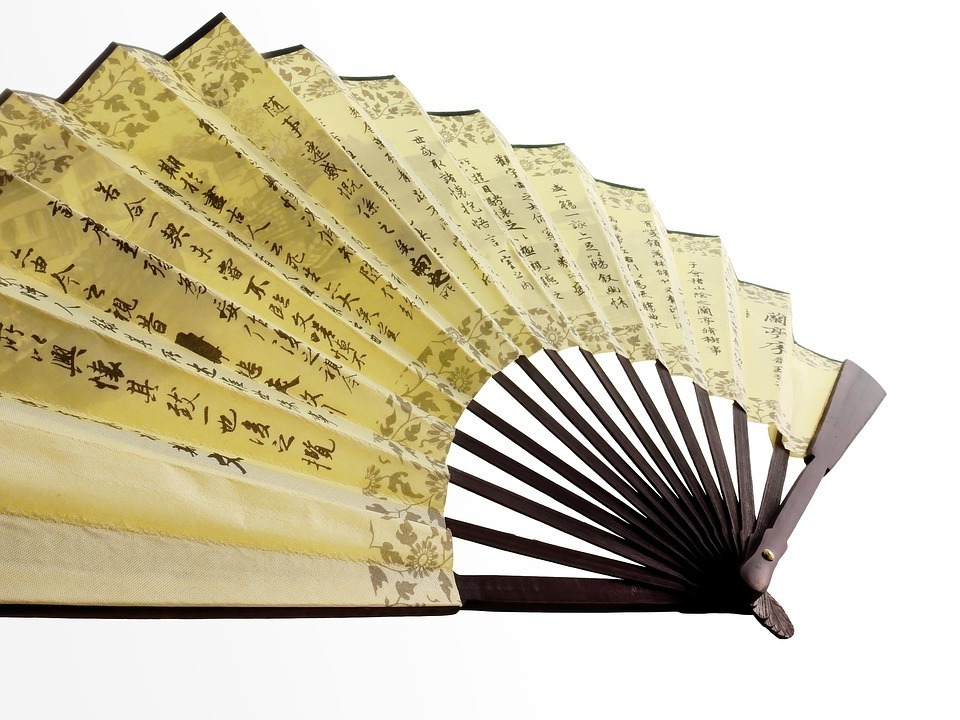三国志と宦官について
■ 三国志と宦官について
三国志と宦官について
中国は古くから宦官という役職があり、三国時代も例外なく宦官として働くものがいました。宦官とは男性が去勢して宮殿の最深部(後宮)で働くことを指しますが、日本人からしたら意味が分からない職種だと言えるでしょう。
しかし、話を理解するとなかなか理にかなったシステムです。なぜ宦官がいるのかというと一言で言うと「後宮内(日本で言う大奥)で男の働き手が必要だが、実際男がいたら困るから」ということです。
なぜ男がいたら困るかというと、「後宮内の女性が妊娠したとしてもそこに帝以外の男がうろうろしていたら実際帝の子供ではなかった」という可能性が少なからずあるからです。
確率にしてみたら0.1%くらいかもしれませんが万が一、帝の子供じゃない者が跡継ぎになって次の帝になったら大変なことです。
つまり慎重に慎重を重ねて宦官という役職があったと言えるでしょう。
「今の時代なら何も去勢までする必要ないでしょ」と鼻で笑いますが、時代が変われば考えは変わるもので合理的と言えば合理的と言えるかもしれませんね。
宦官の仕事について
■ 宦官の仕事について
宦官の仕事について
宦官の仕事の多くは料理や清掃と言った雑用でした。しかし、中には財産の管理をする者、帝の身辺の護衛やお世話をする者、皇子の学問や礼儀作法の教育をする者、帝と宰相の連絡役をする者などがいました。
雑用についてははっきり言って宦官であれば誰でもいいという感じですが、教育係などは帝と仲良くなれるため帝を操るなんて言う輩も出てきました。
(帝がまともに話すことができる男は宦官しかいない為必然的に仲良くなりやすい)
特に宦官は性欲というものを失われているため権力欲が強かったという説もあります。
漢王朝が荒廃した理由の一つとして宦官たちの横行があったのは否めず、宦官という役職が完璧に裏目に出た出来事でした。
宦官のなり手について
■ 宦官のなり手について
宦官のなり手について
宦官のなり手ですが、異民族の捕虜や、異国から送られてきた者などや宮刑を受けた者の他、なんと志願者すらいたといわれています。
(ちなみに宮刑というのは宮廷などで終身に渡り働かせる刑罰という意味なので「宮」という字が用いられています)
今と違って去勢するということは切除部分の治療がままならない為、死亡率も比較的高かったといわれています。
上記でも宦官には権力欲の高い者がいるという記載をしましたが、特に志願者に関しては「命を懸けて宦官になったのだからおいしい思いをしても罰は当たらない」と考えても不思議ではないのかなと思ってしまいます。
いい暮らしをしたいのであれば宦官になるという方法以外で死に物狂いになればいいのにと思ってしまうのは私だけでしょうか。
十常侍について
■ 十常侍について
十常侍について
三国志史上最も有名な宦官、十常侍について紹介します。
三国志演義において十常侍とは張譲、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覧、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝の10名の中常侍を指しますが、後漢書では12名の中常侍の概数をもって十常侍としています。
しかしいずれにせよ張譲、趙忠が権力を持っていたとされています。
霊帝の元で悪業の限りを尽くした十常侍ですが、袁紹(本初)が中心となって彼らを殺し、一人残らず殺されてしまいました。
しかも彼らだけでなく家族も全て皆殺しにされたようです。
去勢を行いさらに権力に取りつかれ最終的には殺されてしまうという最悪な事態に陥った彼らに同情せずにはいられませんね。
もし宦官になったら
■ もし宦官になったら
もし宦官になったら
今でこそ宦官になるというのに理解できないかもしれませんが、仮に三国時代に物騒な兵士がいる中さらに寒空の元ホームレスとして生活しなければいけないという絶体絶命の状況に追いやられたら宦官になりたいというのも理解できなくもないです。
しかも宦官になったら恐らくそれなりの食にありつけ、そこそこの部屋に住まわせてもらえたことでしょう。つまり一般人よりも相当いい暮らしを送ることができたと考えていいでしょう。それを考えると志願者がいたとしても不思議がることはありません。(多くの志願者がいたとされています)
去勢した者にどれほどの性欲が残されるかは分かりませんが、目の前で美女のお世話をするのはどういう心境だったのかというのは聞いてみたいところですね!
宮刑というのは死刑の次に重い刑とされています。そんな悪事を働かせた輩を帝のそばに住まわせていいのかという点は不思議に思ってしまうことの一つです。
「罰を与えたからもう十分」と考えたのかは分かりませんが、現在で言うと殺人を犯したのに去勢したから皇居で天皇陛下のお世話をしている(もしくは天皇陛下のお世話をしている人のお世話をしている)ということではないでしょうか。
ぎょっとする宦官エピソード
■ ぎょっとする宦官エピソード
ぎょっとする宦官エピソード
最後に宦官についてぎょっとするエピソードを紹介します。上記で十常侍は一人残らず殺されてしまったと述べましたが、この際彼らの家族も全て皆殺しにしました。
しかしこの時に髭が無かったため宦官だと間違われて殺されたものも多かったというのです。その数が正確にはどの程度の物か分かりませんが、結構多くの無実の犠牲者が出たことは間違いないでしょう。
そして殺されたのは十常侍及びその家族だけにはとどまりません。
料理や清掃と言った雑用を任されていた宦官も袁紹(本初)、袁術(公路)の宮中乗り込み事件時に殺されていました、その数はなんと2千にも上るとのことです。
余談ですが、袁紹(本初)はともかく、袁術(公路)は親の七光りで生きているような人物として評判が悪い者でした。そんな彼に命がけでなった宦官となった後に殺されたということを考えると「無念」という言葉しか出なかったのではないかという気持ちにさせられてしまいます。
宦官は権力を欲したのかもしれませんが、その罪以上に袁紹(本初)や袁術(公路)が宦官を嫌っていたということが伺えます。
まとめ
■ まとめ
まとめ
日本では考えられない「宦官」だが実は中国以外でも東アジアの地域の歴史では存在していたようです。
去勢しなければいけないものの、宦官になりたいというものは少なからずいて、宦官の多くは権力欲の強い者達でした。
三国志に置いては十常侍という宦官たちが権力を握り、漢王朝を衰退させたといわれています。
袁紹(本初)や袁術(公路)による大規模な「宦官狩り」が行われ、2千人ほどの宦官と共に十常侍も皆殺しにされてしまいました。