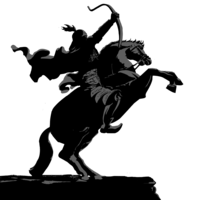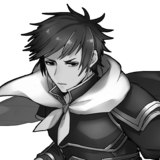蜀攻略にも従軍した名門出の杜預
■ 蜀攻略にも従軍した名門出の杜預
蜀攻略にも従軍した名門出の杜預
杜預の祖父や父は魏に仕えており、杜預は名家の一門出身でした。早くから出世を果たしているかといえば、実はそうではなく、父が権力者である司馬懿(仲達)と仲が悪かったのが原因といわれています。それでも聡明さは評判になっており、司馬懿の次男である司馬昭が跡を継ぐと、妹の婿だった杜預を抜擢していきます
杜預は魏の将軍として活躍していた鄧艾を尊敬しており、魏が大軍で蜀を攻めた263年には杜預も従軍。魏は蜀を降伏させますが、鄧艾が命令違反として逮捕され、鍾会が姜維とともにクーデターを起こしたとき、従軍していた同僚たちが処罰される中、杜預はクーデターに参加しなかった証明をして処罰を免れています。最終的に鄧艾は殺害されたため、杜預の落胆ぶりは相当なものだったといえるでしょう。
朝廷内で疎まれる
■ 朝廷内で疎まれる
朝廷内で疎まれる
杜預は政治に明るく、理論的に自身の意見を主張していきます。しかし、朝廷内には杜預を疎ましく思う輩もおり、官吏の人事制度で新しい制度を述べても採用されず、異民族の対処についても相手の勢いと自軍の装備では春まで進軍を待たなければ、到底勝ち目はないと述べて、遂には逮捕されてしまいます。
先を見通す目で晋の重鎮に出世
■ 先を見通す目で晋の重鎮に出世
先を見通す目で晋の重鎮に出世
杜預は武帝(司馬炎)の叔母を夫人としていたため、処罰されるのは免れます。一方で情勢は杜預の言ったようになり、杜預の先を見通す目が話題になりつつありました。次に匈奴の劉猛が反乱を興すと、杜預は晋軍の支援対策に当たり、塩や穀物の定期輸送で補充を怠らず、農政を安定させて税制も整えていきました。さらに、石鑒は新兵器を開発させるなど、反乱軍を抑えた後も民衆が困らないように処置をしたので、名声は高まっていきました。
ところが、朝廷内での論功行賞で不誠実な対応をされて、口論することになり、貴族でありながらも官位を剥奪されてしまうことになってしまいます。
呉を滅ぼす
■ 呉を滅ぼす
呉を滅ぼす
蜀を滅ばした晋にとって、反乱軍を除くと後は大国の呉を残すのみとなりました。孫権が作り上げた呉は、魏の時代からたびたび戦闘するものの、国境付近を大きく超える決定的な勝利はありませんでした。それだけ呉も国力を有しており、また優秀な武将たちが構えていました。
264年に第4代皇帝に即位した孫皓は、暴君として国が荒れる要因を作りましたが、魏から禅譲したばかりの晋は国力の安定化を図るために、大軍を以って攻め込むことができませんでした。また、呉には軍事的には呉の大都督だった陸遜の息子である陸抗や朱績、丁奉といった有能な将軍たちが健在であり、晋も手出しが簡単ではありませんでした。
羊祜の後任で対呉の将軍として荊州へ
■ 羊祜の後任で対呉の将軍として荊州へ
羊祜の後任で対呉の将軍として荊州へ
そんな中、武帝は何とか呉を滅ぼそうと考えていましたが、晋国内においてその考えをk共有できていたのは武帝の信頼が厚い名将の羊祜や文官として優れた政治力を発揮していた張華、そして杜預のみであったとされています。羊祜は晩年に呉の討伐を願いでますが、朝廷内では却下されてしまい、失意の内に病に倒れてしまいます。羊祜は自身の後任として杜預を推挙しており、278年に羊祜が亡くなると、杜預は対呉の筆頭将軍として荊州に赴任します。
杜預は軍備を増強して精鋭に仕立てあげ、呉の名将張政が隙をついて攻めてきますが、杜預の策略によって大勝しています。張政は暴君の孫皓に殺害されることを恐れ、報告することをためらいます。杜預はその情報を手に入れて、捕えた捕虜を呉の都へ返還しました。驚いた孫皓は張政を罷免し、後任に劉憲を送ります。杜預にとってこの離間策は、一度敗戦を味わった張政が相手だと、要所で懸命に守り抜くことが想像されますが、代わりにきた劉憲ではその対応も出来ないことを見越しての策だといえます。
大軍で呉を攻める
■ 大軍で呉を攻める
大軍で呉を攻める
すでに呉の名臣といえる陸抗や朱績、丁奉はすでに亡く、杜預は都へ呉を攻めるのは今しかないと奏上します。杜預は呉が攻めてくる気配もなく、人材的にも力不足で計略を使えることもないであろうと推測しており、全く負ける要素が見当たらないと考えていました。また、羊祜の意見が採用されなかったのも、武帝が自身の考えを臣下に大きく語らなかったことが要因にあるとしています。
このように杜預は、朝廷での意見をまとめるには武帝自らが呉を攻める覚悟を見せてるほかにないと意見を述べています。武帝は杜預の上奏を読むと、ただちに呉討伐の議論を開いて、開戦を決意しています。
破竹の勢い
■ 破竹の勢い
破竹の勢い
279年、遂に杜預は対呉への総司令官として進軍します。20万ともいわれるこの大軍は、先の離間策も功を奏して、あっという間に呉の領土へ進軍していきます。杜預は軍を2つに分けて攻めたて、優れた戦略を披露していき、次々と城を落としていきます。杜預はただ攻めるだけではなく、各地に刺史を置き、軍を駐屯させたため、略奪などの治安悪化を起さないように努めました。
赤壁の戦いを始め、これまでたびたび呉との対決では風土の違いから疫病の問題がありました。呉の首都である建業に迫ると、配下から気候的に疫病が出る恐れがあるので、冬を乗り越えて進軍するべし」という進言が上がります。
杜預は「兵の士気も高く、固い竹も刀を入れれば手で割ける(破れる)」と言い、進軍は継続されて遂に、孫晧も降伏を決断しました。杜預の快進撃の様と竹のエピソードが後に【破竹の勢い】として故事成語となり、現在にまで使用されています。
人々に慕われた杜預
■ 人々に慕われた杜預
人々に慕われた杜預
杜預は呉を滅ぼした後に昇格しますが、自身は政治家であり将軍ではないとの自己評価をしていたみたいで、武功での評価を辞退しようとしています。杜預は馬にも乗れず、弓も不得意とされており、とても名将と呼ぶのにふさわしくないイメージもあります。しかし、先を見通す目を持ち、どれだけ戦闘で勝利していても、民衆を忘れずに治安の悪化を防いだのはその他の将軍たちでは不可能といわざるを得ないでしょう。
その後、杜預は各地に配属されていき、どこでも善政を敷いたので、住民にはとても慕われていました。杜預は63歳で死去しますが、多くの民衆はその死を嘆き悲しんだといえます。さらに、三国統一後に武帝が政治に興味を失くし、国が混乱する要因を作っていきましたが、杜預が存命だったなら国の建て直しを図れたかもしれません。