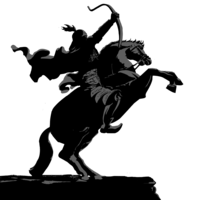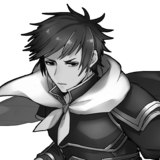呉平定
■ 呉平定
呉平定
紀元200年代の中国、皇帝が3人存在する魏・呉・蜀 3国が均衡を保つ極めて特殊な状況下にありました。
その時代の終盤になると次第に3国の均衡が保たれなくなります。
234年五丈原、諸葛亮は病死し、蜀は魏との戦いで撤退後、蜀を滅ぼすことになります。
魏の司馬懿は238年には遼東の公孫淵を討伐し、魏の朝廷内で揺るぎない地位を確立後、更に皇帝の曹叡は239年に若くして崩御したため、司馬懿の権威は帝室の曹氏をも凌駕していくことになりました。
結果、司馬一族が権威を振るうようになり、魏から禅譲。晋国が誕生します。
呉では孫権の息子、孫登はかなりの有能な当主でした。
そんな呉に対し、魏は国力は最大でも攻勢が出来ない状況でした。
しかし孫登は突如33で死に、跡目争いから内乱が絶えませんでしたが、国力は安定しており軍隊も強かったため滅ぼされません。
そんな中、魏が司馬炎に滅ぼされることになり、晋という国が出来ると、呉に攻勢を仕掛け、呉は晋に滅ぼされてしまいます。
(呉平定)
杜預(とよ)
■ 杜預(とよ)
杜預(とよ)
杜預は、名門の知識人として知られていますが、父が司馬懿(しばい)と仲が悪かったので、父が罪を着せられ幽閉されて命を落としてしまいます。
このことから杜預は、名門ではありましたが、長年不遇の環境に身を置くことになっていました。
杜預は乗馬や弓術など武人としての素質はありません。
しかし、杜預は司馬懿の息子である司馬昭(しばしょう)の妹婿でもあったため父祖の爵位にも就任でき、蜀討伐のときに鎮西長史として従軍する機会を得ることができました。
破竹の勢い
■ 破竹の勢い
破竹の勢い
司馬炎 は、かねてから呉を討伐しようと企ててましたが、賛成者は少なく実行には至りませんでした。
司馬炎 のように呉平定を考えていたのは、杜預を始め、当時の司令官であった羊 祜(ようこ)などを含めた数人でした。
羊 祜は病を抱えていたため、後任に杜預を推挙します。
羊 祜の病没後に行われた司令官交代の隙を突いて呉がせめてきましたが、杜預によって惨敗を喫します。
このことにより、呉の将軍と君主 孫晧(そんこう)の間には不信感が生まれ、呉の国自体も傾いていきました。
これを察した杜預は早速、呉平定の上奏文を送り、司馬炎の許可を得て、呉の侵攻を始めたのです。
建業の近くまで来た時、軍議では疫病が流行る夏の時期を過ぎてから攻め入ろうと言う意見や、長雨の時季も相まって退却の提案も出ましたが、杜預はあくまで侵攻を嘆願しました。
そんな時に杜預が発した言葉が
「竹は、数節刀を入れれば後は手を使えば簡単に割れていく「譬如破竹、譬えるに破竹の如し(勝ち進んできた今こそ、兵威は振るっていて、今なら竹を割くようなものだ)」
」
(数節は当時の観念では1節が15日、つまり、竹の節と暦の節を掛けたもの)
でした。
その杜預の言葉が後押しとなって侵攻が進み、呉は晋に降伏しました。
ここに、統一を見なかった三国時代に終わりが告げられました。
ちなみに、唐時代の中国で有名な詩人『杜甫(とほ)』は、杜預の子孫とのことです。
杜預 も、学者として史書の研究に時間を割いていたようです。
破竹の勢いの類語には、「飛ぶ鳥を落とす勢い」「日の出の勢い」などがあり、みなさんも、使ったことがあるのではないでしょうか?
「破竹の勢い」の由来もわかったことだし、ぜひ、優先で使ってみましょう。