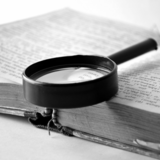勝敗を予知する、7つの基準
■ 勝敗を予知する、7つの基準
勝敗を予知する、7つの基準
(第1章 計篇の続きです)
◆「故にこれを校ぶるに計をもってして、その情を索む」
(ゆえにこれをくらぶるにけいをもってして、そのじょうをもとむ)
【訳】よって、自軍と相手の優劣を計算する基準(七計)でもって、両者の実情を探るのである。
【コメント】前回、「五事」という考え方についてご紹介しました。これは戦争の見通しを考えるための5つの要素―――道・天・地・将・法―――のことです。
この「五事」について自軍と相手を比較するうえで、孫武はより分かりやすい基準を教えてくれています。それがいまからご紹介する「七計」です。
五事……戦争の勝ち負けを決める、5つの要素
七計……より比較しやすくするための、具体例
このように考えておけばいいでしょう。七計の方が、より具体的なのです。
戦の勝敗を決めるのは「国内政治」
■ 戦の勝敗を決めるのは「国内政治」
戦の勝敗を決めるのは「国内政治」
◆「曰く、主いずれか有道なる、将いずれか有能なる、天地いずれか得たる、法令いずれか行はる、」
(いわく、しゅいずれかゆうどうなる、しょういずれかゆうのうなる、てんちいずれかえたる、ほうれいいずれかおこなわる……)
【訳】具体的に言うと、君主はどちらが正しい政治をしているか。将軍はどちらが優秀か。天の条件(気候や季節など)・地の条件(戦いを左右する地形の条件)はどちらに有利か。法律や命令はどちらが徹底して守られているか……」
【コメント】将軍の能力や、天地の条件などは、戦争の優劣を決める要素として分かりやすいでしょう。
しかしもっと注目すべきは、「政治の正しさ」や「法律・命令の徹底度」について言及している点です。戦争はただ将軍や兵士の戦闘力を競うものではなく、国の力量や、軍の組織力も大きく影響します。
「まともな政治が行われ、国民が結束している」国の方が、いざ戦争となったときには強いでしょう。
また国であれ軍隊であれ、「法律が厳格に守られ、命令が徹底されている」側の方が強いはずです。
孫武は将軍や兵士といった、目に見える強さだけではなく、「目に見えない強さ」も必要だと説いているのです。それこそが「正しい政治」であり、「法律の遵守」「命令の徹底」なのです。
戦場でも、強いだけじゃダメ
■ 戦場でも、強いだけじゃダメ
戦場でも、強いだけじゃダメ
◆「兵衆いずれか強き、士卒いずれか練いたる、賞罰いずれか明らかなると。吾れ此れを以て勝負を知る」
(へいしゅういずれかつよき、しそついずれかならいたる、しょうばついずれかあきらかなると。われこれをもってしょうぶをしる)
【訳】兵士の数はどちらが多いか。兵士の訓練度はどちらが上か。功績への褒美・罪への処罰はどちらが明確・公平にされているか……といった点である。私はこうした基準によって、開戦前から戦争の勝ち負けが分かるのである。
【コメント】もちろん戦争である以上、兵士の数や、訓練度は重要です。しかしただ強い兵がたくさんいるだけでは、戦争に勝てません。強い軍隊にちゃんと力を発揮させるには、適切な賞罰(功績への褒美・罪への処罰)が必要になるのです。
もし将軍がエコひいきをして、手柄を立てた強い兵士に褒美を与えず、手柄のない兵士を褒賞したら……強い兵士は「なんだ、必死で戦っても認められないじゃないか」と、やる気をなくしてしまうでしょう。
また、法を犯したり、悪い事をしても罰せられない者がいたら、「ああ、ルールなんて守らなくてもいいんだね」と、他の兵士たちも思ってしまいます。
軍隊にかぎらず、組織というものに力を発揮させるには、賞罰が適切でなければならないのです。だからこそ組織マネジメントの世界では、「信賞必罰」という言葉が口うるさく言われるのです。
孫武が戦争での強さを比較する具体的な基準―――「七計」は、以上のような内容です。
この基準に当てはめる事で、孫武は戦争の勝ち負けが事前に分かるというのですから、スゴイですよね。
三国志にあてはめると、どうなるか?
■ 三国志にあてはめると、どうなるか?
三国志にあてはめると、どうなるか?
それでは、せっかく孫武が「勝ち負けを予見するための具体例」を挙げてくれたのですから、実際に三国志のケースに当てはめて、考えてみましょう。
「七計」は、以下の7項目です(ご紹介しやすいように、一部、並びかえをさせてもらいました)。
【1.正しい政治】君主はどちらが正しい政治をしているか。
【2.将軍の能力】将軍はどちらが優秀か。
【3.法と命令の遵守】法律・命令はどちらが徹底して守られているか
【4.天の時・地の利】天の条件(気候や季節など)・地の条件(戦いを左右する地形の条件)はどちらに有利か。
【5.兵士の数】兵士の数はどちらが多いか。
【6.兵士の強さ】兵士の訓練度はどちらが上か。
【7.信賞必罰】功績への褒美・罪への処罰はどちらが明確・公平にされているか
これらを三国志の具体的な例とあわせ、孫武の「七計」の理論をどう応用するか、見ていきましょう。
七計(1)【正しい政治】君主はどちらが正しい政治をしているか―――蜀(劉禅) VS 魏(司馬昭)
■ 七計(1)【正しい政治】君主はどちらが正しい政治をしているか―――蜀(劉禅) VS 魏(司馬昭)
七計(1)【正しい政治】君主はどちらが正しい政治をしているか―――蜀(劉禅) VS 魏(司馬昭)
この項目については、蜀漢の滅亡を例に考えると、解りやすいでしょう。
諸葛亮死後の蜀は、姜維(きょうい)がたびたび魏を攻撃しますが成果は上がらず、いたずらに国力を消耗してしまいました。さらに宮中では宦官の黄皓(こうこう)が権勢をふるい、政治が大いに乱れました。
このような状況下で、魏の事実上の支配者である大将軍・司馬昭(しばしょう/司馬懿の子)は、蜀漢への大規模な侵攻を決意します。263年、司馬昭は鄧艾(とうがい)・鍾会(しょうかい)らに大軍を率いさせ、蜀への攻撃を開始しました。
これを受け、蜀軍の前線の指揮官である姜維は、すぐに皇帝・劉禅(りゅうぜん)に援軍を要請します。ところが側近の黄皓は、この要請を無視するよう劉禅に進言しました。
(なんと黄皓は、占いによって魏が攻めてこないと信じていたのです。占いを信じるあまり、前線からの報告を無視するのですから、もはやメチャクチャな話です)
このため、蜀軍は十分に体勢が整わないまま、魏の侵攻軍を迎え撃たなくてはならなくなったのです。
この対応の遅れも響き、蜀は鄧艾の軍の進撃を許してしまいます。このとき諸葛亮の孫である諸葛尚(しょかつしょう)が頑強に抵抗しますが、もはや戦の大勢は決していました。
諸葛尚は「黄皓のような者を、早く斬っておかなかったから、こんな事態を招いたのだ」と悔恨の言葉を残し、敵軍へ突撃して戦死したといいます。
こうして魏軍は蜀の首都・成都に迫り、劉禅は成すすべもなく降伏。劉備(玄徳)の創建した蜀漢は、あっけなく滅んだのです。
蜀のあっけない滅亡は、単に魏との国力差だけが原因ではありません。蜀は小さな国とはいえ、姜維の率いる前線の軍は士気が高く、また地形的にも防衛戦には適していました。
やはり滅亡を早めた大きな原因は、黄皓のような人物が政治を乱したことにあります。彼が安全保障上の重大な政策判断まで狂わせてしまったことが、蜀という国にトドメを刺したといえるでしょう。
このように、正しい政治が行われていない国は、戦争になっても戦力を生かすことができず、結局は敗れてしまうのです。