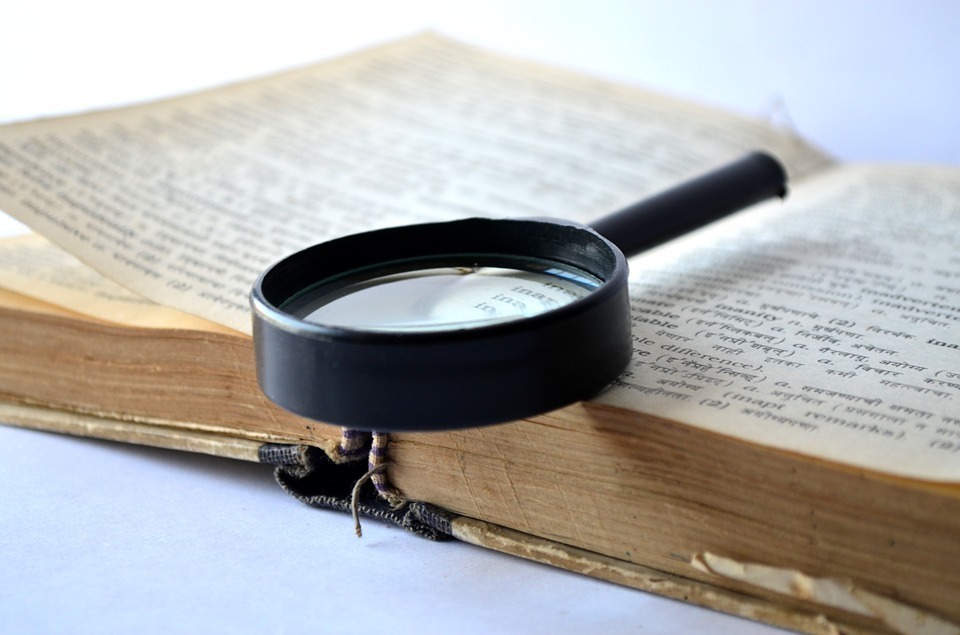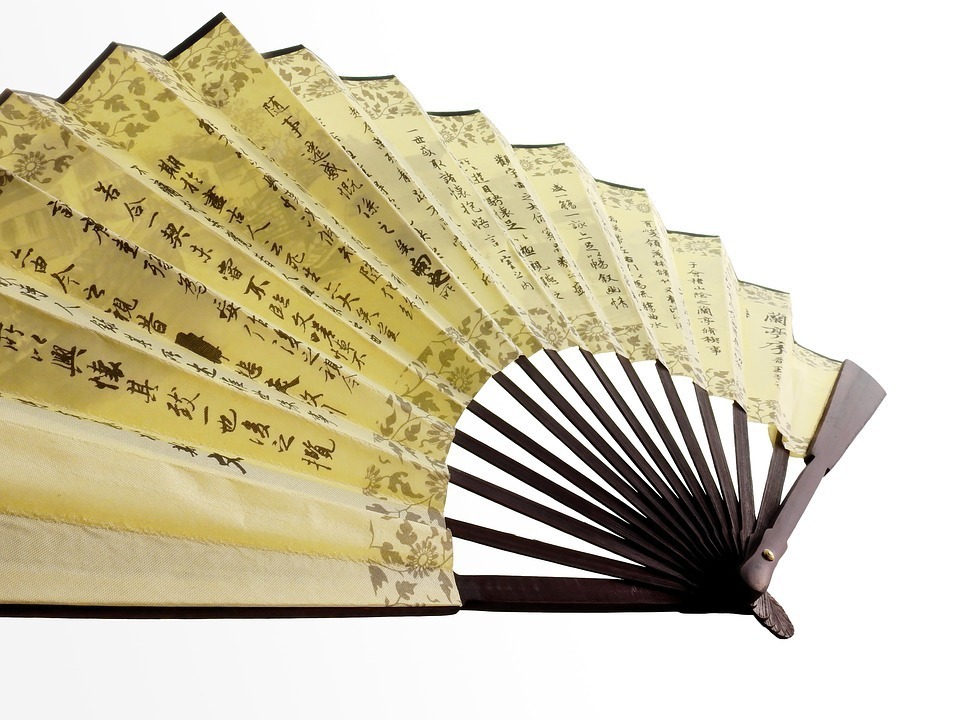孫子とはどういう書物なのか
■ 孫子とはどういう書物なのか
孫子とはどういう書物なのか
「孫子の兵法」という言葉は、三国志を読んでいてもよく出てきます。
武将たちが、合戦を上手く進めるための参考書のようなもの……皆さんがだいたいこんな理解をされていると思います。もちろん、この定義で間違いではありません。
しかし孫子という書物のなかに、具体的にどんな事が書いてあるのかはご存知でしょうか?
「よく分からないけど、『曹操みたいな戦い方をしろ』って、書いてある本なの?」
こう思った方は、とてもするどいのです。
なにしろ三国志随一の戦巧者として知られる曹操は、孫子の注釈書(解説書)まで記したほどの、「筋金入りの孫子マニア」だったのです。現在世界で広く読まれている「孫子」も、曹操の編纂したものが元になっているのですから、スゴイですよね。
「孫子」が書かれた時代
■ 「孫子」が書かれた時代
「孫子」が書かれた時代
「孫子」の「子」とは、学問において独自の流派を立てた人への敬称、またはその人の著作を指す言葉です。よって「孫子」というのは、「孫先生」もしくは「孫先生の書いた本」という意味になります。
その孫先生こそが、孫子の著者である孫武(そんぶ)なのです。
孫武は古代中国の春秋時代に活躍した武将であり、軍事思想家です。
……と、サクサク話を進める前に、いちおう古代中国の時代の移り変わりを見ておきましょう。
殷(いん)→周(しゅう)→春秋(しゅんじゅう)→戦国(せんごく)
→秦(しん)→前漢(ぜんかん)→新(しん)→後漢(ごかん)
→三国(魏・呉・蜀)→西晋(せいしん)
古代の中国は、だいたいこの様に時代が変遷します。春秋時代というのは、秦の始皇帝よりもずっと前の時代です(ちなみに春秋・戦国時代においても、周王朝がほろんだわけではないので、この時代をまとめて東周時代と呼んだりもします)。
ともあれ、三国志よりずっと昔、項羽と劉邦よりも、秦の始皇帝よりもず~~~っと昔の時代に活躍した孫武という人が、軍事思想書を書いたわけです。それが現代にも読みつがれている「孫子」なのです。
春秋時代は始皇帝が中国を統一する前なので、中国がひとつの国になっておらず、それぞれの地域が独立した「国」として存在し、たがいに勢力争いをしていました。孫武はその国のひとつである斉(せい)に生まれましたが、後に長江の南岸にある呉に招かれます(三国志の呉とは無関係の国ですが、エリアは重なっています)。
「孫子」を書いたのはどんな人?
■ 「孫子」を書いたのはどんな人?
「孫子」を書いたのはどんな人?
呉の王様は、孫武に言いました。
「宮中の婦人を使って、貴君の用兵を見せてくれまいか?」
いささか兵法家をバカにした注文のようにも思えますが、孫武は王の依頼を受け、宮中の女性たちに軍事訓練をほどこしました。女官たちをふたつの部隊に分け、王の寵姫(ちょうき/お気に入りの側室)ふたりをそれぞれの隊長に任じます。そうして太鼓の音に合わせ、指示通りの動きをするよう命じました。
こうして孫武は太鼓を叩き、合図をしました。しかし婦人たちは孫武をバカにして笑い、まるで言う事を聞きません。そこで孫武は、将軍である自分の説明不足を認め、合図と行動について再度説明をしました。
そうしてふたたび太鼓を叩いたのですが、婦人たちは相変わらず笑って、言う事を聞きません。
すると孫武は、「再度説明したにもかかわらず、婦人たちが命令を聞かないのは、隊長ふたりの責任である」とし、なんと王のお気に入りであるふたりの寵姫を処刑すると言い出したのです。
あわてたのは呉王で、なんとか寵姫たちを許してくれるよう懇願しました。
しかし孫武は軍の規律は絶対だとして、容赦なくふたりを切って捨てたのです。
隊長たちの処刑後、孫武は新たに隊長を選び直し、再度太鼓を鳴らします。すると孫武に恐れをなした婦人たちは、ひとり残らず指揮に従ったといいます。
寵姫ふたりを無残に処刑され、呉王はいたく感情を害しました。しかし孫武が有能である事を認め、彼を将軍として起用する事を決めます。孫武は王の期待にこたえ、各地の戦争で活躍し、呉の発展に大いに寄与したと伝えられています。
孫子の具体的な内容は?
■ 孫子の具体的な内容は?
孫子の具体的な内容は?
孫子の構成は、以下の13篇(へん)から成っています。
計篇(けいへん) 開戦前に考え、見積もるべき内容を説いています。
作戦篇(さくせんへん) 戦争の費用や、経済への影響を説いています。
謀攻篇(ぼうこうへん) 戦闘に頼らず、計略で敵を倒す方法を述べています。
形篇(けいへん) 勝つための体勢作りについて説いています。
勢篇(せいへん) 軍に勢いをつけて勝利する方法を説いています。
虚実篇(きょじつへん) 自軍の強いところで敵の弱いところをつく方策を述べています。
軍争篇(ぐんそうへん) 敵の機先を制する方法について説いています。
九変篇(きゅうへんへん) 様々な状況の変化について述べています。
行軍篇(こうぐんへん) 行軍を中心とする軍の行動について説いています。
地形篇(ちけいへん) 地形に応じた戦い方を説いています。
九地篇(きゅうちへん) 土地環境が兵士に与える影響と、それを生かした戦い方を説いています。
火攻篇(かこうへん) 火攻めの注意事項や、戦争後の処理について述べています。
用間篇(ようかんへん) スパイ・工作員の用い方を説いています。
もちろんどの項目も重要なのですが、著者・孫武が特に強調したかったのは冒頭の3つの篇ではないかと思います。
1.計篇 2.作戦篇 3.謀攻篇
計篇では、戦争を始める前に、十分な計算・計画をすべきと説いています。自軍と敵軍の戦力をそれぞれ見積もったうえで、戦いが不利であれば、最初から戦ってはいけないと説きます。
作戦篇では、戦争がいかに費用がかかるかを説き、戦いの決断は慎重にすべきと述べています。
そして謀攻篇では、できれば戦闘(軍事衝突)に頼ることなく、謀略を用いて戦わずして勝つ方法を説明しています。
孫子は平和主義者だった?
■ 孫子は平和主義者だった?
孫子は平和主義者だった?
さて、ここまでお読みになって、なにかお気づきになりませんか?
そう。孫子は戦いの方法を示す兵法書ではありますが、決して「ガンガン(戦争に)いこうぜ!」とは説いていません。
むしろ孫武は戦争の怖さを説き、軽々しく戦争を始めるべきではないと忠告しているのです。むしろ孫武は、できる限り戦争を避けることを説いています。戦争のプロだからこそ、孫武は戦争がいかに恐ろしいものかをよく知っていたのです。
よって、戦争を始める前に戦力・国力を十分に計算し(計篇)、戦争になったらどれだけ費用がかかるかを考え(作戦篇)、できれば策略を用いて戦わずして勝つのがいいですよ(謀攻篇)……と、孫武はくどいほどに言っています。
謀攻篇には、以下の名文句があります。
「戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり」
まさにこの一文こそが、孫武のもっとも伝えたかった事だと思います。
それでも……!
どうしても……!
戦争する以外に方法がないのであれば……!
じゃあ仕方がないから、こうやって戦ってくださいね―――というのが、第4篇以降の内容なのです。
以上、今回は「孫子」の成り立ちと概要だけをざっとお話ししてまいりました。
次回からはその具体的内容について、じっくり見ていきましょう。