長坂坡の戦い
■ 長坂坡の戦い
長坂坡の戦い
長坂坡の戦いは、劉備が曹操軍に追われ、家族や民衆とともに敗走した戦いです。
趙雲が劉備の子・阿斗(後の劉禅)を救出するため敵陣に突入していた一方、張飛はわずか二十騎を率いて退路を守りました。
彼に与えられた役割は、いわば「最後の砦」。時間を稼がなければ、劉備たちは全滅してしまう危機的状況でした。
張飛は無謀な猛将じゃない
■ 張飛は無謀な猛将じゃない
張飛は無謀な猛将じゃない
三国志といえば、熱い戦いと個性的な英雄たちの物語。特に張飛といえば、「乱暴者」「猪突猛進」のイメージが強いですよね。でも、実は彼の一番の見せ場でこそ、そのイメージを覆す驚くべき知性と計算された戦略が見えるのです。
今回は、誰もが知るあの伝説的エピソード「長坂坡の橋の一喝」を、少し違った角度から深掘りします。張飛の勇猛さの裏に隠された、知略と心理戦の達人としての一面にきっと驚くはずです。
絶体絶命!劉備軍の最大のピン
■ 絶体絶命!劉備軍の最大のピン
絶体絶命!劉備軍の最大のピン
時は208年、曹操軍の猛追撃を受けた劉備は、家族や民衆を連れて必死の敗走を続けていました(長坂坡の戦い)。この時、劉備軍は完全に壊乱状態。さらに、劉備の息子・阿斗(後の劉禅)が乱戦の中で行方不明になるという最大の危機を迎えます。
そこで孤軍奮闘したのが趙雲。彼は単騎で敵陣に突入し、ついに幼子を救い出します。しかし、問題はその退路です。趙雲が戻ってくるまでに、曹操の大軍に追いつかれてしまえば、すべてが水の泡です。
この超重要任務を任されたのが、たった20騎しか率いていない張飛でした。
単騎で橋に立つ!伝説の大喝の真実
■ 単騎で橋に立つ!伝説の大喝の真実
単騎で橋に立つ!伝説の大喝の真実
「
張飛は川の橋に馬を乗り入れ、ぐっと槍を突き立てた。
後ろでは劉備の家族や民が必死に退避し、味方の兵たちも固唾を飲んで見守っている。
「兄者よ、任せろ!趙雲が戻った。ここは俺が食い止める!」
仲間の兵が慌てて声を上げる。
「張将軍、たったお一人で!?あまりにも危険です!」
張飛は一喝するように言い放った。
「黙れ!ここで退けば誰も助からんのだ!」
そして橋の中央に馬を進め、大地を震わせるような声を張り上げた。
「我こそは燕人張飛である!死を賭してかかってくる者はいるか!」
その怒声は雷鳴のように響き、対岸に控える曹操軍を震え上がらせた。
敵の兵がざわめく。
「な、なんだあの気迫は……」
「張飛だと!?あの猛将か……」
「伏兵が潜んでいるに違いない。下手に突っ込めば全滅だ!」
ある将は槍を構えかけたが、すぐに手が震えて引き戻す。
「曹公……進軍いたしますか?」
曹操も馬上で目を細め、ただならぬ気配を感じていた。
「いや……無闇に突っ込むな。張飛の背後には必ず伏兵がいる。慎重にせよ。」
その一言で全軍が動きを止める。
張飛は敵の足が完全に止まったのを見届けると、槍で橋を突き崩した。轟音とともに橋が落ちる。
味方の兵が歓声を上げる。
「張将軍!敵が退きましたぞ!」
「す、すごい……たった一喝で大軍を止めてしまった……!」
張飛は鼻息荒く馬を返す。
「ふん、奴らの肝が小さいだけよ!行くぞ、兄者を追う!」
こうして、張飛の一喝は大軍の進撃を止め、劉備軍の退避を成功へ導いたのである。
」
というイメージでしょうか? 整理します。
趙雲の帰還を確認した張飛は、単騎で橋の上に立ちます。
そして曹操軍を睨み据え、大喝しました。
「我こそは燕人張飛である!かかってこい!死を決する者はいないのか!」
その迫力はすさまじく、曹操軍の将兵は誰一人前に進めなかったといいます。
さらに張飛は橋を破壊。曹操軍は「背後に伏兵が潜んでいるのでは」と疑い、撤退を選びました。
ここで重要なのは、張飛が「無謀な突撃」ではなく、敵の心理を揺さぶる芝居を打ったという点です。
彼は自分の声と威圧感で「大軍が潜んでいる」と思わせ、敵を足止めすることに成功したのです。
単なる武勇伝じゃない
■ 単なる武勇伝じゃない
単なる武勇伝じゃない
一見すると、「張飛、超強くてビビった!」という単純な武勇伝のように思えます。しかし、よく分析すると、張飛の計算され尽くした戦略が見えてきます。
1. 完璧な「陽動」と「欺瞞」の戦術
張飛の最も賢かった点は、20騎という少数の兵で「大軍が待ち構えている」ように見せかけたことです。
視覚的効果:馬の尾に枝を結びつけ、大量の砂塵を上げさせたのは、大軍の移動を演出する古典的ながら極めて効果的な方法です。
心理的効果:曹操は劉備が伏兵を仕掛けてくるかもしれないと常に警戒していました。張飛はこの曹操の猜疑心を見事に利用したのです。
2. 地の利を最大限に生かした場所選び
橋というのは、一騎打ちには最適の場所です。大軍が一気に攻め込むことができず、数的劣勢を相殺できる choke point(扼点) です。張飛はこの地の利を最大限に活かす場所を選んで立ちはだかったのです。
3. 曹操軍の心理を読んだ「演出」
もし本当に無鉄砲なだけの武将なら、最初から自軍の不利も顧みず突撃していたでしょう。しかし張飛は、趙雲が戻るまで時間を稼ぐという明確な目的を持ち、そのために最も効果的な「パフォーマンス」を選択しました。
彼の大喝は、単なる威嚇ではなく、「おいでおいで、かかってこい!でも…本当にこっちには何もないと確信してるのか?」と相手の疑心を煽る、高度な心理戦だったのです。
張飛像の意外な一面
■ 張飛像の意外な一面
張飛像の意外な一面
長坂坡のエピソードは、張飛の「勇」だけが強調されがちですが、その本質は 「勇」を形にするための「知」 にあったと言えるでしょう。
状況分析力:自軍の劣勢と目的(時間稼ぎ)を正確に理解。
戦術構築力:陽動と地の利を活かした戦術を即座に構築。
心理洞察力:敵将・曹操の猜疑心を見事に衝いた。
「張飛は武勇だけの武将」という固定観念は、このエピソードを深く読むと大きく覆されます。彼は劉備陣営を支えた、勇猛かつ計算高き、バランスの取れた知将だったのです。














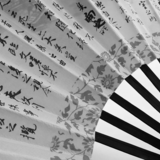











古代の雑学を発信