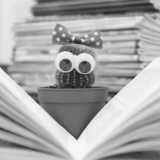義理の息子に裏切られた丁原(建陽)の不幸話
■ 義理の息子に裏切られた丁原(建陽)の不幸話
義理の息子に裏切られた丁原(建陽)の不幸話
三国志は各地で乱を起こしていた黄巾賊が衰退し董卓(仲謀)が猛威を振るったあたりから徐々にストーリーが展開されています。権力者である董卓(仲謀)はまさにやりたい放題でストップをかける者はあまりいませんでした(キングダムを読んでいる人は呂不韋を想像してもらうと分かりやすいかもしれません)
その中で真正面から対抗しようとしたのが丁原(建陽)です。董卓(仲謀)は丁原(建陽)が邪魔な存在のため斬ってしまおうと思っていましたが、ボディーガードである呂布(奉先)が目を光らせていたためそれは叶いませんでした。
呂布(奉先)がいては丁原(建陽)を倒すことはできないと思った董卓(仲謀)は呂布(奉先)に赤兎馬を贈呈し自分の陣営に迎え入れたのです。
呂布(奉先)は義父である丁原(建陽)をあっさりと殺してしまいました。わが子のように育てた呂布(奉先)に殺され、さらには悪政をふるう董卓(仲謀)をどうすることもできなかった丁原(建陽)は不幸というしかありませんね。
母を人質に取られた徐庶(元直)の不幸話
■ 母を人質に取られた徐庶(元直)の不幸話
母を人質に取られた徐庶(元直)の不幸話
三国志の天才と言えば真っ先に諸葛亮(孔明)という名前が挙げられることでしょう。しかし、諸葛亮(孔明)は元々劉備(玄徳)の元でタクトをふるっていたわけではありません。三顧の礼で劉備(玄徳)が諸葛亮(孔明)を軍師に迎え入れたエピソードは有名ですが、その諸葛亮(孔明)を劉備(玄徳)に紹介したのが徐庶(元直)です。
徐庶(元直)は元々劉備(玄徳)の元で軍師をしていました。
関羽(雲長)、張飛(翼徳)を従える劉備軍の力はすごかったのですが、緻密な軍略という物はなくあまり成果を上げることができずにいましたが徐庶(元直)を軍師に引き入れることができた劉備(玄徳)は徐々に頭角を現すのです。
ところが徐庶(元直)はヘッドハンティング好きの曹操(孟徳)の目に留まるのです。母親を人質に取られ自分の元で働くようにと言われてしまいます。徐庶(元直)は劉備(玄徳)の元で働きたかったのですが、母が気がかりだったため諸葛亮(孔明)を劉備(玄徳)に紹介し曹操(孟徳)の元へ行くのでした。
ところが話はそこで終わらず、息子が君主を裏切って自分の元に来たと知った母はそれを恥じて自殺してしまうのです。それからは実力はあったものの徐庶(元直)は曹操(孟徳)の元で知略をふるうという事はありませんでした。
あっけない結末を迎えた孫堅(文台)の不幸話
■ あっけない結末を迎えた孫堅(文台)の不幸話
あっけない結末を迎えた孫堅(文台)の不幸話
わずか17歳で海賊退治に成功した孫堅(文台)は功績を修め続け「江東の虎」という異名を与えられるほどでした。力があり周りから一目置かれる存在で、黄巾賊討伐の際に大いに活躍しました。
袁紹(本初)をリーダーとした反徳卓連合では先鋒隊を任せられ、相手の先鋒隊である華雄と激突しました。優勢でしたが、攻め込んでいる際に食料物資が滞るという事件が起き(袁術(公路)が意図的に物資を送らなかった)結局自分たちが逃げてしまうという目にあってしまったのです。
しかし不幸なことばかりではありません。孫堅(文台)は連合軍が解散となった後落葉で皇帝の印である玉璽を井戸の中から見つけ自分の物にしてしまったのです。ところがそれが他国の者にばれ、劉表(景升)にばれ命を狙われる羽目になります。実力的にどうにかなる相手でしたが、自分の武力を過信してしまったため相手の策略にはまり、全身に石や矢を浴び、37歳の若さで亡くなってしまいました。
彼が生きていれば袁紹(本初)、曹操(孟徳)、孫堅(文台)の三人が三国志の中心にいたかもしれませんね。
父とは違い評価が高かった劉諶の不幸話
■ 父とは違い評価が高かった劉諶の不幸話
父とは違い評価が高かった劉諶の不幸話
劉備(玄徳)の後を継いだ劉禅(公嗣)が愚弟だったという話は三国志をちょっと知っている人ならうなずく人が多いことでしょう。劉禅(公嗣)は戦えば何とかなったかもしれなかったものをあっさり降伏し、悠々自適な生活を得ることを選びました。
しかしその子供である劉諶は違いました。
劉諶は幼少のころから聡明で勇気があったと言われています。蜀が滅亡する間際では徹底抗戦しようと唱えましたが父である劉禅(公嗣)からは一蹴されてしまいました。
それでもここで降伏してしまったら劉備(玄徳)に申し訳が立たないと言い、劉諶は劉備(玄徳)を祭る墓の前で際しともども自決しました。
彼が不幸だったのはおろかな父親を持ったこともありますが、5男だったという境遇も不幸を増長させる要素の一つだったというところです。もし長男だったらもっと求心力があったのかもしれませんが、7人兄弟の5番目という事で宮廷での発言権が乏しかったと言われています。
とにかく君主に恵まれない陳宮(広台)の不幸話
■ とにかく君主に恵まれない陳宮(広台)の不幸話
とにかく君主に恵まれない陳宮(広台)の不幸話
陳宮(広台)は三国志では天才軍師の一人として登場しています。しかし彼を語る上で欠かせない曹操(孟徳)の話をまずしたいと思います。
三国志の帝王と言える存在の曹操(孟徳)ですが、実は何度も死にそうなった経験があります。その一回目が董卓(仲謀)暗殺未遂事件です。彼は意気揚々と「自分が董卓(仲謀)を暗殺する」と言ったのですがあっけなく失敗しました。失敗するだけならいいのですが、逆に殺人未遂という事で指名手配され陳宮(広台)につかまってしまうのです。
しかし陳宮(広台)は董卓(仲謀)の悪政をよくないと思っていたため曹操(孟徳)を逃がすのです。しかもただ逃がすだけでなく、自分も一緒に逃げてお供となったのです。
最初は好青年だと思っていた曹操(孟徳)ですが、私利私欲のため人を殺すどうしようもない人物だという事が分かってしまいました。
そんな曹操(孟徳)を見限った後ついたのが呂布(奉先)です。呂布(奉先)の元で知略をふるい、戦を勝利に導くことはありましたが、進言を聞き入れられないこともありました。そして結局曹操(孟徳)に捕まります。曹操(孟徳)は自分の元で働かないかと言いますが、死を選びました。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志の不幸な人の話をしましたがいかがでしたでしょうか。勇ましいのに周りに受け入れられない者、天才なのにその実力を発揮できなかった者、自分の置かれた境遇によりどうしようもできなかった者など多々います。
華々しい戦績を上げる将軍がいる裏でこういった不幸なものがいたという事を知ってもらえれば彼らの不幸もほんのちょっとは報われるのではないでしょうか。