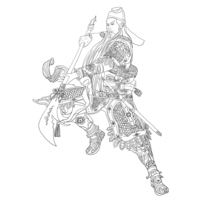諸葛亮と直接対決なった第四次北伐
■ 諸葛亮と直接対決なった第四次北伐
諸葛亮と直接対決なった第四次北伐
蜀は諸葛亮が毎年のように北伐を繰り返してきますが、そのたびに補給が追い付かずに撤退を繰り返していきます。231年の春になると、4度目の北伐を開始しました。またも補給がもたないだろうと楽観していた魏国内は、司馬懿を総司令官として10万もの大軍で蜀軍を迎え打ちます。
司馬懿も諸葛亮と対決するにあたり、国力を含めた戦力差や補給の難しさを挙げており、孟達のときほど警戒心はなかったといえます。しかし、諸葛亮は現地で刈入れを行い、輸送にも木馬を開発していたので、長期戦が可能となっていました。諸葛亮は軍を分けて臨み、自らは魏延を先鋒にしており、別働隊には王平を向かわせて祁山を攻めたてました。
しかも第三次北伐の時に北方の異民族を攻略して味方に付けており、司馬懿の背後を襲わせようと画策していました。焦った司馬懿は軍を二手に分けて自らが諸葛亮に向かい、歴戦の名将である張コウを王平の相手とさせています。
王平は張コウに対して懸命に守備を固め、見事に撃退しました。司馬懿は大軍を以って攻めますが、魏延の奮闘や諸葛亮の連弩などの武器もあって大敗を喫してしまいます。守備を固めながら攻めてくる諸葛亮の兵法に苦しみ、司馬懿は退却を決意しました。
退却戦で張コウを失う
■ 退却戦で張コウを失う
退却戦で張コウを失う
諸葛亮ら蜀軍は局地的な合戦で連勝し、意気揚々と長安へと進出を図ろうとしましたが、雨があまりにも続き、さすがに兵糧の確保が難しくなっていきました。十分な兵糧を用意していたにも関わらず、蜀本陣からの輸送が途絶えてしまったので、諸葛亮は全軍撤退を余儀なくされます。
司馬懿はこの機を逃すまいとして、張コウに追撃を命じます。蜀軍は勝って退却するので、諸葛亮が伏兵を用意しているから危険であると張コウらは進言しますが、司馬懿は断じて追撃を指示しました。先の曹真や曹休らの大敗からの失脚を見ている司馬懿は、自身が曹氏の一族でないから身の危険が及ぶ可能性が高いと踏んで、何とか失脚を免れたい一心からきたものといえます。
張コウが諸葛亮らをめがけて追撃すると、蜀軍は高所に伏兵を配し、張コウ軍に対して一斉射撃を繰り広げていきました。さしもの張コウもこれには敵わず、弓によって討たれてしまいます。張コウを失った魏軍は今度こそ退却し、司馬懿は諸葛亮の恐ろしさを身に染みて感じていきました。
5度目の北伐で守備を徹底する
■ 5度目の北伐で守備を徹底する
5度目の北伐で守備を徹底する
司馬懿は処断されることも覚悟していましたが、曹真や曹休といった大将軍に張コウといた名将までも相次いで失った魏にとって、蜀や呉の大軍と対等に渡り合える指揮官は司馬懿しかおらず、処罰されるのを免れました。司馬懿は諸葛亮が再度攻めてくることを予測し、今度は討ってでないように考えていました。
蜀では連年の北伐で兵が疲弊し、国力の回復を待っていました。諸葛亮は自分の死期が近いことを悟り、234年に5度目となる北伐を敢行しています。諸葛亮は勝算もありましたが、懸念されることが2つありました。
諸葛亮にある2つの懸念
■ 諸葛亮にある2つの懸念
諸葛亮にある2つの懸念
まずは魏軍が守勢に回ることです。先の戦いで司馬懿は痛いほど蜀軍に苦しめられているので、司馬懿が総指揮官になると今度は徹底した守備に回るだろうと推測していました。兵糧の問題がある蜀軍にとって、持久戦は避けたいところであり、何としても攻勢に回ってもらわないといけないからです。
もう一つの懸念は自身の死後にありました。指揮が近いことを受け、陣中で没する可能性もあったので、その場合は退却戦になりますが、宿将でもある魏延が本陣の撤退指示に素直に賛同するかということでした。これまで散々諸葛亮と意見の食い違いを見せていた魏延でしたので、下手をすれば突撃していき、蜀軍が分裂してしまう恐れがあったからです。
しかも相手が司馬懿とあれば、蜀軍が分裂してしまうとあっという間に壊滅してしまう可能性は否定できないといえました。
守備作戦で蜀軍が退却
■ 守備作戦で蜀軍が退却
守備作戦で蜀軍が退却
蜀軍は現地で刈入れを行う屯田を行い、持久戦も覚悟していました。対する魏軍は司馬懿が総大将として迎え打ちます。諸葛亮の懸念は的中し、長期の持久戦の構えとなっていきました。蜀軍はさんざん魏軍を挑発し、諸将が激怒するほどでした。司馬懿の配下たちは競って討って出るように進軍しますが、司馬懿は決して賛同しませんでした。どれだけ屯田を敷いて、補給路を確保していても、国力で勝る魏が持久戦に負けることはないので、このまま座しても勝てると踏んでいたからです。
諸葛亮や諸将は攻撃を繰り広げますが、徹底した守備を敷いている以上、司馬懿の堅固な陣を打ち崩すことができずにいました。魏の諸将たちの怒りが頂点に達する頃、司馬懿はこの守備作戦は魏の皇帝である曹叡からの勅命でもあると諭します。それでも諸将が討ってでたいというのなら、皇帝の許可を受ける必要があるとして都に伝令を出しています。これで一応の対応を取った司馬懿に対し、諸将は皇帝の勅命ならば仕方ないと諦めモードになりました。もちろん司馬懿には討ってでる気持ちなどなく、諸将らの士気を下げないために必要な対応を取ったに過ぎません。
諸葛亮の死
■ 諸葛亮の死
諸葛亮の死
都に伝令が出たというのは蜀軍にも伝え広まり、これで魏軍が攻勢に回る可能性があると蜀陣営は活気付きます。しかし、諸葛亮は皇帝に許可を取る行動そのものが、司馬懿が討ってでないことを意味していると悟り、この戦いに勝つことは不可能になったと実感していきます。
諸葛亮は病に倒れ、後事を諸将に託し、陣中に没していきます。このことは蜀に送り込んだ間者によって知らされ、蜀軍が退却することを受けて、司馬懿は追撃しようと試みます。しかし、蜀軍が攻撃に回ろうとしたので、司馬懿は諸葛亮が死んだのは嘘の情報なのかもしれないと踏み、追撃ができずにいました。
結局蜀軍は無事に退却することができ、諸葛亮のもう一つの懸念だった魏延も蜀軍によって討たれています。司馬懿は諸葛亮が本当に死んだことを知り、その陣跡をみて「諸葛亮は天下の奇才である」と漏らしたと伝えられています。このことは後世によって「死せる孔明、生ける仲達を走らす」と称されるようになりました。
魏の中枢を担う司馬懿仲達
■ 魏の中枢を担う司馬懿仲達
魏の中枢を担う司馬懿仲達
司馬懿は帰参し、曹叡にも絶賛されていきました。諸葛亮が死んだことにより、蜀は大した行動も起こせないと踏んでいたからです。翌年に蜀の馬岱が攻めてきましたが、司馬懿は自らが赴きもせず、配下に指示して撃退しています。
今後の司馬懿は権力の座に就くようになりますが、まだ聡明な曹叡が健在とあって曹氏を抑え込むようなことまではできませんでした。諸葛亮の死後、三国志は終焉を迎えることになっていきますが、司馬懿が本領を発揮するのはこれからといえました。