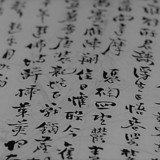1.三国志から人生の教訓を得る(エピソード)
■ 1.三国志から人生の教訓を得る(エピソード)
1.三国志から人生の教訓を得る(エピソード)
10万の矢
■ 10万の矢
10万の矢
赤壁の戦いの前のエピソードとして有名なのが「10万の矢」です。赤壁の戦いは、呉・蜀が手を結び魏と戦った三国志の大きなターニングポイントとなっています。呉と蜀は同盟しているのですが、呉の周瑜は蜀の諸葛亮を恐れており、この機会の諸葛亮を抹殺しようと考えていたのです。そこで、周瑜は諸葛亮に対し、「10日で10万の矢を作れ」と無理難題を押し付けたのです。当時の技術力では、矢の大量生産など不可能であり、10万本を10日で用意するなんて事実上不可能でした。しかし、諸葛亮は「3日で作ります」と快諾するのです。
そして、本当に諸葛亮は3日で矢を用意するのです。実は、諸葛亮は矢を作ったのではなく、曹操軍を利用して10万の矢を用意したのです。藁人形を積んだ船を20隻用意し、濃い霧の中で曹操軍の前に出航させます。曹操軍は敵襲だと思い、大量の矢を放ちます。諸葛亮は船を回収すると、藁人形に刺さった矢を抜き10万の矢を用意したのです。
このエピソードから、発想の転換について学ぶことができます。10万の矢を作るのが無理なら、あるところから都合つければいいのです。固定概念で凝り固まっていたら、こんな発想はでてきません。無理難題を押し付けられたら、10万の矢の思い出してみてください。
泣いて馬謖を斬る
■ 泣いて馬謖を斬る
泣いて馬謖を斬る
現代でも使われる故事成語なのが「泣いて馬謖を斬る」です。このエピソードからも、人生の教訓を得ることができます。このエピソードは、諸葛亮が愛弟子である馬謖を涙ながらに処刑したことからできました。街亭の戦いにおいて、馬謖は諸葛亮の指示に背いたことで、蜀は敗戦したのです。その責任を取らせるために、諸葛亮は愛弟子であった馬謖を処刑にしたのです。
このエピソードから、規律を守るためには、個人的な感情に左右されるべきではないという教訓を得ることができます。もし、馬謖を処刑しなかったら、蜀の武将から「命令違反しても問題ない」と認識される恐れがあります。そうなれば蜀の規律は乱れることになってしまうのです。だから、規律を守るためには、いくら親しい間柄であっても、命令違反はしっかりと罰する必要があります。現代でも規律を守るためには、個人的な感情に左右されるべきではないのです。
三顧の礼
■ 三顧の礼
三顧の礼
三国志のエピソードからできた故事成語と言えば「三顧の礼」が有名です。三顧の礼は、とても教訓になるエピソードとなっています。三顧の礼とは、劉備(玄徳)が諸葛亮を迎えるために、3度も訪ねたというエピソードとなっています。当時、劉備(玄徳)は40代であり、一方の諸葛亮は20代です。しかも劉備(玄徳)には多くの部下がおり、諸葛亮は在野の一個人に過ぎません。しかし、劉備(玄徳)は誠意をもって3度も訪ね、劉備(玄徳)を迎え入れることに成功したのです。
このエピソードから、誠意をもってあたることの大切さを学ぶことができます。肩書や年上であるという理由で横柄な態度をとっては、交渉事は成功しません。誠意をもって交渉に当たることによって、成功するのです。これは現代社会でも同じことが言えます。仕事をする上で、三顧の礼はとても良い教訓になるのではないでしょうか。
2.三国志から人生の教訓を得る(名言)
■ 2.三国志から人生の教訓を得る(名言)
2.三国志から人生の教訓を得る(名言)
士別れて三日、即ち更に刮目して相待すべし
■ 士別れて三日、即ち更に刮目して相待すべし
士別れて三日、即ち更に刮目して相待すべし
この言葉は、呂蒙が放った言葉となっています。呂蒙はもともと、学がありませんでした。家が貧しく、学問に触れる機会がなかったのです。そこで、孫権は呂蒙に学問を勧めるのです。孫権の勧めとあって、呂蒙は勉学に励むようになります。すると、学者にも劣らぬほどの知識を身に付けたのです。その後、呉随一の知恵者である魯粛と会話を交わし、魯粛は「呉下の阿蒙に非ず」と評価すると、呂蒙は「士別れて三日、即ち更に刮目して相待すべし」と答えたのです。
この言葉の意味は、「士(男)なら別れて三日もあれば、随分と成長するものであり、次に会うときには注意して見るべきです」となります。この言葉から得ることができる教訓は、誰もが成長することはあり得るということです。努力すれば成長するものであり、過去の評価を引きずっていては、相手を正確に評価することはできません。日々、人は成長するものだと思い知らされる名言となっています。
その長ずる所を貴び、その短なる所を忘れるべし
■ その長ずる所を貴び、その短なる所を忘れるべし
その長ずる所を貴び、その短なる所を忘れるべし
この名言は、もともと老子が使った言葉となっています。三国志では、呉の初代皇帝である孫権が好んで使った言葉としても有名です。「その長ずる所を貴び、その短なる所を忘れるべし」とは、人には一長一短があることを認識し、短所には目をつぶり長所を活かせるようにするべきとの意味があります。これは、現在でも通用する考え方であり、とても教訓になります。誰でも長所と短所の両面を持っているものであり、完全無欠の人などいません。だからこそ、短所ばかりを見るのではなく、長所を見ることが大切なのです。これからは、相手の長所を見るように心がけていきましょう。
勝負は変化あり、詳らかにせざるべからず
■ 勝負は変化あり、詳らかにせざるべからず
勝負は変化あり、詳らかにせざるべからず
沮授が残した名言である「勝負は変化あり、詳らかにせざるべからず」も、現代社会でも通じる教訓となります。この名言には、勝負は常に変化するものであり、よく見定める必要があるという意味があります。現代社会において、勝負事はたくさんあるのが現実です。日々、勝負と言っても過言ではありません。そのため、この名言は教訓として活かすことができるのです。どんな勝負であっても、絶対はありません。状況が変われば、勝負の結果は変わってきます。だからこそ、勝負の変化を見定め、勝つために行動していく必要があるのです。「勝負は変化あり、詳らかにせざるべからず」という名言を胸に刻んで、日々勝負していきましょう。
3.まとめ
■ 3.まとめ
3.まとめ
今回は、三国志のエピソード・名言から、人生の教訓として活かせるものをいくつか紹介してきました。どのエピソード・名言も、人生において大切なことを教えてくれています。胸に刻んでおくことによって、これからの人生において大きな影響を与えてくれるのではないでしょうか。三国志のエピソード・名言は、これ以外にもたくさんあります。そのどれもが、人生の教訓として得られるばかりです。そのため、三国志のエピソードや名言にも注目してみてください。座右の銘なども見つかるかもしれません。ぜひ、三国志を人生の教訓として活かしてみてください。