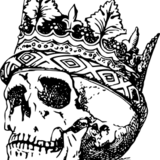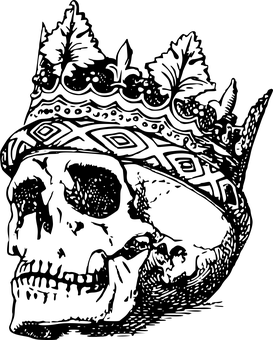公孫延の移住
■ 公孫延の移住
公孫延の移住
公孫延という男がなぜ住んでいた遼東郡襄平県から離れたのかは、どこにも記録が残っていません。おそらく追い出されるような形で遼東郡から隣郡の玄菟郡に移住したようです。何かトラブルを起こしたのか、騒動に巻きまれたのか、どちらにせよこれ以上は住んでいられない状況になったようです。
玄菟郡に移り住んだ公孫延は、太守である公孫琙に郡吏として仕えることができました。この頃、太守の公孫琙は息子を亡くし、失意のどん底にいたようです。息子の名は豹。18歳でした。
そして驚くべきことに、移住してきた公孫延の息子もまた豹という名(幼名)で、18歳でした。正式な名は度といいます。公孫度、字は升済です。
公孫度の幸運
■ 公孫度の幸運
公孫度の幸運
地縁のない公孫度にとって、この出会いは幸運でした。
息子を亡くした太守の公孫琙は、公孫度をその代わりとして可愛がったからです。立派な師に学問を学ぶことができ、公孫琙の勧めで妻を迎えます。おそらく名士の家柄の娘だったのではないでしょうか。
公孫度は有道に推挙され、尚書郎に任命されます。そして冀州の刺史にまで昇進するのです。かなりの出世です。その背景には、公孫琙の威光や、妻の実家の影響もあったと考えられます。
その間、公孫度は息子の公孫康を、自らの故郷である遼東郡襄平県に住まわせています。しかし県令の公孫昭は、公孫康を召し出しましたが、軽んじて伍長に任じました。これは公孫度・公孫康親子への嫌がらせに他なりません。
襄平県では公孫度の一族はかなり嫌悪されていたということでしょう。
公孫度の復讐
■ 公孫度の復讐
公孫度の復讐
公孫度自身も流言のために失脚し、冀州刺史から罷免されてしまいます。どのような流言だったのかは、こちらも記録に残っていません。何かしらの政争劇があったのでしょう。
しかし、ここで思わぬ救いの主が現れます。後漢の朝廷が董卓に牛耳られることになり、その際に遼東郡出身の徐栄が、董卓に公孫度を推挙したのです。
徐栄といえば、曹操を破ったことでも有名な戦上手の武将です。はたして公孫度とどのような繋がりがあったのか。もしかすると公孫度の妻の実家と徐栄は親戚関係だったのかもしれません。
董卓は公孫度をなんと遼東郡の太守に任じます。こうして追い出された故郷の太守に返り咲いたわけです。
公孫度は任地に到着するや、すぐに元県令だった公孫昭を捕らえさせます。息子に嫌がらせをした県令です。罪状も明らかにせぬままに、公孫度は公孫昭を市場に引き出し、鞭で打って処刑しました。
さらに公孫度の一族に屈辱を与え続けてきた豪族の田韶を捕らえ、罪を洗い出して処刑します。そして田韶の一族をことごとく皆殺しにします。関係性のある家はすべて潰しました。その数は100あまりにのぼったと記されています。
こうして公孫度は、幼い頃から虐げられてきた襄平県に復讐を果たしたのです。
武勇にも優れていた公孫度
■ 武勇にも優れていた公孫度
武勇にも優れていた公孫度
公孫度は学問だけでなく、武芸や兵法も学んでいたのでしょう。遼東郡の太守に任命されてから、周囲を囲む勇猛な異民族を次々に破っていきます。
東の高句麗、西の烏丸などです。中央からの援軍が期待できぬなか、どのような戦略と策を用いてこのような強力な勢力を討伐したのでしょうか。
とにかくこの事実は全土を震撼させ、「遼東郡の公孫度」の名を一躍世に広めることになります。
公孫度は後漢王朝の衰退ぶりを知り、遼東で独力勢力を築き、王となることを夢見るようになります。
遼東郡を分けて、遼西中遼郡として太守を置き、さらに青州の東萊郡を支配下に加えて、営州刺史を置きました。
そして「遼東侯」・「平州牧」を自称するようになるのです。ここに至り、公孫度は侯国を建てたわけです。
公孫度⇒公孫康⇒公孫恭⇒公孫淵
■ 公孫度⇒公孫康⇒公孫恭⇒公孫淵
公孫度⇒公孫康⇒公孫恭⇒公孫淵
献帝を許都に迎えた曹操は上表し、公孫度を武威将軍・永寧侯に取りたてました。しかし、公孫度は自らを遼東の王だとして、この印綬を武器庫に隠してしまいました。
公孫度の死後は公孫康が継ぎ、朝鮮半島への勢力を拡大し、楽浪郡の南部を帯方郡とします。さらに曹操に敗れて逃れてきた袁紹の息子たち(袁熙、袁尚)を処刑して、その首を曹操に送り、襄平侯・左将軍に任じられています。
公孫康の死後は弟の公孫恭が後を継ぎ、曹丕が皇帝に即位すると、車騎将軍・仮節・平郭侯となりました。
公孫度の一族は、こうして遼東方面に一大勢力を築きあげたのです。
しかし、公孫康の息子であった公孫淵は、叔父の公孫恭を幽閉し、当主の座を奪いました。
ここから公孫度の一族は滅びの道を歩み始めていきます。
燕王・公孫淵
■ 燕王・公孫淵
燕王・公孫淵
二代目皇帝である明帝(曹叡)は、公孫淵を揚烈将軍・遼東太守に任じます。
野心に満ちた公孫淵は、魏だけではなく、呉とも通じ、孫権から「燕王」に封じられました。
しかし公孫淵は呉から訪れた使者を処刑し、その首を魏に届け、大司馬・楽浪公に任じられます。
魏も公孫淵の態度を怪しんで、詔勅で召そうとしましたが、ここで公孫淵は完全に独立を表明し、燕王を自称するようになります。そして元号を紹漢元年と定め、魏領に侵攻し始めるのです。
これに対し、魏は太尉である司馬懿を司令官として討伐軍を派遣します。公孫淵は呉の孫権に援軍を求めるも、間に合わず、司馬懿に敗れました。
まとめ・遼東の成人男性7000人が虐殺される
■ まとめ・遼東の成人男性7000人が虐殺される
まとめ・遼東の成人男性7000人が虐殺される
最終的に襄平城で籠城することになった公孫淵ですが、城は完全に包囲されている状態であり、さらに兵糧も底を尽きます。餓死者が続出し、人々が食らい合うという最悪な事態となります。
公孫淵は再三に渡り司馬懿に和議や降伏の使者を立てますが、認めてもらえず、仕方なく城を抜け出したところを発見されて、公孫淵とその息子である公孫脩は斬り殺されています。
主を失った襄平城に司馬懿は急襲し、徹底的に将兵や民を虐殺しました。その数は7000人にものぼり、その首は高く積み上げられました。
公孫淵の叔父で幽閉されていた公孫恭は、この時に救出され、司馬懿の嘆願によって処刑を免れ、釈放されています。洛陽にいた公孫度の一族はことごとく処刑されたそうです。
公孫度の復讐から始まった遼東の支配ですが、最期は逆に復讐される形で幕を閉じます。こうして遼東の公孫氏は滅亡したのです。