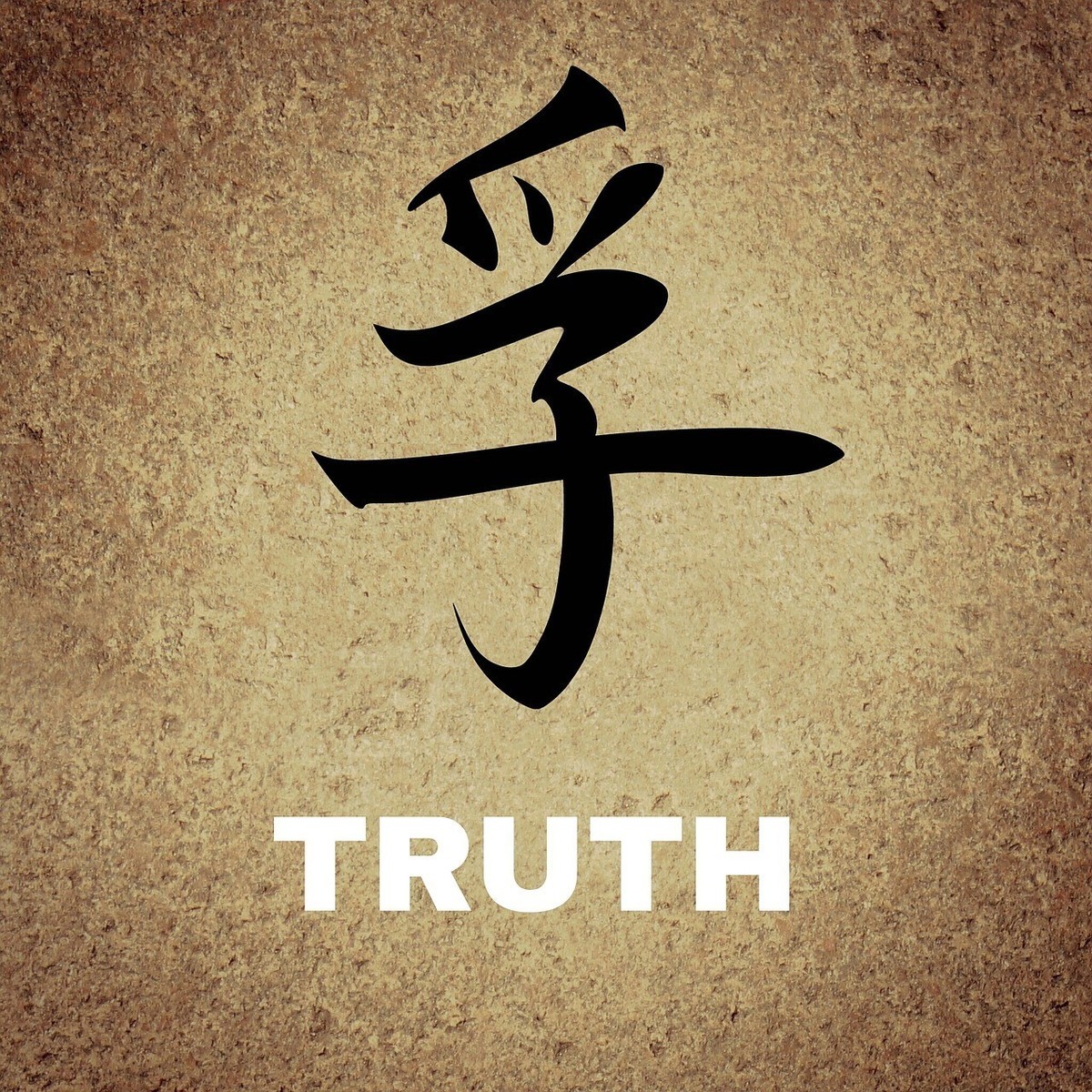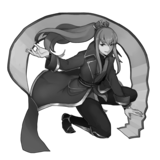周瑜--顔も性格も美周郎
■ 周瑜--顔も性格も美周郎
周瑜--顔も性格も美周郎
三国志で最も知られているイケメンと言えば、やはり周瑜です。演義でのあだ名は「美周郎」。今で言えば、
「美しき周さん」
となります。正史にも、
「立派な風采をしていた」
と記載されています。正史に、
「周瑜は音楽に非常に通じていた。どんなに酔っ払っていても、微かな間違いに気づいた」
と記載されています。美形で音楽に通じていた、現代世界に周瑜が生きていたらさぞかし女性にモテモテだったと思われます。
また、周瑜は初めの頃、孫堅のときからの譜代の臣である程普と折り合いが悪かったようです。程普から見れば若造であった周瑜を、度々侮辱していましたが、周瑜は怒ることなく、程普をたてて接していたので、程普も周瑜を認めるようになりました。
顔だけでなく、性格もイケメン。それが三国志NO1のイケメンと言われる周瑜なのです。
張松--小男だけどブサイクかどうかは!?
■ 張松--小男だけどブサイクかどうかは!?
張松--小男だけどブサイクかどうかは!?
張松は演義において、劉備(玄徳)が益州を手に入れるきっかけになった人物です。劉璋では益州を守れないと考え、曹操に益州を譲ろうと考えましたが、曹操に会った時、曹操の傲慢な態度を見て、考えを変えました。都から益州へ帰る途中、荊州に立ち寄り、劉備(玄徳)に会って、彼に益州を譲るべきだと考えました。正史でも曹操に軽くあしらわれて、曹操ではなく劉備(玄徳)に益州を譲ろうと考えを変えるところは同じです。
張松は演義では容姿について散々に書かれています。
「背が低くて、出っ歯で、鼻も低い、風采の上がらない人物」
まさに、ブサイクの典型みたいな書き方です。実際、マンガや小説の三国志を読むと、張松はそのように書かれています。では、正史においてはどうだったのでしょうか?正史で張松については
「小男で勝手に振る舞うところがあったが、才能はあった」
となっています。演義にあるようなことは殆ど書かれていません。容姿については
「小男」
であったとのみあります。ですが、三国志のような戦乱の時代においては身体が大きくて強そうというのはそれだけで見栄えが良いとされました。「小男」であったのでしたら、それだけで軽くあしらわれたり、女性にモテなかったであろうことは想像がつきます。ブサイクかどうかはわからないけど、小男であった、それが張松の正史における姿です。
荀彧--どんなに辛口でも容姿だけは認められた
■ 荀彧--どんなに辛口でも容姿だけは認められた
荀彧--どんなに辛口でも容姿だけは認められた
荀彧は曹操が中国の2/3を制覇するのに大いに功績がありました。主君の曹操や、同僚の司馬懿や鍾繇も
「荀彧の功績にはとても及ばない」
と言っていました。曹操の臣下としての功績も大きかったのですが、最終的に曹操が魏公になることに反対し、自殺したとも、憂いの内に病死したとも言われています。荀彧はあくまで漢王朝の臣下として、曹操の天下平定に尽力していたのです。自分のための天下統一を目指す曹操との決別は必然だったのかもしれません。
荀彧の容姿については正史に
「涼しげな風貌と王佐の風格」
があると記載されています。現代風に言うと
「冷静で有能な知恵袋のような外見」
とでも言えばよいでしょうか?この風貌は内外で非常に評判が高かったみたいです。
また、人の批評において辛口で有名な禰衡が荀彧を評した際には
「荀彧は見てくれだけは良いので、弔問の客をもてなすのにちょうど良い」
と言いました。決して褒め言葉ではないでしょうが、その外見については認めていたということが分かります。荀彧も三国志におけるイケメンというのに相応しいでしょう。
龐統--重用されるには身なりも大事だった
■ 龐統--重用されるには身なりも大事だった
龐統--重用されるには身なりも大事だった
龐統は演義においてもっとも身なりが悪く書かれている人物ではないでしょうか。周瑜の死後、魯粛に推薦されて孫権に会いますが、身なりが悪いということで用いられませんでした。龐統の才能を惜しんだ魯粛が推薦状を書き、今度は劉備(玄徳)の元へ向かいます。ですが、龐統の身なりが悪いため、劉備(玄徳)も重用をためらい、田舎の県令という閑職を与えます。暇を持て余した龐統は毎日酒浸りで過ごします。その噂を聞いた劉備(玄徳)は張飛(この人選はどうかと思いますが)と孫乾を派遣して問いただします。そして、張飛たちの前で才能を発揮した龐統をやっと劉備(玄徳)は重用します。
と、龐統が重く用いられるまで紆余曲折があります。そして、その原因が龐統の見た目が良くないためでした。演義でここまで書かれているのなら正史に根拠となる記載があるのでしょうか?
龐統についての正史には以下のような文があります。
「若い頃は口下手で身なりが冴えなかったことから評判を得なかった」
演義での活躍を見ると、口下手だったというのが信じられませんが、身なりが良くなかったというのは正史にも記載されている事実でした。才能には身なりは関係ありませんが、才能を活かす場を得るためには身なりの良さも重要であったという良い例ではないでしょうか。
袁尚--美貌によって両親に愛された傾国のイケメン
■ 袁尚--美貌によって両親に愛された傾国のイケメン
袁尚--美貌によって両親に愛された傾国のイケメン
演義では曹操と袁紹の戦いは官渡の戦いがメインで書かれているので、袁紹の息子たちとの戦いはそこまで多くは書かれていません。必然的に袁尚についての記載も少なく、兄弟喧嘩をして、勢力が衰えて、最終的に曹操に滅ぼされた位でしょう。また、容姿と武勇に優れていたという記載もあります。
では、正史においてはどうだったのでしょうか?正史における袁尚の記載は名門袁家の者であるので、演義よりもずっと多く記載されています。ただし、三国志の魏志ではなく、後漢書にです。魏志にも袁紹一族についての記載はありますが、メインは後漢書です。正史によると袁尚は
「生まれつき美貌があり、武勇に優れていて、父母に愛されていた」
とあります。母の家柄も良く、文句なしの後継者です。長男でさえあれば。正史の記載によると、袁譚のほうが袁尚より優れていたとあります。ですが、一族や家臣たちの多くは袁譚より袁尚を支持していました。この辺りはどちらをメインに考慮していくのが正しいのかは非常に難しく判断できません。ただ、弟である袁尚の容姿が優れていたため、兄より父母に愛され、結果的に袁家の分裂を促進したということは間違いないようです。中国には、美人すぎる女性が国王を惑わし、国を乱す元になるという意味で
「傾国の美女」
という言葉がありますが、袁尚は
「傾国のイケメン」
という事が出来そうです。