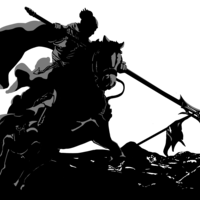30歳以上年齢の離れた縁談 その目的は何か?
■ 30歳以上年齢の離れた縁談 その目的は何か?
30歳以上年齢の離れた縁談 その目的は何か?
当時、孫尚香は10代だったと言われています。劉備(玄徳)とは30歳以上も歳が離れている…。縁談としては不自然です。話を受けた側の劉備(玄徳)、諸葛亮(孔明)は何らかの策があるのではないかと警戒します。
しかし、この縁談がまとまれば劉家、孫家に血縁関係が生まれます。北の曹操(孟徳)を抑えるべく同盟にこの上ない要素です。呉に裏の策がある可能性も感じつつ劉備(玄徳)はこの縁談を承諾します。さらに婚儀のために呉国へ訪問することも承諾します。荊州領有権で揉めている最中です。本当に危ない行動です。命懸けです…。そして、趙雲(子龍)と500人の兵を護衛に劉備(玄徳)は呉国へ向かいます。
劉備(玄徳)、喬国老に会って結婚の挨拶をする
■ 劉備(玄徳)、喬国老に会って結婚の挨拶をする
劉備(玄徳)、喬国老に会って結婚の挨拶をする
呉国に到着した劉備(玄徳)はまず喬国老という人物を訪問して結婚の挨拶をします。喬国老は絶世の美女と言われた大喬、小喬の父親です。大喬が孫策(伯符)に嫁いでいる関係で孫家とは血縁関係になっています。また、小喬も呉軍大都督周瑜(公瑾)に嫁いでいますから、呉国においては並々ならぬ地位にある人物です。
喬国老はこの縁談に大いに驚きます。こんな重要な話…「家族」たる喬国老が「聞いてなかった」のです(笑)。彼は早速、孫尚香の母親(あたり前ですが孫権の母親でもある)に問い合わせます。そして母公もビックリ!「何で10代のかわいい姫が50歳近くのオヤジに嫁がなければならないのか」呉国大騒ぎです!!
当然、孫権(仲謀)が呼び出され事情を問われます。そしてこれが劉備(玄徳)暗殺のための政略結婚であることを聞き激怒します。「妹の結婚を口実に暗殺を計画するなど、例え成功しても孫家末代までの恥である」と、その怒りは激しいものでした。母公は言います「劉備(玄徳)が我が娘(孫尚香)の夫としてふさわしいかどうかは私が直接会って判断します」。母として当然の発言です。これで、この縁談は「政略結婚」でなくなった訳です。
劉備(玄徳)が最初に喬国老を訪れるように指示したのは諸葛亮(孔明)でした。どこまで見通していたかは不明ですが、母公と喬国老を動揺させてしまったために、劉備(玄徳)暗殺計画の企ては大っぴらに実行できなくなったのです。このような動きを諸葛亮(孔明)は予測していたのでしょうか?ホントに恐ろしい人物です。
甘露寺にて 母公と劉備(玄徳)の面会
■ 甘露寺にて 母公と劉備(玄徳)の面会
甘露寺にて 母公と劉備(玄徳)の面会
後日、甘露寺にて劉備(玄徳)は母公に面会します。当然初対面ですが母公は劉備(玄徳)を絶賛します。
「温和にしてへつらわず、素晴らしいおのこ(男)ですこと」
これで結婚確定です。ちなみに喬国老も劉備(玄徳)の人品に感嘆し、この結婚に大いに前向きになったそうです。この辺りは政治戦略、損得勘定を抜きにした気持ちの良いエピソードです。
母公の発言を受け、歓迎の宴が催されますが甘露寺内には殺気を帯びた兵があちこちに伏せられています。母公の気持ちが変わる…あるいは劉備(玄徳)に何かしらの粗相があれば直ちに襲い掛かろうと…。気配を察した趙雲(子龍)は周囲に睨みを効かせます。極限の緊張状態が続きます。しかし、それを察した劉備(玄徳)は言いました。
「母公、玄徳の命を欲されるならば、どうか私にも剣を持って戦わせてくだされ」
これで伏兵の存在が露見。母公は怒り心頭で孫権(仲謀)を呼びますが、「今日はめでたい席だから」という劉備(玄徳)のとりなしで「伏兵を指示した犯人」を特定することもなく(孫権に決まってますが…)伏兵は取り除かれ、そのまま「めでたい宴席」が継続されます。
劉備(玄徳)には4人の妻と3人の息子がいた
■ 劉備(玄徳)には4人の妻と3人の息子がいた
劉備(玄徳)には4人の妻と3人の息子がいた
ちなみに劉備(玄徳)には、4人の妻と、3人の息子(養子の劉封は除く)がいます。曹操(孟徳)は13人の妻、子供は30人以上と言われていますので、それに比べるとかなり少ないです。劉備(玄徳)は年齢を重ねるまで長らく安定した領土を持たず、子孫を残すに適した環境を持てなかったことが原因と言われています。
夫人のそれぞれの名は「麋夫人」「甘夫人」「孫夫人」「呉夫人」です。
糜夫人は劉備(玄徳)が徐州太守であった頃に娶った女性で家臣の糜竺(子仲)の妹、甘夫人は色々な三国志の物語で「芙蓉姫」と称されて登場する人物です。阿斗(後の劉禅)を産んでいます。そして今回登場する孫尚香が「孫夫人」、劉備(玄徳)が蜀に入った後に娶ったのが「呉夫人」です。その名前から孫尚香と間違われがちですが別人で、蜀の武将呉懿(子遠)の妹です。
なお、語られる事の多い208年の長坂の戦いにおいて曹操軍に追われて負傷し、阿斗を趙雲(子龍)に託して井戸に身を投じたのは「糜夫人」です。
贅沢三昧にて劉備(玄徳)を堕落させる計
■ 贅沢三昧にて劉備(玄徳)を堕落させる計
贅沢三昧にて劉備(玄徳)を堕落させる計
甘露寺での劉備(玄徳)暗殺にまんまと失敗する孫権(仲謀)。そもそも計略で始めた劉備(玄徳)との縁談。このままでは本当に自身の妹(孫尚香)が劉備(玄徳)と結婚してしまいます。そこで、孫権(仲謀)は家臣の進言を取り入れ、「婚礼の祝い」と称して劉備(玄徳)を徹底的にもてなし、「贅沢漬け」にします。劉備(玄徳)の居宅を四季折々の草木で覆うよう造園し、事あるごとに酒宴を行い、侍女を侍らせ…劉備(玄徳)を堕落させ孫尚香が愛想を尽かすよう仕組むのです。
若かりし頃から母親思い、関羽(雲長)、張飛(翼徳)と挙兵後は苦難続きの劉備(玄徳)です。「贅沢の味」に免疫のない彼は急速に堕落して行く…孫権(仲謀)の策は成功するかに見えましたが、ここでも「諸葛亮(孔明)の策」が効力を発揮します。趙雲(子龍)が「曹操(孟徳)が軍備を整え、50万の兵でを再び狙っている」と進言させるのです。
これで劉備(玄徳)は我を取り戻し、荊州に帰ることを決断します。「堕落の計」も失敗です。
諸葛亮(孔明)の忠告 一国が一国を謀るのもよし
■ 諸葛亮(孔明)の忠告 一国が一国を謀るのもよし
諸葛亮(孔明)の忠告 一国が一国を謀るのもよし
劉備(玄徳)は呉脱出を図りますが、当然、追手がかかります。呉の将校にとってみれば、劉備(玄徳)を呉国内に留めておきたい(隙あらば暗殺!)でしょうから…。しかし、ここでも諸葛亮(孔明)の策によって逃亡が成功。そして諸葛亮(孔明)直々にお出迎えとなります。そして、追って来た呉の武将たちに言います。
「周瑜(公瑾)に伝えよ。荊州はもはや一国。一国が一国を謀るのもよし、それも立派な外交であり戦略である。しかし、女性を用いて謀るなどこの上ない下策。二度とこのような策を用いることなかれ。」
まとめ
■ まとめ
まとめ
劉備(玄徳)と孫夫人の仲は悪くなかったようです…と言うより夫婦としての繋がりはむしろ強かったです。それは劉備(玄徳)の呉脱出の際、孫夫人が荊州に同行しているところからも分かります。政略結婚として始まった縁談でしたが、結局、劉備(玄徳)は喬国老、孫夫人の母親、そして孫夫人自身の信頼を取り込んだところは流石でした。しかし、後年、孫夫人は呉の計略(母公が病であるとの偽手紙)によって単身で呉に帰国。以降、劉備(玄徳)に再会することはありませんでした。そして、劉備(玄徳)が夷陵の戦いに敗れ、その心労が元で亡くなったことを聞くと、自らも長江に身を投げたとも言われています。
この政略結婚の最大の被害者は孫夫人だったのかも知れません。なんだか切ないですね。