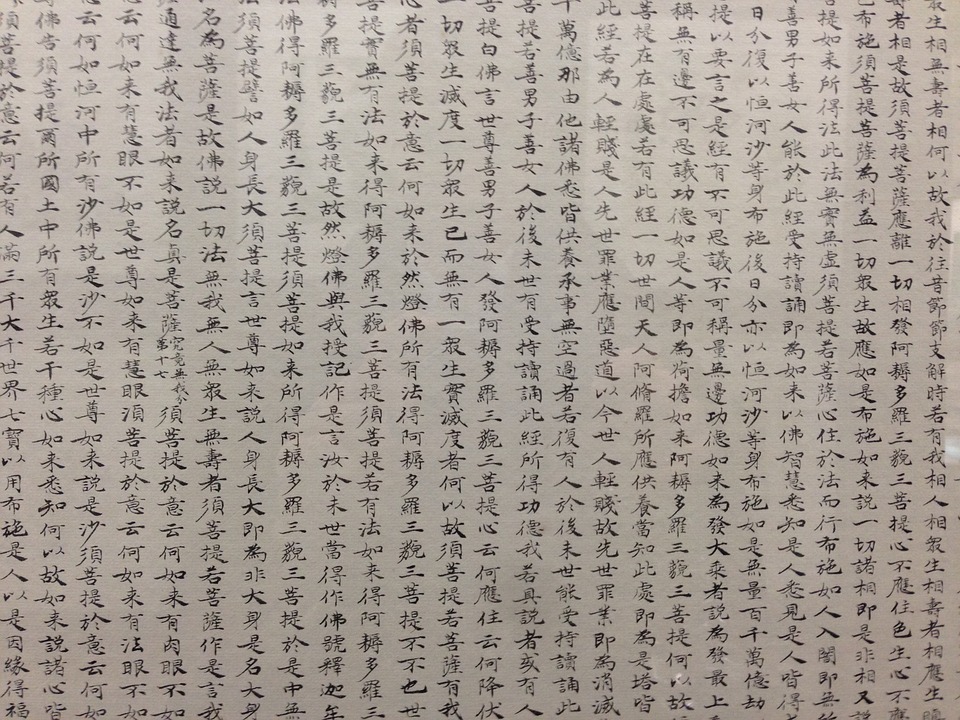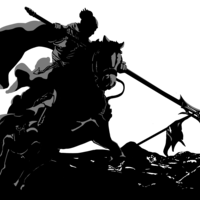学問を学び、人望も厚く数多くの官職に推挙される
■ 学問を学び、人望も厚く数多くの官職に推挙される
学問を学び、人望も厚く数多くの官職に推挙される
盧植は若かりし頃、190センチを超えるほどの大柄な体格をしており、とても威厳があったといいます。豪族ながら儒学に精通した馬融に師事し、めきめきと才能を開花させていきます。盧植は世の中を救うのに何が必要なのかを常に考えており、博学さと剛毅を兼ねていたので、人望も厚く、周囲から一目置かれた立場にありました。
盧植の人柄を知った各州郡から士官の誘いが数多くありましたが、私利私欲に走ろうとする官職たちには従わず、盧植はすべて断っています。盧植は文武に秀いていたので、士官の声は多く上がりますが、その中でも一度引き受けたのは、蛮族が反乱を起した九江の太守でした。
この反乱を抑えると、盧植は病と称して太守の官職を辞しています。その後は故郷の幽州涿郡に戻り、学問を指導するようになっていきます。そこには、若き劉備(玄徳)や公孫サンが学びにやってきました。
劉備(玄徳)が漢王朝の復興を目指し、幾度となく領地を奪取できる機会があったにも関わらず、周囲を裏切るような行為ができなかったのも、盧植の教えを守ったからともいえるでしょう。
中央に仕えて将軍として軍を率いる盧植
■ 中央に仕えて将軍として軍を率いる盧植
中央に仕えて将軍として軍を率いる盧植
しばらく学問を教える隠居生活がつづきますが、再度九江近郊で反乱が起きたのをきっかけに、かつての手腕を期待されて、廬江太守に再度任命されました。その後、盧植は中央に招かれ、霊帝に仕えています。
当時の朝廷は宦官が主導権を握り、霊帝は傀儡として祀られていました。盧植はこれを憂いており、政治を正すように霊帝に進言しますが、従うことはありませんでした。
184年に黄巾の乱が起きると、盧植は将軍として軍を率い、乱の首謀者である張角の討伐に向かいます。盧植は戦略にも優れた才能を発揮し、多くの反乱軍を破って、黄巾の乱の終結に貢献しています。
監察官に貶められる
■ 監察官に貶められる
監察官に貶められる
盧植は張角が逃げ込んだ城を包囲し、一気に攻めようとしたところ、霊帝から監察官が派遣されてきます。この監察官は賄賂を要求したので、盧植に毅然とした態度で退けます。これを恨んだ監察官が霊帝に虚偽の密告をしたため、霊帝は激怒し、盧植は逮捕されてしまいます。
盧植は官職を剥奪されて罪人となり、都へと護送されていきます。しかし、黄巾の乱が平定されると、ともに戦った皇甫嵩によって無実が証明され、盧植は官職に復帰することができました。当然といえばそうですが、弁明が利かないこの時代において、官職に復帰できたのも、日ごろの人徳がものをいったのでしょう。
三国志演義では劉備(玄徳)と遭遇する
■ 三国志演義では劉備(玄徳)と遭遇する
三国志演義では劉備(玄徳)と遭遇する
この逮捕されるいきさつでは、小説の三国志演義でも取り扱われており、義勇軍として参戦していた劉備(玄徳)一向と遭遇しています。劉備(玄徳)は理不尽な扱いを受けている師匠を見て、以下に政治が腐敗しているかを目の当たりにします。
劉備(玄徳)と参戦していた張飛は、持ち前の怪力で盧植の檻を壊そうとしますが、罪人を助けたとあっては、後の劉備(玄徳)が困ることになるとして、盧植は張飛を一喝しています。その姿をみて、劉備(玄徳)は涙をこらえて師匠を見送ることになっています。
このシーンでは盧植の人柄と、張飛の男気な一面も垣間見えています。
董卓との対立
■ 董卓との対立
董卓との対立
189年に霊帝が崩御すると、大将軍の何進と十常侍といわれる宦官たちで権力抗争が勃発します。何進の妹(何皇后)が霊帝の子どもを生んでいるので、次期皇帝を自分の甥に継がせたいと考えていました。宦官の中には何進の勢いを止めるため、その甥である劉弁よりも妾が生んだ劉協を即位させる意見が多く出ていました。
何進は大軍を動かせるので、いつ自分たちが襲われるか心配だった宦官たちは、何皇后に近づき、劉弁を即位させる代わりに、何進と和睦させてほしいことを訴えています。自分を皇后に取り立ててくれた宦官たちに恩義を感じていたので、これを受け入れます。この劉弁が小帝として即位し、劉協は陳留王になり、何進や何太后(何皇后)の地位は安泰に映るようになります。しかし、宦官を討ち破るために和睦を受け入れようとしなかった何進は、妹にも圧力をかけるために、各地の将軍たちを呼び寄せます。
この中には西涼出身で、狂暴な董卓も含まれていました。盧植は董卓の性格を熟知していたので、何進の行動を批判し、必死に止めようとしますが、何進は従いませんでした。
油断した何進は宮中で暗殺されてしまい、安堵した宦官たちでしたが、今度は袁紹と袁術が何進の兵を借りて、宮中に攻め込みます。この時、まだ幼い帝を抑えた勢力が次の権力を手中にできるとあって、血眼になって連れ去ろうとしますが、盧植はこの危機をいち早く察知し、帝を守るために大斧を持って奮戦しています。
董卓によって逮捕されるも人望によってまたも助かる
■ 董卓によって逮捕されるも人望によってまたも助かる
董卓によって逮捕されるも人望によってまたも助かる
宮中の混乱を機に、小帝や陳留王は董卓によって保護されるようになります。帝を手中にした董卓は実権を掌握して、鮮明な陳留王を帝にしようと企みます。少帝を廃しようとした董卓の暴虐ぶりに、周囲から反論をするものもなく、唯一盧植が猛反対し、董卓の暴挙を正そうとしました。
正義感というよりも、己の信念が董卓の専横を許さなかったといえます。さすがに董卓も激怒して、盧植を捕えて処刑しようとします。しかし、儒学の権威として名高く、人望が厚い盧植は、宮中に仕える多くの学者や官職たちによって助命されます。実権を掌握したばかりの董卓も、この時ばかりは怒りを鎮めて免職だけに留めています。
盧植は董卓の元にいれば、その命を不条理に奪われると感じ、病と称してすぐに都から逃げ去ります。故郷の近くまで逃げようとし、その道中に董卓が追手を差し向けていきますが、無事にたどり着いています。
親子三代に渡って優秀な一家
■ 親子三代に渡って優秀な一家
親子三代に渡って優秀な一家
盧植はその後、袁紹に招かれて参謀となり、192年に死去しました。盧植の跡を継いだ盧イクや孫にあたる盧欽は、盧植に負けない存在として官職に就き、活躍していきます。その人望は盧植に勝るとも劣らないものとして、その血を後世に伝えています。
親子三代に渡って優秀な一家というのは、盧植によって成し得た、勉強をして「世の中を救いたい」という強い気持ちの表れといえる部分が大きいでしょう。