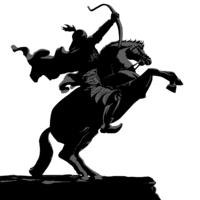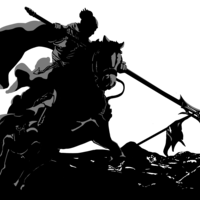零陵郡の攻防 力の差を認識できなかった劉延
■ 零陵郡の攻防 力の差を認識できなかった劉延
零陵郡の攻防 力の差を認識できなかった劉延
劉備軍が最初に侵攻したのは零陵でした。太守劉度は降伏を考えていましたが、息子の劉度は猛将刑道栄を用いて劉備軍を蹴散らしてみせると主張します。議論の末、劉延、刑道栄率いる零陵軍が劉備軍を迎え撃つ事に。しかし、刑道栄は張飛(翼徳)にあっけなく敗れ、捕らわれてしまいます。
ここで諸葛亮(孔明)が策を講じます。捕えた刑道栄に「劉度を生け捕って来ればお前(刑道栄)は殺さない。さらに劉備軍で重く用いてやる」と伝えます。釈放された刑道栄は零陵軍に戻りますが、諸葛亮(孔明)に服する気などなく、劉延に夜襲を進言します。この辺の行動からして恩知らずの小人。結局、夜襲は失敗に終わり刑道栄は殺され、今度は劉延が捕らわれてしまいます。
劉延が捕らわれたことを知った劉度は即座に降伏。零陵郡は劉備(玄徳)の支配下に入ります。
この攻防は、そもそも国家(中国)の歴史を左右する曹操(孟徳)との戦いを続けている劉備軍と一地方軍たる零陵軍との「力の差」を認識できなかった劉延の浅はかな考えが招いた敗戦でした。無謀でしたね。
劉度をそのまま零陵太守に これは寛大な処置か
■ 劉度をそのまま零陵太守に これは寛大な処置か
劉度をそのまま零陵太守に これは寛大な処置か
劉備(玄徳)は劉度を殺さなかったばかりか、そのまま零陵太守を続けさせます。そして劉延を劉備軍に組み込みます。これは「寛大」とも受け取れますが、実際には「効率的」と表現する方が近いでしょう。劉度を殺さないことで零陵の民衆に対する劉備(玄徳)の「義」は保たれますし、劉延を劉備軍に組み込むことで、暗黙の「人質」を取るような形になります。これで劉度が反乱を起こすことはできません。劉備軍にとっても、人材を「現地調達」できれば元の人材を割かずに次の地(桂陽郡)の攻略に向かえます。降伏したばかりの劉度が心服しているとは考え難いですので、まさに「効率的処置」と言えるでしょう。
桂陽郡の攻防 実戦も計略も格の違いが浮き彫り
■ 桂陽郡の攻防 実戦も計略も格の違いが浮き彫り
桂陽郡の攻防 実戦も計略も格の違いが浮き彫り
劉備軍侵攻の報を聞き、桂陽郡太守趙範も劉度同様に降伏を検討しますが、桂陽郡の将、陳応が趙範を説得し劉備軍(総大将趙雲)と交戦します。しかしこちらもあっけなく決着します(劉備軍勝利)。元々戦う気のなかった太守趙範は直ちに降伏、劉備軍の桂陽入りを歓迎すると称して酒宴を行いますが、ここでちょっとした騒動が起こります。
酒宴の際、趙雲(子龍)は歓待を受けますが、そこに一人の美女が現れます。その女性は趙範の兄の嫁で、今は未亡人でした。そのため、趙範はこの女性を趙雲(子龍)に娶(めと)らせようと紹介しました。すると、趙雲(子龍)は激怒します「そもそも兄嫁を酒宴で接待させること自体、礼を欠く(女性に対して)のに、それを男(趙雲自身のこと)に薦めるとは言語道断!」と言い放って趙範を殴ってしまいます。
これを逆恨みした趙範は後日、降伏していた陳応に協力させ、趙雲(子龍)に夜襲を企てますがあっけなく露呈。逆に趙範が再度捕らえられることとなります。
兄嫁騒動から見る趙雲(子龍)の忠誠心
■ 兄嫁騒動から見る趙雲(子龍)の忠誠心
兄嫁騒動から見る趙雲(子龍)の忠誠心
こうして桂陽郡は劉備軍によって平定されますが、劉備(玄徳)は「美人なら嫌う者はおるまい。私が仲人となってその美人を娶らせようか」と趙雲(子龍)に相談しますが、趙雲(子龍)は固辞します。趙雲(子龍)は「占領したばかりの桂陽で私がその地の女性を妻に娶れば、権力に任せて女を奪ったと民衆に誤解されかねません。臣下である私がそのような誤解を受ければ、それは当然、我が君(劉備のこと)の義にも影響します。美人と言えども、そのようなリスクを冒してまで娶りたいとは思いません」と言いのけます。
まさに「忠義の人」の「まっすぐな言葉」です。
武陵郡の攻防 零陵、桂陽とは異なる展開
■ 武陵郡の攻防 零陵、桂陽とは異なる展開
武陵郡の攻防 零陵、桂陽とは異なる展開
次に劉備軍は武陵郡に侵攻します。武陵太守は金旋(元機)。零陵、桂陽の時とは違い、太守金旋(元機)自身が劉備軍を迎え撃つと言い出します。しかし、これを武将の鞏志が反対、「我が武陵軍と劉備軍との力の差は明らか。零陵、桂陽の前例もあり、むやみに民を戦火に巻き込み、将兵の命を奪うことは避けるべきである」と主張します。
金旋(元機)は「武将の身でありながら臆病風に吹かれおって!」と鞏志をののしり、裏切りの疑いもかけて打ち首にしようとしますが他の部下たちに諫められます。しかし、鞏志は投獄され、金旋(元機)自身が劉備軍に対峙します。劉備軍総大将は張飛(翼徳)。
どう考えても勝敗は明らかです。これまたあっけなく張飛(翼徳)が勝利します。
命からがら逃げる金旋(元機)。やっとの思いで武陵城に辿り着きますが城門は開きません。そして、城壁の上で姿を見せたのは鞏志でした。
鞏志は言います。
「私は民衆と相談しました。あなた(金旋)は実力の差が明らかなのに民を戦火に巻き込み、多くの人々の将兵の命を奪った。あなたに太守の資格はない。今日から武陵は劉備(玄徳)様にお渡しする。」
そして、金旋(元機)は弓矢で射殺されてしまいます。鞏志は金旋(元機)の首を持って劉備軍に投降。張飛(翼徳)は武陵城を攻撃することなく入城し武陵郡は陥落します。
武陵郡の攻防においては、金旋(元機)が戦いに敗れて戻った際に投獄されていた鞏志が城壁で待ち構えていたところがすべての答えでした。投獄されたいたはずの鞏志が牢から出され、金旋(元機)を待っていた訳ですから…これは「民衆(将兵も含め)の金旋(元機)に対する静かな反乱」です。
後日、この鞏志の行いを評価した劉備(玄徳)は彼を武陵太守に任じます。
このように「民衆の事を真摯に考える人が正しく評価される」のは当たり前ですが、三国志の時代のような乱世では必ずしもそうでない場合も多いです。そんな中での武陵郡の出来事は愉快な事例のひとつです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
零陵、桂陽、武陵の荊州南部侵攻は劉備(玄徳)が初めて「有利な立場で戦いを進める局面」というところが、三国志のこれまでの展開と大きく異なります。劉備(玄徳)がこれまで大事に守ってきた仁愛の情もしっかりと発揮され、また、零陵での戦い後の人材配置など諸葛亮(孔明)の現実的な采配も見所です。
それまで、董卓(仲穎)、呂布(奉先)、袁術(公路)等々の「弱肉強食」「裏切り」「勝てば官軍」といった行動、曹操(孟徳)の帝を利用した専横…乱世ですから致し方ない面もありましたが、やはり何となく後味の悪い展開が三国志の主流となっていました。
劉備軍の荊州南部侵攻については「勧善懲悪」的な愉快な場面が多く、安心してその展開を見守れます。