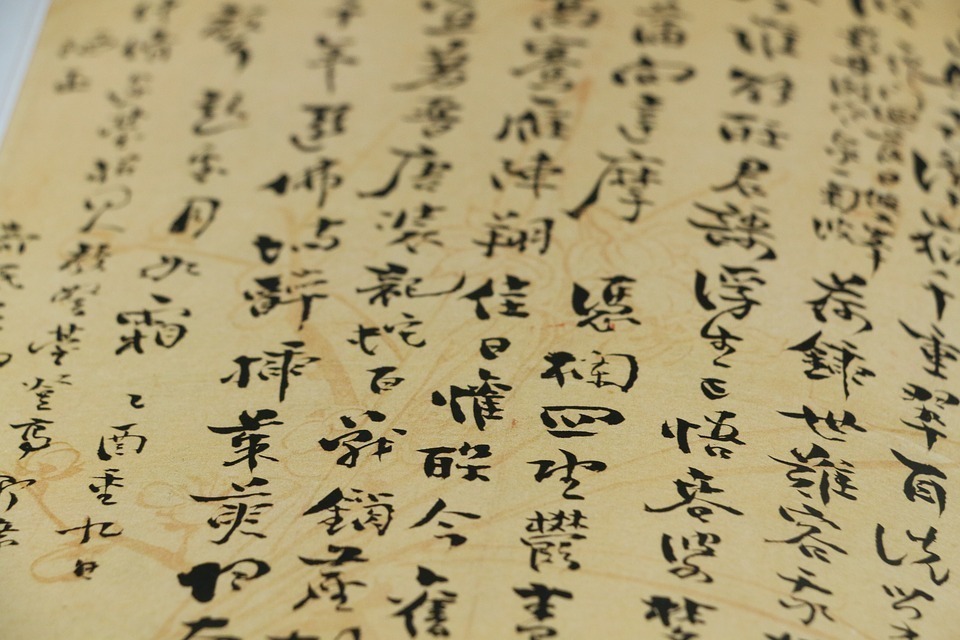曹操(孟徳)の器について
■ 曹操(孟徳)の器について
曹操(孟徳)の器について
曹操(孟徳)のエピソードはいい面も悪い面も多数あり、やはり三国志演義での敵役にピッタリです。しかし彼は董卓(仲穎)のようにただ横暴でワンマンだったというわけではありません。彼について「さすが大人物」と思わせたエピソードがあるので紹介したいと思います。
禰衡(正平)という才能に恵まれた若者がいました。しかし彼の性格はどうしようもなくいろいろな人物の悪態をつくのでした。曹操(孟徳)は「こいつは才能があるが使えない」と見限り劉表(景升)の元に送り込み様子を見ることにしました。
ある時、禰衡(正平)が作った天子へ奉る文章があまりにも素晴らしかったため、劉表(景升)は彼を気に入りました。しかし人づきあいができない禰衡(正平)に我慢できなくなり黄祖に預けました。
黄祖のところでも最初は歓迎されましたが、性格がひねくれすぎていた禰衡(正平)はまたも疎まれてしまいます。黄祖にむかって「くたばりぞこない」と悪態をつき最終的に黄祖によって処刑されました。
しかし禰衡(正平)の能力をみんなが知っていたため「黄祖は軽率な奴」というレッテルを張られるようになってしまいました。逆に曹操(孟徳)はそんな扱いづらい禰衡(正平)を殺さなかったことにより「さすがは大人物」と思われるようになったのです。
劉備(玄徳)に人望があった所以
■ 劉備(玄徳)に人望があった所以
劉備(玄徳)に人望があった所以
「三国志で人望がある人物は誰か」という質問を投げかけたら多くの人が劉備(玄徳)と答えるのではないでしょうか。彼は民を思い、民から好かれていてあらゆる豪傑を引き寄せる能力に長けていました。
彼の人望についてはまさに死ぬ間際の言葉だけで納得がいきます。彼は臨終の際に三人の子供に対し「悪小なるをもってこれをなすなかれ、善小なるをもってなさざるなかれ、これ賢これ徳、よく人を服す」という言葉を残しました。
これは「善悪どんな小さなことでも軽視するな。どんな小さいことでも悪いことをすれば巨悪に通じる。逆に小さな善行は忠実に行わなければいけない。賢明な言葉と仁徳が人を動かすのだ」という意味です。
彼の人望の厚さはこの言葉に忠実に生きた証だといえるのではないでしょうか。
宴会を中断させるのを最も嫌った関羽(雲長)
■ 宴会を中断させるのを最も嫌った関羽(雲長)
宴会を中断させるのを最も嫌った関羽(雲長)
蜀で宴会好きと言ったら真っ先に思い浮かぶのは酒豪の張飛(翼徳)ではないでしょうか。豪快に飲み、酒におぼれ、それゆえ失態が多い張飛(雲長)に関しては「酒を控えたら」と言いたくなってしまうほどです。しかしそれに勝るとも劣らないのが関羽(雲長)です。
ある時関羽(雲長)が敵の矢を肘に受けてしまいました。その矢には毒が仕込まれていたので「骨を削らなければいけない」と言われたのです。
言われたのが宴会時でしたが「ではここでやってくれ」という無茶ぶりをしました。
実際医者の華佗は痛み止めなしに骨を削ったのですが、それを見ていた部下達の顔色は変わります。ところが当の本人である関羽(雲長)は平然と酒を飲み談笑し続けたというエピソードがあります。
「宴会くらい止めにしてちゃんと治療すれば」と言いたくなりますが、そうはしたくなかったのが関羽(雲長)という人物なのでしょう。
実は曹操(孟徳)が一番死にかけた回数が多い
■ 実は曹操(孟徳)が一番死にかけた回数が多い
実は曹操(孟徳)が一番死にかけた回数が多い
曹操(孟徳)と言ったら三国志一の敵役として扱われることが多いです。それは三国志演義の主役が劉備(玄徳)であり、日本で一般的に出回っている吉川英治の小説「三国志」や横山光輝の漫画「三国志」はこの三国志演義が元にして作られているからです。
そしてその曹操(孟徳)は丞相(現在で置き換えると総理大臣のような者だと思ってもらえたら分かりやすいと思います)というくらいを得て魏を最強国に仕立て上げます。
強すぎて憎たらしいほどの曹操(孟徳)ですが実は何度も死にかけているのです。
最初はまだ若かりし頃。董卓(仲謀)の暴政を誰も止めることができなかったときに曹操(孟徳)が「自分が殺して差し上げましょう」と大見えを張って董卓(仲謀)の館に行きます。しかし暗殺がばれて逆にお尋ね者になってしまいます。命からがら逃げることができましたが、死んでもおかしくないという目にあいました。
董卓連合対反董卓連合の際にも攻撃を仕掛けるも返り討ちに会い味方の軍とはぐれてしまいあと少しで死ぬという目にあいました。
赤壁の戦いでも孫権、劉備連合軍に敗れ、その後もことごとく孔明の罠にかかりいつ死んでもおかしくありませんでした。しかし関羽(雲長)に見逃してもらい、命からがら逃げ伸びることができました。
普通最強の敵役はラスボスとして存在することが多いのですが、三国志の曹操(孟徳)は徐々に強くなっていくタイプの敵役です。そのため敵役ではありながらも偉大な人物とされファンが多く存在しているのでしょう。
曹植(子建)、詩の才能で自らの命を守る
■ 曹植(子建)、詩の才能で自らの命を守る
曹植(子建)、詩の才能で自らの命を守る
魏では曹操(孟徳)亡き後跡目争いが起こってしまいました。その際に争ったのが兄の曹丕(子桓)です。曹丕(子桓)は跡目争いに勝利すると、弟である曹植(子建)を呼び出して殺そうとしました。しかしその際母親の卞氏に命乞いをされたため、詩人でもある曹植(子建)に対して七歩歩く間に一首作るよう命じました。それができたら命だけは見逃してやるというのです。すると曹植(子建)は曹丕(子桓)が七歩歩く間に見事な詩を作ることができました。
しかし曹丕(子桓)は「七歩ではまだ遅い」と自ら言った約束を捻じ曲げてしまうのです。今度は「即座に作れ」と無茶ぶりをします。すると曹植(子建)は「お題をください」と言いました。曹丕(子桓)は「兄弟」をお題として一詩作れと言います。
曹丕(子桓)はその際にできた詩にいたく感動してしまい不覚にも涙を流してしまうほどで曹植(子建)を殺すことはありませんでした。これを俗にいう「七歩吟」と言います。
大ピンチでも機転を利かし「詩の才能」によって自らの命をつなぎとめた曹植(子建)はあっぱれと言わざるを得ないでしょう。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志のサイドストーリー的エピソードを紹介してみましたがいかがだったでしょうか。この話を知らなくても本編を楽しむことができますが、こういったエピソードを知っておくことで人物を掘り下げて知ることができ、より本編を楽しむことができるのではないかと思いました。細かいサイドストーリーを集め推しメンを作るとより三国志に熱を上げることができると思います。