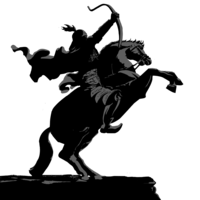三国志の時代では「魏・呉・蜀」の三国が常に歴史の中心にいました。この三国を中心に争いが起こったり、時に同盟を結んだりなど様々な駆け引きが行われてきました。三国にはそれぞれのお国柄とも言える特徴があり、その国の内側を知っていれば、さらに三国志が面白くなります。そこで今回はそんな各国のお国柄を分かりやすいように人に例えてご紹介します。
魏
■ 魏
魏
三国志の中でも最も大きな領地を所有しており、優秀な人材や強靭な武将なども揃っていました。そのトップに立っていたのが魏の中でも有名な曹操(孟徳)です。魏は曹操の思うままに進んでいき、発展を遂げていく国であるため、曹操の性格を把握しておく必要があります。
曹操は三国志の歴史で言えば嫌われ役のような人でしょう。曹操は自分が正しいことをしていると思えば大虐殺などをも厭わない性格の持ち主でした、そのため、蜀の劉備(玄徳)ファンなどからすれば確実に嫌いなキャラでしょう。しかし、曹操は戦場においてはとても勇ましく誰よりも頼れる男でした。
曹操自身がまさに魏という国を表していると言っても過言ではありません。曹操は頭も切れて、戦闘の才能もあったことから乱世を生きていくことができたと言われています。
さらに、曹操は自分の軍勢より大きい軍勢にも果敢に立ち向かっていき、絶対に勝てないと思われる戦況も覆すことができるのが最も優れた才能と言えるでしょう。そんな曹操のもとに多くの優秀な人材が集まったのも納得と言えるでしょう。
まさに魏は人に例えるとエリートタイプと言えるでしょう。様々な才能を持っていて、難しい問題にも立ちむかい、それをクリアしていくという超優秀な人間に例えられます。しかしそんな優秀な人間も調子が悪いという時もその時に身を滅ぼすという展開もあります。決して完璧な人間などいないということが言えるでしょう。
呉
■ 呉
呉
呉は熱意を持った男たちが集まった国でもありました。野望家が特に多いことから様々な野望を持っていた人が多いです。そんな呉の中で実権を握り続けて、君主として立ち続けていたのが孫策や孫権のような孫家の人たちです。孫家の人たちを中心に呉は大きくなっていきます。そのことから孫呉と言われるようになっていき、建立してからも勢いをつけていきます。
孫呉は天下統一のためにその身を犠牲にしながらも戦場にかけるような熱意の塊の国でした。どんな手を使ってでも天下統一をするというとにかく荒々しい国と言っても過言ではありませんでした。そのため、とにかく戦場で猛威を振るっている武将が多かったのも事実です。
その中でも小覇王と呼ばれていた孫策は特に戦場ではかなりの強さで圧倒していました。軍師などの頭の切れる人たちもいましたが、それが隠れてしまうほど勇猛な武将であったと噂されています。
蜀と同盟を結び、南下してくる魏を討伐し追い返したというエピソードがありますが、その後の呉の行動でいかにして天下を手にするためになんでもするという気持ちだったかがわかります。
呉は蜀と同盟を結んでいましたが、蜀と土地の問題でもめていました。荊州という蜀との間の土地でどちらが所有すべきかという問題でもめていたところ、荊州を守っていた蜀の武将である関羽を策にはめて処刑します。今まで戦っていた味方でも邪魔となればあっという間に手にかけます。
自分にとって不都合なことがあればどんな状況であれ、自分に有利になるように動くというのが呉の特徴とも言えるでしょう。血の気が多い分、こういったことも躊躇なく行えるというのも長所とも言えるかと思います。その分、軍師に負担が掛かり次々と軍師などが病を抱えていくデメリットもあります。
呉はとにかく自分を信じて思うがままに進む冒険家タイプとも言えるでしょう。しかし、その分周りに迷惑をかけることも多く、周りを良い方向にも悪い方向にも導くようになるかと思います。頼れる上司のような性格の人に例えるのが良いかと思います。
蜀
■ 蜀
蜀
蜀は三国志の中でも最初に滅びたとされる国家です。劉備(玄徳)という武将が蜀を牽引し続けましたが、病に倒れたことをきっかけに蜀の勢いは次第になくなってしまいます。劉備(玄徳)が亡くなったあと、二代目の皇帝であり、劉備(玄徳)の子供である劉禅が蜀を収めますが魏に攻め込まれた際に無血開城という形をとって魏に下ることになります。
そんな蜀ですが、とにかく平和のために尽力していたと言えるでしょう。特に自国の民を安全や平和な暮らしを優先しており、そのために戦を行っていたということが多いです。民が危険な目にあったり、戦火に巻き込まれそうな時は民を誘導しながら本拠地を変えるなども行っていました。とにかく民の安全を優先にして政治を行っていたと言えるでしょう。
蜀を率いていた劉備自身が人に対する人徳を大切にする人で、特に自国の武将や民には愛情を注いでいました。また、同盟を一時期組んでいた呉に対しても、手厚く関係を結んでいました。しかし、その信頼が仇となり、義兄弟の契りを交わしていた関羽が呉によって打ち取られてしまいます。周りを大事にしすぎたり、仁をもって接するあまり失敗するという傾向もありました。
最終的には魏に下るという選択を行いましたが、この際にもまだ戦えるという蜀の誇りを忘れない軍勢がいましたが、当時当主となっていた劉禅は争わずに話し合って解決する術を探していました。その結果、誰も傷つかずに済む無血開城という形になりました。
蜀はまさに平和主義者とも言えるでしょう。決して自分が損をする立ち回りになったとしても周りが平和に終わるのであればそれで満足するという特徴があります。自分が言いたいことがあったとしても、それを言って事態がややこしくなるのであれば口に出さずに飲み込んで終わらせるといった内向的な性格の人と言えるでしょう。
まとめ
■ まとめ
まとめ
「魏・呉・蜀」という国がどんな国だったのかというのが人に例えて擬人化するとよりわかりやすいと思います。それぞれの国によって、目指す天下の形も変わってくれば、周りの敵国に対する意識も変わってくると思います。国を形成する人物や抱えている野望なども把握しておけば、より三国志を楽しく感じるのではないでしょうか。