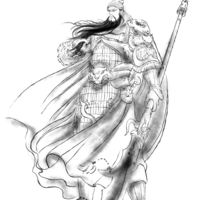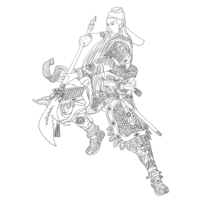董卓(仲頴)を唯一ある程度操れた漢、李儒
■ 董卓(仲頴)を唯一ある程度操れた漢、李儒
董卓(仲頴)を唯一ある程度操れた漢、李儒
董卓軍を語る上で欠かせないのが李儒です。
董卓(仲頴)から絶大な信頼を受けていて誰の言うことも聞かなかった董卓(仲頴)を唯一説得できる人物でした。
三国志の序盤で姿を消したためあまり多くを語られることはありませんでしたが、力的に荀彧(文若)や魯粛(子敬)級の知略の持ち主だったのではないでしょうか。
(もしくはそれ以上ですが個人的には周瑜や司馬懿には及ばないと思っています)董卓(仲頴)と呂布(奉先)が仲たがいした時も一人王允の策に違和感を覚え董卓(仲頴)に進言しました。
(これに関しては受け入れられませんでしたが)とにかく董卓軍がここまで大きくなったのも李儒のおかげと言っても過言ではないくらい存在感を与えていた人物です。
最強の漢呂布(奉先)
■ 最強の漢呂布(奉先)
最強の漢呂布(奉先)
三国志最強と呼び声高い呂布(奉先)がいたから董卓(仲頴)があそこまで大きな顔をしていられたと言ってもいいでしょう。
「人中の呂布、馬中の赤兎」(人は呂布が、馬は赤兎馬が最強という意味)と言われるくらいで、関羽(雲長)、張飛(翼徳)、劉備(玄徳)の三人相手でも倒すことができなかった人物です。
元々董卓(仲頴)と敵対する丁原の義理の息子でしたが、その丁原を裏切って殺すことになりました。
そして董卓(仲頴)の養子となり、それ以降董卓(仲頴)に仕えることとなります。とにかく強く戦うもの戦うものを次々と斬り落とし、呂布がいるから董卓軍を落とせないとされていました。
しかし最後は王允の策にはまり、董卓(仲頴)と仲たがいをし、最終的には董卓(仲頴)を殺してしまいました。この裏切りが無ければだれも董卓軍を倒すことはできなかったでしょうね。
先鋒で相手を落としまくった華雄
■ 先鋒で相手を落としまくった華雄
先鋒で相手を落としまくった華雄
汜水関の戦いで董卓軍の先鋒を務めたのが華雄です。5万の軍勢を率い、反董卓連合軍が出してくる猛将を次々と斬り落とし董卓軍を勢いづかせます。
相手の勢いに飲み込まれた反董卓連合軍ですが、ここで出てきたのがまだ名も知られていない関羽(雲長)でした。
反董卓連合軍の名だたる将軍から「誰だお前」と言われる中、華雄を見事斬って取りました。
これにより董卓軍は一気に旗色が悪くなったわけですが、ここで関羽(雲長)が華雄を倒せなかったら反董卓連合軍はいよいよ慌てふためき、一気に連合軍解散という危機に直面していたかもしれません。
特攻隊長にして相当な実力者だったことが伺えます。それほどの将軍を先鋒でぽんと出すことができた董卓軍はやはり凄かったとしか言いようがありません。
李傕(稚然)
■ 李傕(稚然)
李傕(稚然)
董卓(仲頴)が呂布(奉先)に殺された後、董卓軍をまとめて他国と闘い続けた際の大将軍を務めた人物です。
董卓(仲頴)、呂布(奉先)がいなくなった後でも董卓軍が一気に弱体化しなかったのは彼の功績と言えるでしょう。
董卓(仲頴)亡き後、幼馴染の郭汜と共に力を合わせていましたが、最終的にはこの二人が仲たがいをするような形で、董卓軍が崩壊したと言っても過言ではないでしょう。
しかもこの二人が仲たがいをしたのは董卓(仲頴)と呂布(奉先)のように仕組まれてのことでした。(これについては諸説ありますが)つまり同じ運命をたどったと言える反面、そうでもしなければ彼らの勢いを完璧に止められなかったと言ってもいいくらい、手に負えない将軍だったということでしょう。
彼らが仲たがいしなければこの時代の勢力図は大きく変わっていたでしょうね。
郭汜
■ 郭汜
郭汜
李傕(稚然)同様董卓(仲頴)亡き後董卓軍を支えた人物です。三国志史上最も悪名高いのが董卓(仲頴)と言われていますが、実は李傕(稚然)と郭汜はそれ以上だったのではないかといううわさもあります。
ちなみにある民は一人の董卓(仲頴)がいなくなったかと思ったら二人の董卓(仲頴)が現れたなんて言っていたくらい、やりたい放題やっていました。
つまり、やりたい放題やって財産を獲ったり、残虐極まる行為をするのを奨励した者は敵も多いがついてくるものも多いということが分かります。
とは言えそういった物達は必ず崩壊する運命にあり、結局策を練られて李傕(稚然)と郭汜が仲たがいさせられ董卓軍残党兵の弱体化は顕著になりました。
高順
■ 高順
高順
高順は董卓軍というよりは呂布に最後まで仕えた武将です。人を裏切り続けた呂布でも高順が最後までついてきたということを考えるとやはりカリスマ性はあったのだということが伺えます。
そしてこの高順ですが、ただ単に呂布にくっついていただけでなく、濮陽の戦いでは曹操をあと一歩という所まで追いつめたほどの武将です。曹操はこういうタイプの武将が好きそうですが、結局は曹操に捉えられ斬首させられてしまいました。
李粛
■ 李粛
李粛
呂布に赤兎馬を与え董卓軍に引き入れた切れ者。それだけで功績は十分と言えるのに後に董卓(仲頴)に疎まれる存在となってしまいました。
しかし、王允や呂布の董卓(仲頴)暗殺計画に乗っかり董卓(仲頴)の元へ赴きました。天子が位を董卓(仲頴)に譲りたいと言っているという嘘を付き、宮廷におびき寄せました。まんまと罠に引っかかった董卓(仲頴)はあっけなく呂布に殺されてしまうのでした。
李粛の成し遂げたことはとてつもなく大きかったものの、そこまで脚光を浴びることはなく、よほどの三国志通でない限り日本ではあまり知られていない存在です。
とは言えこういった脇役がいるからこその三国志と言っても過言ではないでしょう。なかなか憎めないやつです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
董卓軍の面々はいかがだったでしょうか。なんとなく似たようなタイプの人間が集まっていたとは思いますが、今一つ一枚岩になり切れなかったという感があります。
もちろん上記で挙げた以外でも一筋縄ではいかない武将や軍師がおり、難攻不落の董卓軍を形成していました。
もし最後まで一枚岩でいられたとしたら、他の国では太刀打ちができず、弱い国から順番に彼らに滅ぼされていったのではないでしょうか。
董卓連合対反董卓連合は虎牢関の戦い以降は激しくやり合ったという印象は薄いのですが、もし最後まで死力を尽くしきっていたら董卓軍が勝利していたのではないかと思っています
(反董卓連合は序盤からまとまりに欠けていた上、董卓軍は相当の力があったため)
しかしそうならなかったからこその三国志であり、一強でなかったために後世の人々を魅了したのだと言えるでしょう!