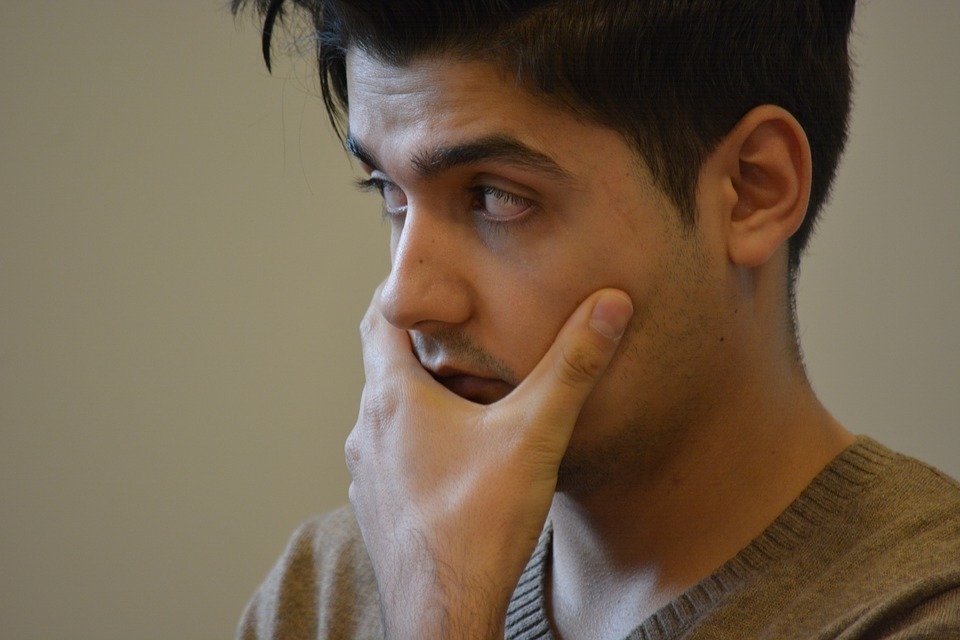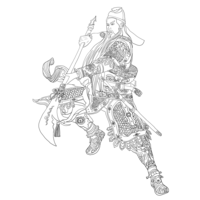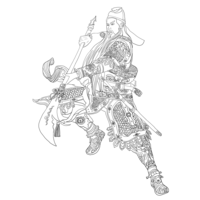陳宮(公台)の人柄について
■ 陳宮(公台)の人柄について
陳宮(公台)の人柄について
あまり知られていませんが陳宮(公台)はなかなかの天才軍師としてその手腕をふるっていました。特に正義感が強く、曲がったことが大嫌いな性格でした。しかし彼の残念なところは見る目がないということです。
陳宮(公台)が最初に目を付けたのが曹操(孟徳)でした。陳宮(公台)は曹操(孟徳)のことを「なかなかしっかりした青年将校だ」と思い目をかけていました。
そのため陳宮(公台)の元に曹操(孟徳)の逮捕命令書を贈られてきたときでも、見逃すどころか一緒に逃亡するようになりました。
余談ですが、これに関し曹操(孟徳)はとても心強かったことでしょう。もしこれが陳宮(公台)でなければ明らかに曹操(孟徳)は捉えられて董卓(仲頴)に殺されていました。
それだけでなく一緒に逃げてくれたのです。見逃されたとしてもはっきり言って曹操(孟徳)はここでゲームオーバーだったでしょう。
このことからも陳宮(公台)は自分の良かれと思ったことを信じる真っすぐな人間だったと言えます。
陳宮(公台)の決断
■ 陳宮(公台)の決断
陳宮(公台)の決断
ではなぜ陳宮(公台)は曹操(孟徳)が台頭したころ彼の横にいなかったのでしょうか。それは陳宮(公台)が曹操(孟徳)を見限ったからです。
董卓(仲頴)から逃げまとう二人は曹操(孟徳)の知人である呂伯奢の元へ厄介になることにしました。呂伯奢は「酒を買ってくる」と言って二人を家に残し、家の者に猪鍋を二人に振る舞うよう言いました。
しかしそんな呂伯奢の考えなど知る由もない二人は呂伯奢の帰宅が遅いことと、周りが騒がしいことに懸念を抱き、家の者を殺してしまいました。
気につるされていた猪を見て「誤解」だったと気づいた二人は呂伯奢の家を後にすることにしました。
両親の呵責に悩まされていた陳宮(公台)とは裏腹に曹操(孟徳)は「仕方がなかった」と割り切ってしまうのです。
これに関して陳宮(公台)は曹操(孟徳)の人間性を疑うのでした。
しかし話はそこで終わりではありません。呂伯奢の家を後にした二人はばったり呂伯奢と出くわしてしまったのです。
曹操(孟徳)は「昼間寄った店に忘れ物をしたから」という言い訳をし、その場をやり過ごしました。しばらく歩いた後、今度は陳宮(公台)に「ちょっとここで待っていてくれ」と言って呂伯奢の家の方へ行ったのでした。
陳宮(公台)が待っていると曹操(孟徳)は「騒がれたらまずいから呂伯奢も殺してきた」というのでした。
陳宮(公台)は「こいつはダメだ」と思い曹操(孟徳)と決別しました。
とにかく見る目がない陳宮(公台)
■ とにかく見る目がない陳宮(公台)
とにかく見る目がない陳宮(公台)
これだけでも十分すぎる陳宮(公台)の不幸話ですが、まだ彼の人生には続きがあります。陳宮(公台)が後に仕えた君主は呂布(奉先)でした。
三国志通の人はご存知かと思いますが、裏切りで有名な呂布(奉先)に仕えたらそれだけで「失敗じゃん」と思うことでしょう。
そしてまさにその予想通りの結末となってしまうのです。
呂布(奉先)の元でその知略を存分に発揮していったのですが、呂布(奉先)は陳宮(公台)の進言を聞くこともあれば聞かないこともありました。
特に聞かないときに大敗を喫するなど、まさに君主に足を引っ張られると言った状態になっていました。
そして最後は呂布(奉先)に渾身の策を授けるも呂布(奉先)の妻である厳氏に反対され結局敵となった曹操(孟徳)に捕まってしまいました。
結局進言を聞いてもらえないという君主たちに振り回された陳宮(公台)は見る目がなかったと言わざるを得ないでしょう。
実は才能があった陳宮(公台)
■ 実は才能があった陳宮(公台)
実は才能があった陳宮(公台)
呂布(奉先)が陳宮(公台)の進言を聞いた際の結果はことごとく成功を収めていました。そういった経緯から陳宮(公台)は天才軍師として高い評価を得ることとなったのです。しかし進言を聞いてもらえればいいのですが、聞き入れられないことも少なくなかったため結局三歩進んで二歩下がる状態でした。
結局彼の知略が他国を牛耳るほどには広がらず、「誰もが知っている天才軍師」の仲間入りになることはありませんでした。
これは私の推測ですが、陳宮(公台)はかなり優秀だったのですが、まじめすぎるあまり応用力に乏しい、存するタイプだったのではないかと思います。
曹操(孟徳)と陳宮(公台)の関係
■ 曹操(孟徳)と陳宮(公台)の関係
曹操(孟徳)と陳宮(公台)の関係
しかしほんのちょっとだけ陳宮(公台)が報われる話をさせてください。曹操(猛徳)に捉えられた陳宮(公台)ですが、そこですぐに殺されたわけではありません。陳宮(公台)の手腕を知っている曹操(猛徳)は陳宮(公台)に対して「自分の元で働かないか」という旨を伝えます。しかし曹操(孟徳)に対して嫌悪感を抱いていた陳宮(公台)は首を縦に振ることなく死を選んだのです。
もしここで陳宮(公台)が曹操(孟徳)の軍門に下り、その知略を存分に発揮していたら司馬懿(仲達)と二枚看板で両輪のごとく活躍で来ていたかもしれません。
そしてそうなったら曹操(孟徳)が生きているうちに中華を統一できていたという結果になったかもしれません。
歴史にタラレバはナンセンスかもしれませんが、そういう仮定が浮かんでくるのも事実です。
そして何が報われるのかというと、曹操(孟徳)は陳宮(公台)を刑場へ送り出す際、あふれ出る涙を抑えていたと言われています。
まだ曹操(孟徳)がぺーぺーだった頃二人で逃亡生活をしたことを思い出していたのでしょう。曹操(孟徳)は最後の最後までできることなら陳宮(公台)を救ってやりたいと思っていたのです。
しかし命乞いをしないあたりが陳宮(公台)のいいところであり、複雑な人間模様が絡み合う三国志のいいところなのでしょう。
まとめ
■ まとめ
まとめ
陳宮(公台)について少しは分かっていただけたでしょうか。
曲がったことが大嫌いで最後まで正義を貫いた陳宮(公台)はもっと称賛されてもいい人物だと思っていただけたら幸いです。
そして曹操(孟徳)を語る上でも陳宮(公台)は重要人物ですので是非とも頭の片隅にでも入れておいてください。
見る目がなく、最後までいい君主に出会うことができなかった陳宮(公台)ですが、劉備(玄徳)に使えないからこそ三国志は美しいものだと言えるのではないかと思っています。
最後まで芯を曲げなかった陳宮(公台)はやはり三国志時代の宝です!