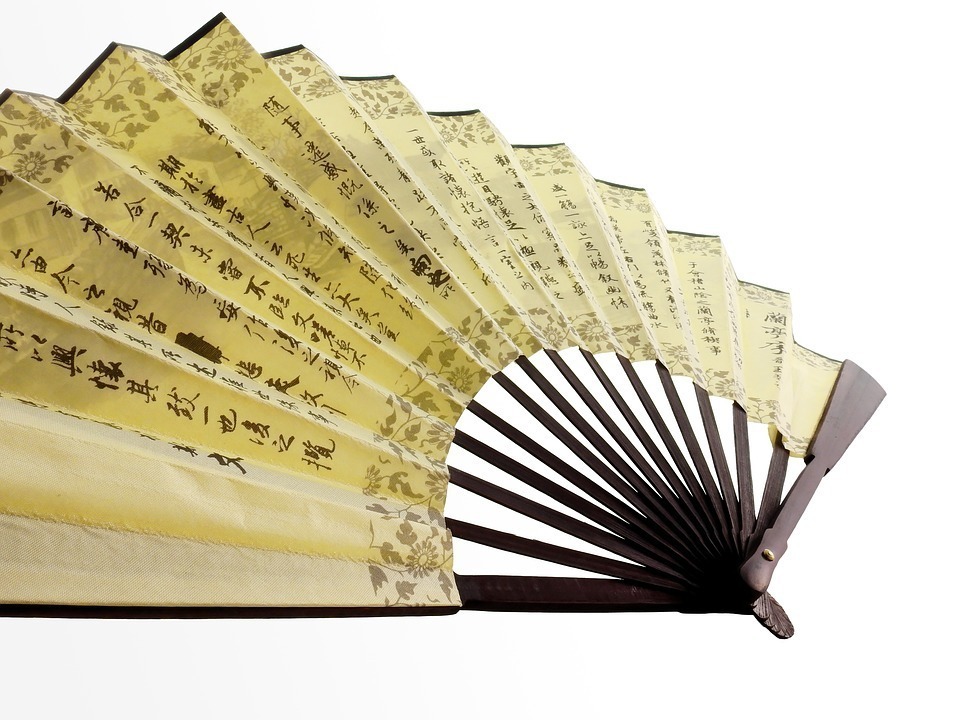曹叡の生まれ
■ 曹叡の生まれ
曹叡の生まれ
曹叡、字は元仲。魏の二代目皇帝「明帝」です。祖父はあの三国志の英雄・曹操ですね。父親は曹操の後継者である曹丕(文帝)になります。長子です。母親は三国志に登場する女性の中でも屈指の美貌を誇る甄氏です。母親の遺伝子を強く受け継いでいたのか、「天姿秀出」の容姿であったと伝わっています。もしかすると周瑜や孫策に匹敵するイケメンだったのかもしれませんね。その才能は幼い頃から祖父・曹操にも認められています。
問題は生まれた年です。204年または206年として伝わっています。「三国志正史」では204年として記されており、後に三国志に注釈をつける裴松之は206年と変更しています。わずか2年の違いですが、この2年の違いは曹叡にとってとても重要な意味を持ちます。父親が変わるかもしれないからです。
母親・甄氏の生い立ち
■ 母親・甄氏の生い立ち
母親・甄氏の生い立ち
甄氏は実は人妻でした。曹丕がそれを略奪したのです。もともとの夫は袁紹の次子・袁熙になります。甄氏の生家は帝室の子女のお守役を務めていた甄邯の末裔です。甄氏の父親は豫州上蔡郡の令に就任していました。家柄としては名門袁家とはまったくつり合いがとれません。しかし、あまりの美貌から評判になり、袁熙との縁談話が持ち上がりました。さらに甄氏は生まれたときから寝入ると何者かが玉衣をかけるという超常現象も起きています。著名な人物鑑定家の劉良は甄氏の人相を調べて必ずや后妃になると予言しました。そんないわくつきの女性だったのです。
袁熙は一目で甄氏に夢中になり、二人は結ばれます。
曹丕による甄氏の略奪
■ 曹丕による甄氏の略奪
曹丕による甄氏の略奪
袁熙は幽州の牧として本拠地の鄴を後にします。妻の甄氏は鄴に残されました。そして袁紹は「官渡の戦い」で、大軍を率いながら曹操に敗北し、病没してしまいます。その後、長子・袁譚と三子・袁尚の間で後継を巡る内紛も勃発。建安九年に鄴は曹操に包囲され落城しました。この建安九年が問題の「204年」にあたるのです。
204年8月に曹操軍は鄴の城を落としますが、その際に曹丕がすかさず甄氏を確保します。そして父親である曹操に甄氏を妻に迎えたいと申し出ます。曹丕は18歳で、甄氏は23歳。さらに甄氏の夫である袁熙は幽州で健在でした。さすがに曹操としてもいい顔はしません。しかし曹丕が執拗に主張するので曹操が折れました。とても異例なケースなのですが、甄氏は敵将の妻ながら奴隷でも妾でもなく正妻として曹家に迎い入れられました。
曹叡の誕生と甄氏の死
■ 曹叡の誕生と甄氏の死
曹叡の誕生と甄氏の死
こうして甄氏は曹叡を生みました。曹叡は220年に武徳公、221年に斉公、222年に平原王に封じられます。その間の221年に、甄氏は皇帝として即位していた曹丕によって死を賜ります。理由は謎ですが、曹丕が側室の郭氏を寵愛し皇后にしたかったためだといわれています。曹丕と郭氏の間に子はできず、曹丕は皇后となった郭氏に養育されました。ちなみに甄氏は髪をふり乱したまま、口にはぬかを詰め込まれ、棺におさめることも許されず葬られたといいます。曹丕からよほどの憎しみを受けていたことが見て取れます。
曹叡は皇太子に立てられず
■ 曹叡は皇太子に立てられず
曹叡は皇太子に立てられず
曹操をして「わが基はこの子で三代となるだろう」と評価された曹叡でしたが、曹丕の長子であるにもかかわらず皇太子に立てられませんでした。確かに曹丕も曹操の王太子に選ばれるのが遅かったのですが、曹丕は病気で重体になるまで後継者を決めていません。226年に曹丕は病没します。もしかすると曹丕は最期まで曹叡を皇太子と認めていなかったかもしれないのです。曹丕は曹叡を人前に出すのを嫌がっていたといいます。甄氏、曹叡ともに曹丕に憎まれていた可能性があるのです。実際に曹叡は暑気を理由にして曹丕の棺を見送らなかったそうです。
曹丕が重体になったために曹真、司馬懿あたりが皇太子を曹叡と決めてしまったのかもしれません。正史では重体の曹丕は曹真、曹休、陳羣、司馬懿に曹叡の補佐を託したと記されていますが、真実はわかりません。
曹叡の逆襲
■ 曹叡の逆襲
曹叡の逆襲
父親の葬儀で棺を見送らなかった曹叡ですが、育ての母である郭氏に対しても熾烈な対応をしています。郭氏は235年に病没しました。曹叡は郭氏の髪を乱させ、口にぬかを詰め、棺におさめずに葬りました。まさに実母である甄氏の復讐です。
甄氏の死がトラウマとしてずっと曹叡の心の内にあったのでしょうか。曹叡の皇后となった毛氏もまた甄氏と同じように冷遇されて死を賜っています。曹叡は実母がされた行為を自分の正妻にも行ったのです。ただし毛氏は皇后として葬られています。
トラウマによって曹叡の愛情は屈折したものになっていたとも考えられます。
諸葛亮との戦いに出陣する
■ 諸葛亮との戦いに出陣する
諸葛亮との戦いに出陣する
そんな曹叡は皇帝であるにもかかわらず蜀の北伐に対して長安に親征を行っています。ちょうど第一次北伐ですから228年のことです。蜀の皇帝である劉禅は曹叡とほぼ同じ歳ですが、出陣しようとした気配すらありません。このとき蜀の猛将・魏延は子午谷道から一気に長安を突く作戦を提案していますが、諸葛亮に却下されています。どちらにせよ親征し、見事に蜀を撃退したことになりますから曹叡の名声は高まりました。
そもそも曹丕が群臣の前に曹叡を出さなかったために、曹叡を知らない者が多かったのです。曹叡はこれでようやく二代目皇帝として認められたのかもしれません。
まとめ・曹叡は誰の子なのか?
■ まとめ・曹叡は誰の子なのか?
まとめ・曹叡は誰の子なのか?
三国志を編纂した陳寿が誤っているのであれば曹叡が曹丕の子であることに間違いはないでしょう。しかし陳寿の記しているように204年の生まれとなると話は大きく変わってきます。曹叡は袁熙の子ということになるからです。そんなことがありえるのでしょうか。そうなると袁紹の孫が皇帝に即位したことになります。曹丕が認めることはないでしょう。そもそもそれを知って曹叡のことを生かしておくはずがありません。
常識で考えるとすぐにそういった答えが導き出されるのですが、なぜ引っかかるのでしょうか。それは曹丕が甄氏を必要以上に憎んだということと、曹叡を人前に出さなかったということがあるからです。それが「曹叡・袁熙子息説」に信憑性を持たせてしまうのでしょう。
はたして真実はどちらなのでしょうか。真実は甄氏しか知らないのかもしれません。