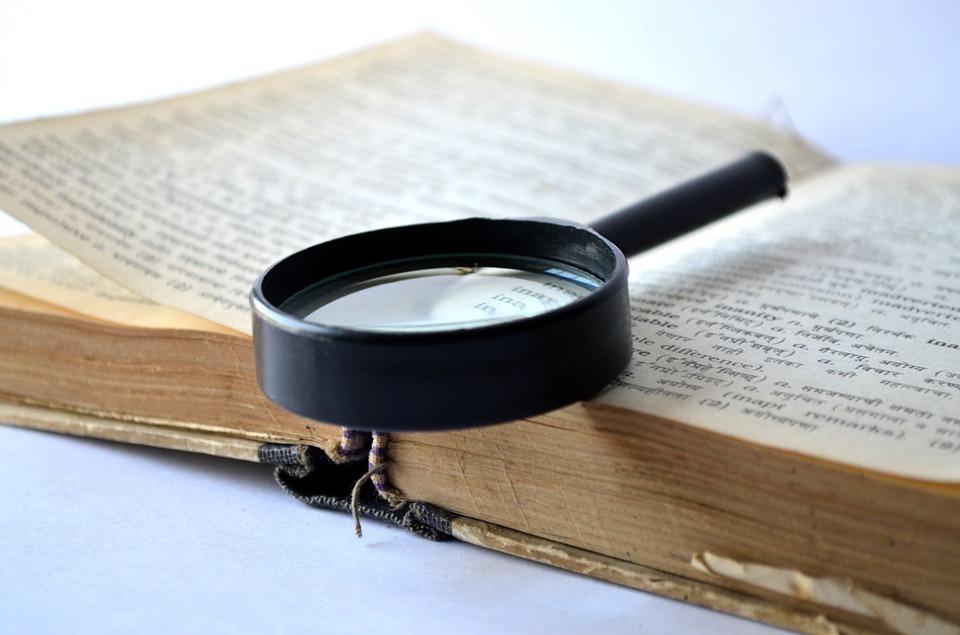天邪鬼な張昭
■ 天邪鬼な張昭
天邪鬼な張昭
張昭、字は子布。徐州の彭城国の出身です。若い頃から多くの書物に通じ、趙昱や王朗と並び称されています。その名声から、20歳の頃には孝廉に推挙されていますが、都・洛陽には向かいませんでした。さらに徐州の刺史・陶謙に茂才に推薦しましたが、張昭はこれを断ります。茂才とは官僚候補です。これに腹をたてた陶謙によって捕縛されて獄に入れられていますが、趙昱がその救援のために奔走してくれたおかげで釈放されています。無理やり仕官させられることに抵抗したためですが、陶謙のことを心底嫌っていたわけではなかったようです。病没した陶謙への哀悼の辞では「陶謙は美徳と武勇と知性を兼ね備え、剛直であり、恩愛のある統治を実践した」と褒め称えています。
孫策へ仕える
■ 孫策へ仕える
孫策へ仕える
徐州の陶謙には仕えることがなかった張昭は、徐州の混乱を避けて長江の南へ移り住みます。おそらく曹操の徐州侵略のタイミングだったのではないでしょうか。
さらに揚州刺史である劉繇を破った孫策が江東で自立を試みたときに、参謀として仕え始めています。孫策は名士である張昭を早速、長史・撫軍中郎将に任じました。孫策はわざわざ張昭の母親に挨拶にいくなどの礼を尽くしています。
張昭の名声を慕って北から多くの書簡が届き、張昭はその扱いに頭をかかえることになりました。書簡の内容はどれも張昭を褒め称えているものであり、公表するのもおかしな話です。しかし隠すのも何か企んでいると勘ぐられる心配があります。そんな心配をよそに孫策はそのことを知ってむしろ喜び、斉の桓公と宰相の管仲の関係を例にあげて、「張昭という賢才を立派に使いこなすことができれば自分も桓公並みの活躍ができる」と満足そうだったと伝わっています。
孫権へ仕える
■ 孫権へ仕える
孫権へ仕える
そんな孫策は刺客に受けた傷がもとで病没してしまいます。孫策は弟の孫権の後見になるように張昭に依頼しました。孫権に政務を執る資格がなければ張昭が代わってもかまわないとも話しています。
孫策が亡くなったことで孫権は悲嘆にくれていましたが、張昭はそんな孫権を叱咤激励し、「先人の事業を受け継いで国造りに励み、大きく発展させることが第一の勤めなのにもかかわらず、悲しみに伏せり匹夫の情におぼれているとは何事です」と厳しく戒めました。
そして孫権を馬に乗せ外出させ、新しい主君の存在を民衆にアピールしたのです。
孫権が車騎将軍代行に任ぜられると、張昭は軍師となりました。
張昭の武勇
■ 張昭の武勇
張昭の武勇
文官としてのイメージの強い張昭ですが、出陣して敵を討つことでも活躍しています。
黄巾の賊徒が反乱を起こすと兵を率いて平定しました。孫権が合肥に出陣した際には、別動隊を率いて匡琦を討っています。さらに諸将を率いて豫章郡の賊頭・周鳳を南城で打ち破っています。残念ながら張昭が兵を率いて戦ったのはこれが最後だったようです。その後は常に孫権の傍にあって智謀を用いて貢献しています。
孫権への諫言
■ 孫権への諫言
孫権への諫言
張昭といえば君主・孫権に対し、歯に衣着せぬ言いようで諫める場面を多く見かけます。時には互いに感情的になって衝突することもありました。他の群雄を見渡しても、ここまでダイレクトに主君に諫言する臣は稀です。
孫権が大好きな虎狩りも諫めています。孫権はしょげかえって謝ったそうですが、狩りをやめることはせずに特製の車を作って箱の中から虎を射ていたそうです。
酒宴で酔っ払い群臣に水をかけて盛り上がる孫権に対しては無言で帰宅し、呼び戻されると、「殷の紂王も楽しもうと思っただけで悪いという自覚はなかったそうです」と答えています。孫権は黙り込んで酒宴をやめました。
呉の丞相には抜擢されず
■ 呉の丞相には抜擢されず
呉の丞相には抜擢されず
ここまでの重臣ですから、孫権が丞相職を設けた際には、群臣はみな張昭が適任だと思っていました。しかし孫権は孫劭を任じています。言い分は「丞相は責務が重いため、優遇したことにならない」からだそうです。
そんな中で孫劭が病没します。群臣は張昭を推薦しましたが、孫権は断りました。「張昭は剛直なのでトラブルがおきるだろう。だからこそ張昭のためにはならない」と答え、顧雍を丞相に任じたのです。
張昭の諫言があまりに度を越していたのが原因だったのではないでしょうか。
徹底的に苦言を呈する張昭の覚悟
■ 徹底的に苦言を呈する張昭の覚悟
徹底的に苦言を呈する張昭の覚悟
孫権の意に逆らって諫言したために朝見を禁じられたことがありました。孫権は翌日に使者を出して参内を求めます。張昭は無礼を詫びながらも、「愚かさをかえりみずお国にお仕えするのは、心から忠節を尽くして、死してのちやむ覚悟からです、自身の栄華のために陛下のご機嫌をとりむすぶことなど断じてできません」ときっぱりと断言しています。
孫権も張昭の覚悟を知って、詫びるばかりだったそうです。
さすがは張昭ですね。ここまで開き直れるところが張昭の凄さでもあります。
信じられない孫権との衝突
■ 信じられない孫権との衝突
信じられない孫権との衝突
当然のように孫権との衝突はその後も続きます。遼東の公孫淵との外交を巡って、またも孫権と張昭の意見は分かれます。この押し問答では孫権は怒りを爆発させて剣を抜いていますが、張昭は涙を流して諫言する理由を伝えました。孫権は剣を投げ捨てて共に泣いたそうです。しかし決断を変えることはありませんでした。
張昭は憤り、病気と称して参内するのをやめます。孫権は立腹して張昭の屋敷の門を土で塞ぎました。すると張昭も対抗して内側からも土で塗り固めたのです。
外交は張昭の進言どおり失敗に終わり、孫権は張昭の屋敷を訪れて詫びるのですが、張昭は許しません。業を煮やした孫権は門に火を放ちます。それでも張昭は頑として屋敷を出ません。孫権は慌てて火を消させました。ここでようやく息子たちに抱えられて張昭が屋敷から出てきたのです。孫権は自らの不明を詫びました。
まとめ・張昭の死
■ まとめ・張昭の死
まとめ・張昭の死
孫権ですら「張昭と話すときはめったなことはいえない」と気をつかっていたわけですから、国中の群臣が張昭を畏れ敬っていました。そんな張昭はなんと81歳まで生きました。大往生です。遺言によって簡素に葬られたようです。
孫権もその葬儀に参列しています。はたしてどのような思いだったのでしょうか。まさに父を失う気持ちだったのではないでしょうか。孫権は張昭に文侯と諡しています。
こうして諫める者がいなくなった孫権は、少しずつ歯車が狂っていくのです。