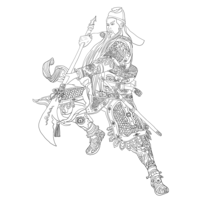1 遺書の書き換えで後継者が変更!
■ 1 遺書の書き換えで後継者が変更!
1 遺書の書き換えで後継者が変更!
後継者問題というのは今も昔も大変重要な問題でした。会社の場合後継者選びに失敗してしまうと一気に倒産してしまうなんて言うことになりかねません。そして三国志の時代ではこれを一歩間違えると国が滅びてしまうということになりかねませんでした。劉備にまだそこまで力が無かったころ、劉表(りゅうひょう)と共闘していた時期がありました。その劉表は死に際に後継者として長男の劉琦(りゅうき)を指名していたが周りの者の陰謀により遺書が書き換えられ次男である劉琮(りゅうそう)が劉表の後継者となってしまいました。そしてこの劉琦は孝行心にすぐれ、聡明だというのだからもったいないと言うばかりです。
2 董卓(とうたく)のでたらめ政治
■ 2 董卓(とうたく)のでたらめ政治
2 董卓(とうたく)のでたらめ政治
三国志の中でも最も悪役にされることが多いのが董卓です。董卓は残虐性で知られ「反董卓連合」を作らせるほどの大物でみんなが「董卓を倒さなければ」と思うほどの存在でした。そんな董卓はとにかくやることがでたらめ。一番のでたらめ政治と言ったら新貨幣の導入と言ってもいいでしょう。単なる銅片を貨幣としてしまいました。もちろんそんな貨幣として扱うことはできず、その貨幣では売買が成立することはできませんでした。とにかく何でもありと言った政策を打ち出す董卓の発想はやはりぶっ飛んでいますね。最後は養子とした呂布に倒されてしまうというのもなんとなく頷けます。
3 曹操(そうそう)の行った苦肉の策
■ 3 曹操(そうそう)の行った苦肉の策
3 曹操(そうそう)の行った苦肉の策
最終的に三国志の覇者のような扱いを受ける曹操(実際彼が三国をまとめたわけではありませんがその礎を築いた功績は大きい)ですが、実は何度も大敗を喫しています。そんな曹操ですが、ある時戦争が長引き、野営日数が多くなったことにより食糧難に陥ったことがありました。そんな時曹操がとった苦肉の策が食料を量る升を小さくするという策です。しかしますがあっけなく升が替えられたことに気づいた兵士たちは暴動を起こすことになるのですがなんと曹操は食料支給担当者が勝手にやったことだと言ってその首を取って難を逃れました。こんな感じでピンチでも逃げることができる曹操が覇者となったのです。
4 とにかく飲ませる張飛
■ 4 とにかく飲ませる張飛
4 とにかく飲ませる張飛
張飛は大の酒豪として知られ、酒による失敗もやらかしてしまいました。一番の失態は張飛が酔いつぶれている際に呂布の軍勢が城内になだれ込んでしまったため劉備(玄徳)の家族も置き去りにして逃げ出してしまいました。そんな張飛に対し自害しようとした張飛に対し劉備(玄徳)はそれを止めるどころか「妻子よりもお前の方が大事だ」という旨を伝えています。しかも張飛は飲むのが好きなだけでなく、飲ませるのも好きで酒を断った曹豹をむち打ちの計にしています。最後は部下に首を取られてしまうという笑えない結果になってしまいました。今で言ったら相当のパワハラ上司で話にならない人物ですが強い者には目をつむってしまうのは今も昔も変わりませんね。
5 最終的な勝者
■ 5 最終的な勝者
5 最終的な勝者
三国志をよく知らない人でも劉備や孔明、曹操は聞いたことがあるでしょう。そしてそれよりはちょっと三国志についての知識がある人は、三国が魏・呉・蜀の三国であることを知っているでしょう。しかし、私が昔読んだ三国志の漫画は孔明が死んだところで終わりましたし、曹操率いる魏が強すぎたため「最終的に魏が統一して終わったのかな」という漠然なイメージしかありませんでした。ところが三国志の終焉は魏の統一ではありません。魏が蜀を滅ぼした後、曹一族が築き上げた魏を司馬炎(しばえん)が簒奪、魏と蜀の地を晋(しん)としました。そして最後にその晋が呉を蹴散らして三国時代の終わりを迎えました。「結局そこ?」という感じですね。
6 三国志のその後
■ 6 三国志のその後
6 三国志のその後
上記5で記述したように三国志はなんとそれまでしのぎを削っていた「魏・呉・蜀」の勝利ではなく漁夫の利というような形で晋が幕を下ろしてしまいました(晋を魏という見方もできなくはありませんが)しかしその晋、長くは持ちません。天下を統一した晋の司馬炎がなくなると後を継いだ司馬衷(しばちゅう)が即位するといきなり勢力争いが勃発してしまいました。晋が天下を統一した24年後には劉淵(りゅうえん)が漢を建国してしまい、その7年後には晋が滅ぼされてしまいました。わずか31年で実質的に晋は滅びてしまったのです。それが起きたのが311年のことですが、なんと次に中国が統一されたのは589年(隋)です。遣隋使で有名ですね。
7 そもそも日本人の知っている三国志って?
■ 7 そもそも日本人の知っている三国志って?
7 そもそも日本人の知っている三国志って?
三国志って名前は聞いたことがあるけどいつの時代だか分からないし、「関羽が強すぎたり、孔明が頭良すぎたりなんか大げさすぎない?」と思う人もいることでしょう。それもそのはず、日本で知られている三国志というのは主に3世紀末に発表された歴史書である「三国志」と、7割の史実に3割の虚構を加えた歴史小説「三国志演義」があるからです。レッドクリフで、孔明が東南の風を吹かせるなどの神懸ったことは「三国志」ではありません。また曹操が悪者と言う印象が強いのは三国志演義で曹操が敵役として描かれたためです。ちなみに三国志演義は14世紀初頭に発表。著者は羅漢中(らかんちゅう)とも施耐庵(したいあん)とも言われています。
8 関羽の死後
■ 8 関羽の死後
8 関羽の死後
呉の武将呂蒙(りょもう)の罠にかかり関羽は息子の関平とともに殺されてしまったわけだが、その後が結構安っぽい話になってしまいました。なんとその呂蒙は関羽に呪い殺されてしまいまうというオチです。さらに孫権は関羽を殺したことで劉備(玄徳)がブチ切れているというのを知って関羽の首を曹操に送って怒りの矛先を曹操に向かわせようとしました。それまで何人もの死体が発生した三国時代において関羽の死だけはなぜか特別扱いされていました。ちなみに関羽の乗っていた赤兎馬も関羽の死後まぐさを食べようとせず数日後に死にました。関羽の死により劉備(玄徳)が強引な攻めに出たりと、関羽の死は三国志の中でかなりのターニングポイントとなりました。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志では現在では考えられないほどの珍プレーが存在していました。もちろん当時の人たちは大まじめにそれらを捉えていたわけですが、曹操や董卓のとった行動は「馬鹿だなぁ」と思ってしまいますよね。昔の豪傑は誇張されているだろうから凄さばかりが引き立ちますが珍プレーによりどこか「普通の人だったのかも」と思わせてくれると思ったのは私だけでしょうか。とにかく大真面目に生きた戦国時代でも「クスっ」と笑ってしまうようなことはあるので気軽に三国志に触れてもらえればうれしいです。