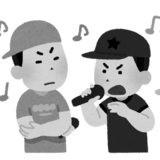歴史を支えた弁舌家たち
■ 歴史を支えた弁舌家たち
歴史を支えた弁舌家たち
三国志といえば戦乱の時代。歴史の節目には必ず大きな戦がありました。
しかし、いくら戦乱といっても、もちろん彼らも年中戦争をしていたわけではありません。
魏・呉・蜀の三国が擁立しそれぞれに基盤が出来てくると、大切になってきたのが、対外交渉でした。
そもそも三国が成立するキッカケとなった「天下三分の計」も、圧倒的大国になってしまった魏に対して、呉と蜀で連携して対抗しようという戦略のことです。
三国という形を維持するためにも、そして戦を有利に運ぶためにも、各国には他国と上手く連携を図り、自国を有利な展開へと導く交渉人が必須の存在でした。
そうした使者たちは、自国の君主から命じられた任務を遂行するために、相手国の君主や重臣たちと困難な交渉を行わなければなりませんでした。しかもそれだけでなく、他国の情報を収集し、場合によっては貿易なども行っていたそうです。
そのためそうした使者として選ばれるのは、待ち構えている相手と互角以上に渡り合える弁論術と、困難な状況にも物怖じせず向かっていける胆力を兼ね備えた、弁舌家たちでした。
というわけで今回は、そんな歴史の裏側で活躍した弁舌家たち同士が火花を散らした、名舌戦をご紹介していきたいと思います。
例え話でやり込める 諸葛亮 vs 張昭
■ 例え話でやり込める 諸葛亮 vs 張昭
例え話でやり込める 諸葛亮 vs 張昭
弁舌家といえばまず思い浮かべるのが、諸葛亮ではないでしょうか。諸葛亮といえば、劉備(玄徳)に仕えた稀代の大軍師で、その智謀は他に並ぶものが無いほど、とも言われています。
そんな諸葛亮には、やはり様々な舌戦の記録があります。今回はその中でも最も爽快な、呉の重鎮たちと行った問答をご紹介します。
新野の戦い・長坂の戦いに相次いで負け、呉との同盟を結ぶ必要にかられた劉備軍。これは諸葛亮が単身で呉へと使者として赴き、蜀呉で同盟を組んで曹操軍に対抗するように説得しにいったときのこと。立ち並ぶ呉の重鎮達を前に、諸葛亮は次々に彼らを論破していきます。
全ての問答を書くと余りにも長すぎるので、ここでは張昭との問答を抜粋します。
張昭「孔明先生が加わってからの劉備軍は負け続けでは無いですか?」と揶揄された諸葛亮。すぐさまそれに反論して曰く、
「重病人を回復させようと思ったら、まずは消化によい粥を食べさせ弱い薬で胃腸を整えます。そして次に肉を与えた後で強い薬を用いて完治させる。もしこの順序を守らなければ必ず取り返しの付かないことになります。現在の劉備軍はまさしくこの重病人なのです」
つまり、いきなり大きな勝利を望むのは間違いで、まずは軍備を整えて体制を立て直す、今はその時期である。ということを良い、張昭の皮肉を見事にかわしてみせたのです。
たった一言で大逆転! 孫権 vs 伊籍
■ たった一言で大逆転! 孫権 vs 伊籍
たった一言で大逆転! 孫権 vs 伊籍
お次は同じく蜀の使者、伊籍が孫権に接見した際のこと。
弁舌が巧だと言う噂の伊籍を前にして、その才を試してやろうという対抗心が湧き上がった孫権は、謁見が終わり拝礼して立ち上がった伊籍にすかさず言いました。
「無道の君主に仕えるというのはさぞかし苦労が多いであろう?」
孫権が言った無道の君主とはもちろん、伊籍が仕える劉備のこと。つまり孫権の言葉を裏読みすると、「あなたは有能だそうですけど、どうして劉備(玄徳)とかいう小物なんかに仕えているんです?」という感じでしょうか。
これに対して伊籍は間髪居れずに返答します。
「いえ、一拝一礼することに苦労などありませんよ」
この伊籍一言で、孫権の言った「無道の君主」という言葉の指し示す相手が、劉備(玄徳)から孫権にすげかわってしまったのです。
この見事というより他にない返答に、問答相手の孫権もいたく感服したそうです。
まるで詩を吟じるかのよう。薛綜 vs 張奉
■ まるで詩を吟じるかのよう。薛綜 vs 張奉
まるで詩を吟じるかのよう。薛綜 vs 張奉
今度は逆に、呉の弁舌家の活躍です。
蜀の使者である張奉が呉にやってきたとき、呉の大臣であるカン沢の名前の文字を取り上げ、意地悪い解釈でからかったのですが、カン沢はそれに対して上手く言い返すことができませんでした。
そこで同僚の薛綜が登場。張奉に話しかけます。
「蜀という字はなんでしょう。犬があれば獨(独の旧字体)となり、なければ蜀となる。目を横にして身を屈めて、その腹の中には虫を飼っている」
これは蜀という文字を分解した一種の言葉遊びであり、しかも「蜀」「獨」「腹」が韻を踏んだ形になっています。
張奉が苦し紛れに「では、呉はどうなのです?」と言うと、またしても薛綜が答えて曰く、
「口が無ければ天、口があれば呉(呉の異文体を、口の下に天と書いたため)。君は天下に臨む、天子の都」
これも同じく文字遊びでありつつ、しかも「呉」と「都」で韻を踏んだ言葉になっています。
この薛綜の即座の切り返しにその場に居た一同はどっと沸き、張奉はもはや何も言い返すことが出来なかったそうです。
打てば響くような問答! 秦フク vs 張温
■ 打てば響くような問答! 秦フク vs 張温
打てば響くような問答! 秦フク vs 張温
同盟国から使者が訪れると、君主への面会が終わった後で歓迎の宴会が開かれるのが常でした。そしてそうした席では、双方の知識人同士が、己の弁舌や知識を披露しあう舌戦が頻繁に行われていました。
これは、呉蜀同盟成立後に使者として蜀を訪れた張温をもてなす宴の席でのこと。張温は早速、秦フクに「あなたは学問をしたことがありますか?」と吹っかけて、舌戦のゴングがなりました。
張温は秦フクに謎掛けで挑みます。
張温「天には頭があるか?」
秦フク「『詩経』に『乃ち眷として西顧する』とある」
張温「では耳はあるか?」
秦フク「『詩経』に『鶴は九皋に鳴き、声は天に聞こゆ』と書いてある」
張温「では足は?」
秦フク「『天の歩みは艱難、この子猶らず』。これも『詩経』にある」
張温「では姓はあるか?」
秦フク「劉だ。天子の姓が劉氏だからです」
張温「……太陽は東から昇るではないか」
秦フク「東から昇り、西に沈むのです」
ここで言う東西とは、もちろん呉(東)と蜀(西)の位置関係のことです。秦フクは張温の意地悪な質問に詩経を引用し知識をアピールしただけでなく、天命が蜀にあるということまで言ってのけたのです。
この打てば響くような問答は、間違いなく秦フクの勝利でしょう。
まとめ
■ まとめ
まとめ
そんなわけで、舌戦名場面をご紹介してきました。
三国志の世界では、派手な戦や駆け引きの裏側で、こうした外交行為が日々行われていたと言われています。兵を動かしての戦いだけではない、こうした言葉の戦いの面白さが少しでも伝われば幸いです。
物事を有利に運ぶために、現代でも必要となる交渉術。
遥か1000年以上前の文官たちの言葉にも、まだまだ学ぶことが多そうですね。
ちなみに、公式に敵対関係だった魏と蜀の間では、こうした使者のやり取りは、一切が記録として残っていないそうです。蜀が魏に対してもう少し交渉をしていれば、もしかしたら違った歴史があったかもしれませんね。